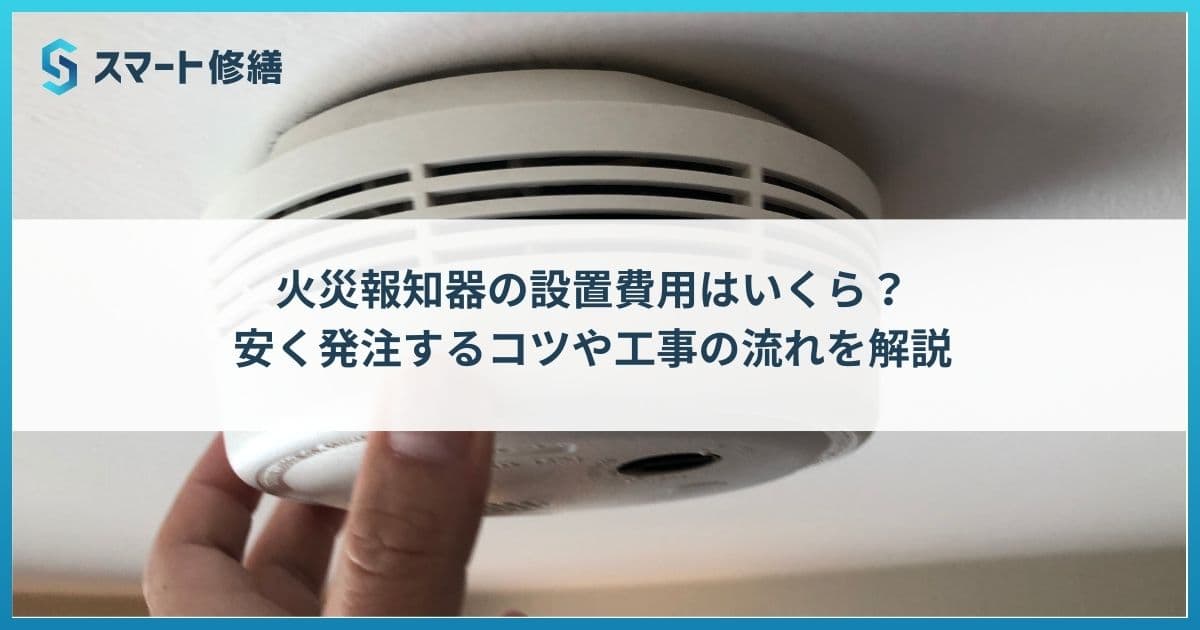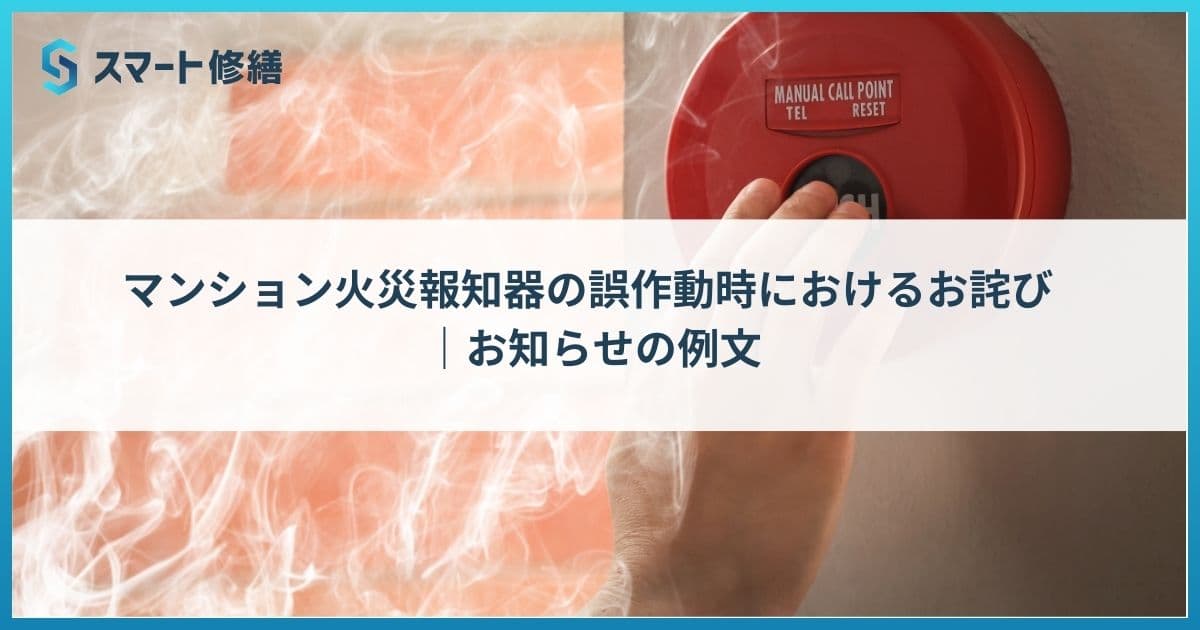火災報知器の寿命は何年?耐用年数・交換時期・費用、依頼時の注意点
更新日:2025年03月11日(火)
本記事では、火災報知器の寿命や交換時期、費用について最新の一次情報を基に解説し、管理組合として知っておくべきメンテナンスのコツも紹介します。
- 本記事のポイント
- 火災報知器の寿命は約10年が目安であることがわかる。
- 火災報知器の異常や誤作動が増えたら交換時期のサインだと理解できる。
- マンションでは一斉交換により、安全性向上と費用削減が可能だと学べる。
火災報知器の寿命は何年?法定耐用年数とメーカー差
一般的に火災報知器の寿命は約10年とされています。自動火災報知器や住宅用火災警報器は常に火災を感知するため待機していますが、内部のセンサーや電子部品は経年劣化するため、設置後10年程度で適切に作動しなくなる可能性があります。
総務省消防庁も「火災報知器の寿命は10年」と公式に案内しており、設置から10年を目安に本体の交換を推奨しています。これは法律上の義務というより、消防当局やメーカーが定める安全上の耐用年数と考えるとよいでしょう。
各メーカー製の火災報知器で寿命に大きな違いはなく、ほとんどの製品が約10年を交換目安としています。実際、日本火災報知機工業会による「とりカエル」というキャンペーンでも、全国一律で「10年経ったら火災警報器を取り替えましょう」と呼びかけています。メーカー間で多少デザインや機能(連動型や音声案内機能など)の違いはありますが、センサーの基本性能や寿命に大差はありません。つまりどのメーカーでも10年程度で交換が必要になる点は共通しています。
マンション管理組合としては、設置から何年経過したかを把握し、特に2006年前後の義務化以降に設置された火災警報器は更新時期を迎えている可能性が高いことに注意しましょう。10年を超えた機器は早めの交換計画を立てることが肝心です。
交換時期の見極め方:寿命サインと点検ポイント
火災報知器の交換時期を見極めるには、以下のポイントに注目します。
設置後の経過年数
前述のとおり設置から約10年が経過したら交換時期です。本体に記載の製造年月や設置年月を確認し、10年を超えていれば新品への交換を検討しましょう。
定期点検での動作確認
管理組合では半年に1度の消防設備点検を実施しているはずです。その際、各住戸内の火災警報器や共用部の感知器の動作を確認します。テストボタンを押しても警報が鳴らない、ランプが点灯しないなどの動作不良が見られた機器は寿命切れや故障の可能性が高く、交換が必要です。
警報音や動作の異常
火災報知器が寿命に近づくと、警報音に異常が出ることがあります。たとえば住宅用火災警報器では、一定間隔で「ピッ」という電子音が定期的に聞こえる場合、それは電池切れ(=寿命)を知らせるサインです。多くの住宅用警報器は電池寿命が約10年で、電池が切れる際に電子音で知らせる機能があります。このような警告音が出たら、本体ごと速やかに交換しましょう。
誤作動や感度低下が増えた
経年によりセンサーにホコリが溜まったり回路が劣化すると、火災でもないのに警報が鳴る誤作動が増えたり、逆に本当の煙・熱に反応しづらくなるケースがあります。経年劣化は誤作動の大きな原因であり、この場合は劣化した報知器を交換することで対処できます。最近誤報が増えた機器や感知性能に不安がある機器も交換時期と言えるでしょう。
以上の点から、「10年」「動作不良」「警告音」「誤作動増加」が交換の4大サインです。特にマンション全体で設置から10年以上経過している場合は、一斉に交換する計画を立てることで、交換漏れによる事故リスクを防ぐことができます。日頃から各住戸や共用部の火災報知器の状態を把握し、異常の兆候があれば早めに手を打ちましょう。
火災報知器の交換費用の相場:本体価格と工事費
火災報知器交換にかかる費用は、機器の種類や台数によって幅があります。大きく分けて「各住戸内に設置する住宅用火災警報器」と、「共用部などに設置する自動火災報知設備の感知器(煙感知器・熱感知器)」で相場が異なります。
住宅用火災警報器(各住戸内の独立型警報器)
ホームセンターや防災設備店で1台あたり約2,000円~16,000円ほどで購入できます。機能や音量によって価格帯に幅がありますが、ベーシックなもので約3,000円前後が一般的な本体価格です。取り付けを業者に依頼する場合、工事費は物件の戸数や設置個数によります。例として、50戸規模のマンション全住戸で住宅用火災警報器を交換するケースでは、工事費用が全体で約5万~10万円程度(本体代別途)となり、作業は1日で完了することが多いです。一戸あたりに換算すれば工事費は1,000~2,000円程度と考えられます。入居者自身で交換可能なケースもありますが、安全確実に作業するために業者依頼が望ましいでしょう
共用部の感知器(自動火災報知設備の一部)
マンションの共用廊下やエントランスに設置されている煙感知器・熱感知器は、自動火災報知設備(自火報)の感知器です。これらは住宅用に比べ高機能・高信頼性の機器であるため単価も高めです。例えば、煙を感知する光電式スポット型感知器の場合1台あたり約4万円、熱を感知する差動式スポット型感知器は1台約1万5千円が更新工事費用の一例です。この費用には機器代と交換作業費が含まれるケースですが、機種や設置場所によって変動します。
マンション全体の自動火災報知器を一式更新する場合は、受信盤など他の機器も含め100万円以上のまとまった費用となることもあります。共用部感知器の交換は、消防設備の専門業者に依頼して適切な機種選定・交換工事・消防署への申請まで行ってもらう必要があります。
コストを抑える方法
一度に複数台をまとめて交換することで単価を下げるのが基本です。管理組合として計画的に全戸の警報器を一斉交換する方式をとれば、故障のたびに個別に交換するよりも割安になる傾向があります。また、自治体によっては住宅用火災警報器の設置・交換に補助金を出していることもあります。高齢者世帯向けの補助など条件付きの場合もあるので、自治体の防火担当部署に確認してみましょう。
火災報知器の更新費用は、建物の構造や既存設備の状態、交換範囲によって大きく変わるため、「どこに無駄が潜んでいるか」を把握するのは簡単ではありません。当社「スマート修繕」では、余計な工程を省きつつ最適な更新プランを導き出す専門知見を活かし、必要以上の出費を避けられるようサポートしています。検討のタイミングでご相談いただければ、将来的に気づかず選んでしまう割高な工事を未然に防げる可能性が高まります。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
工事依頼のコツ:タイミングと業者選びのポイント
工事依頼のコツは大きく3つあります。
その1 複数の時業者から見積もり金額を取得する
まずは相見積もりを取得しましょう。この業界は、工事を依頼する業者によって金額が乱高下するのが特徴です。それを知らずに1社だけの見積もりをそのまま受け入れると大損するおそれがあります。そのため、複数の業者から見積もりを取得して、金額を見比べてることがスタートしましょう。
その2 過去の実績を調査する
続いて、過去の工事実績を調べてみましょう。見積もり金額を比較検討した後、自分たちの場合は「いくら適正金額なのか?」を把握しなければいけません。具体的には、類似の工事実績で公開されている情報をインターネット等の手段で調べてみてください。そこで提示されている金額と見積書に乖離ががある場合、金額を下げる交渉の余地があります。
その3 専門家に相談する
最後に、最も安全かつ確実なコストダウンを実現するなら、実績のある専門家に相談するのが適切な手段です。工事は専門知識が必要なので、事業者と交渉してもうまく状況をコントロールするのが難しいのも実情です。だからこそ、うまいこと専門家を活用してコストダウンさせるのも賢い選択なのです。
特に、過去の実績を調べたときに、工事内容と類似の案件に携わっているのならば、初期費用をかけない無料相談を実施しているところ活用して、コストダウンの可能性を模索しましょう。
お問い合わせ件数、数千組合様以上!
修繕のプロにぜひお任せください!!

Webから無料相談
専門家に相談する
火災報知器の誤作動が多すぎるときの対応:原因の見極めとメンテナンス
「やたらと火災報知器が誤作動して困る」という場合、その裏には設置環境や機器状態に原因があることが多いです。考えられる主な原因と対処法を確認しましょう。
ホコリ・虫の侵入
煙感知式の警報器は、内部にホコリや小さな虫が入り込むと煙と誤認して警報が鳴ることがあります。定期的に警報器周辺を掃除機で吸い取り掃除する、殺虫剤のくん煙剤を使用する際は警報器にカバーをするなど、異物が入らないよう工夫しましょう。もし内部に汚れが蓄積している場合は清掃や本体交換で改善します。
結露や水漏れ
上階からの水漏れや湿度の高い場所での結露が感知器内部に発生すると、回路がショートしたり誤検知を引き起こすことがあります。特に熱感知器は水濡れで接点が錆びて誤作動するケースもあります。水がかかった形跡がある場合は十分乾燥させ、それでも再発するようなら交換を検討します。
急激な温度変化・風
エアコンの温風が直接当たる場所にある熱感知器は、急な温度上昇と判断して鳴ってしまうことがあります。また強い風が感知器に当たると圧力変化で誤報を起こすこともあります(台風接近時の気圧変化など)。対策として、エアコンの風向きを変える、感知器やエアコンの位置を見直すなど物理的条件を調整します。気圧変化によるものは防ぎづらいですが、頻発する場合は機器交換も検討しましょう。
機器の劣化
前述のように経年劣化した感知器そのものが誤作動を起こすケースも少なくありません。古い機種で誤報が多発するようなら、最新の機種に交換することで改善できる可能性が高いです。特に差動式熱感知器では内部の小さな穴(リーク孔)が詰まりやすく、予期せぬタイミングで作動することがありますが、交換すれば解決します。
対応策
火災報知器の誤作動が起きた場合は、まず本当に火災かどうか確認し(後述の緊急対処参照)、原因を推定して取り除くことが大切です。環境要因であれば上記のような対処を行い、機器不良であれば部品交換や本体交換を行います。また誤作動が頻発する間は、万一に備えて火災が起きていないか念入りに確認する習慣も重要です。一度原因を取り除いても再び誤報が起こる場合は、プロの業者に相談して点検してもらいましょう。誤作動続きで「また誤報だろう」と油断していると、いざ本当の火災時に見逃す危険もあります。常に設備は万全に維持しつつ、一つ一つ原因を潰していくことが求められます。
夜中に誤作動したときの対処法:深夜に警報が鳴った場合の手順
真夜中に突然火災報知器が鳴り出すと非常に驚きますが、落ち着いて適切に対処することが大切です。夜間に警報が作動した場合の基本的な対応手順と、誤作動だった場合の対処・再発防止策を整理します。
火災の有無を確認する
警報音が鳴ったら、まず本当に火災が発生していないか迅速に確認します。部屋の中や周囲に煙や火の手がないか目視で確認し、火の元(コンロやストーブなど)の安全をチェックしてください。マンションの場合、自室だけでなく廊下に煙がないか、隣室で火災の気配がないかも注意します。火災の疑いが少しでもある場合は躊躇せず119番通報と避難を優先します。たとえ誤作動かもしれなくても、万一火災だった場合に通報が遅れると致命的になりかねません。
警報を止める
火災ではないと判断できたら、火災報知器の警報を一時停止させます。住宅用火災警報器であれば本体の停止ボタンを押すか停止紐を引くことで警報を止めることが可能です。機種によっては踏み台なしでも紐を引いて止められるものもあります。電池式であれば電池を外す方法もありますが、再度取り付ける際に誤報が再開する恐れがあるので、基本は停止ボタンで対応しましょう。一方、マンションの共用部などに設置された自動火災報知器のベルが鳴っている場合、住民だけで勝手に警報を止めることはできません。管理人室や防災センターにある火災受信盤を操作しないと停止できない仕組みのため、管理員や警備会社に連絡を入れて対応してもらいます。深夜で管理人が不在の場合は、契約している警備会社(ALSOKやSECOMなど)の緊急連絡先や、消防署に「自動火災報知器が鳴っているが火災ではない可能性が高い」旨を連絡し指示を仰ぐとよいでしょう。
原因の究明と再発防止
火災報知器の警報を停止した後は何が原因で作動したのかを探ります。料理の煙や湯気が原因なら換気を行い、以後は換気扇を回す・窓を開けるなど注意します。ホコリが原因なら掃除をし、虫の可能性があれば忌避策を取ります。電池切れが原因の場合は電池を新しいものに交換し、それでも誤報が続くようなら本体を取り替えます。経年劣化した古い機器であれば、この機会に新品へ交換することが根本的な解決策になります。再発防止のため、しばらくは通常より頻繁に点検テストを行ったり、夜間でもすぐ対応できるよう管理体制を整えておくと安心です。
深夜の火災報知器は大きな不安を伴いますが、「火災時は人命第一」「誤作動時でも慎重に対応」が鉄則です。特にマンションでは他の住民も動揺しますので、管理組合として冷静な対応マニュアルを周知しておくと良いでしょう。誤作動でも遠慮せず消防に通報すべき場合もありますし、逆に明らかな誤報で消防出動を避けたい場合は監視サービス会社への連絡体制を確認しておくなど、想定シナリオごとに適切な対処を準備してください。
まとめ|寿命を迎える前に定期的な点検と適切なメンテナンスを
火災報知器は「設置したら終わり」ではなく、定期的な点検と適時の交換が不可欠な安全設備です。マンション管理組合として、防災設備の維持管理には常に最新の注意を払いましょう。
適切なメンテナンスを行っていれば、万一の火災発生時に火災報知器が確実に作動し、大切な命と財産を守ってくれるはずです。住民の安心安全のため、ぜひこの記事を参考に火災報知器のチェックと交換計画を進めてください。
火災報知器等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- 自動火災報知設備やインターホンのリニューアル工事の支援実績は多数(過去半年で数千戸分、2025年1月現在)。数百戸の多棟型マンションでの実績も複数。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。インターホンのメーカー系のを含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料