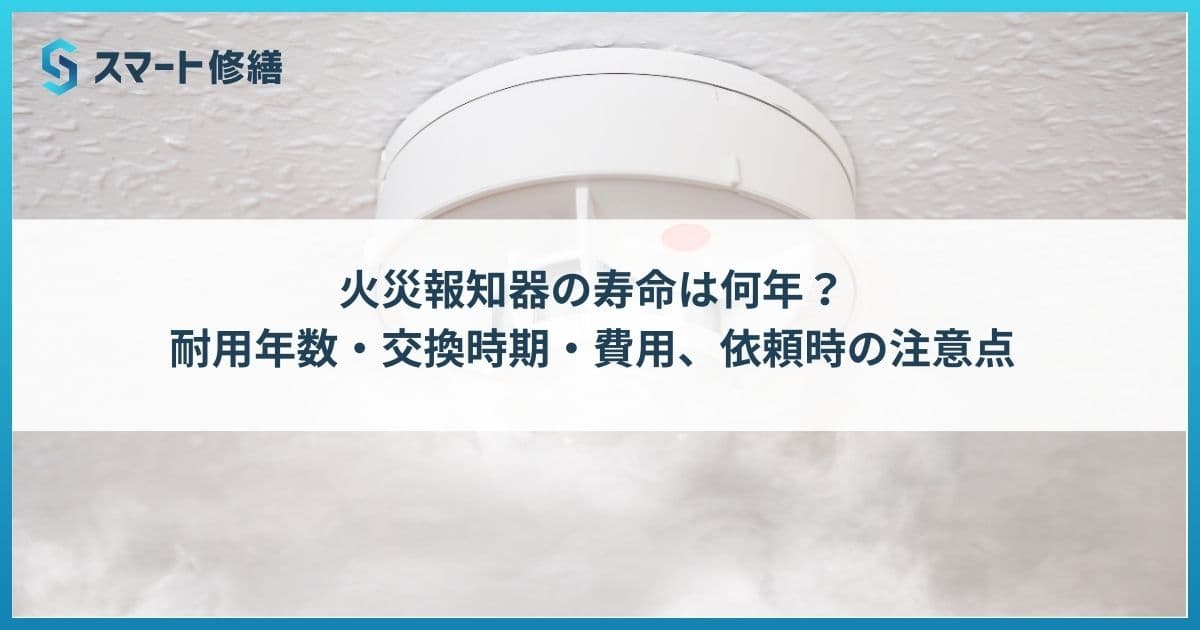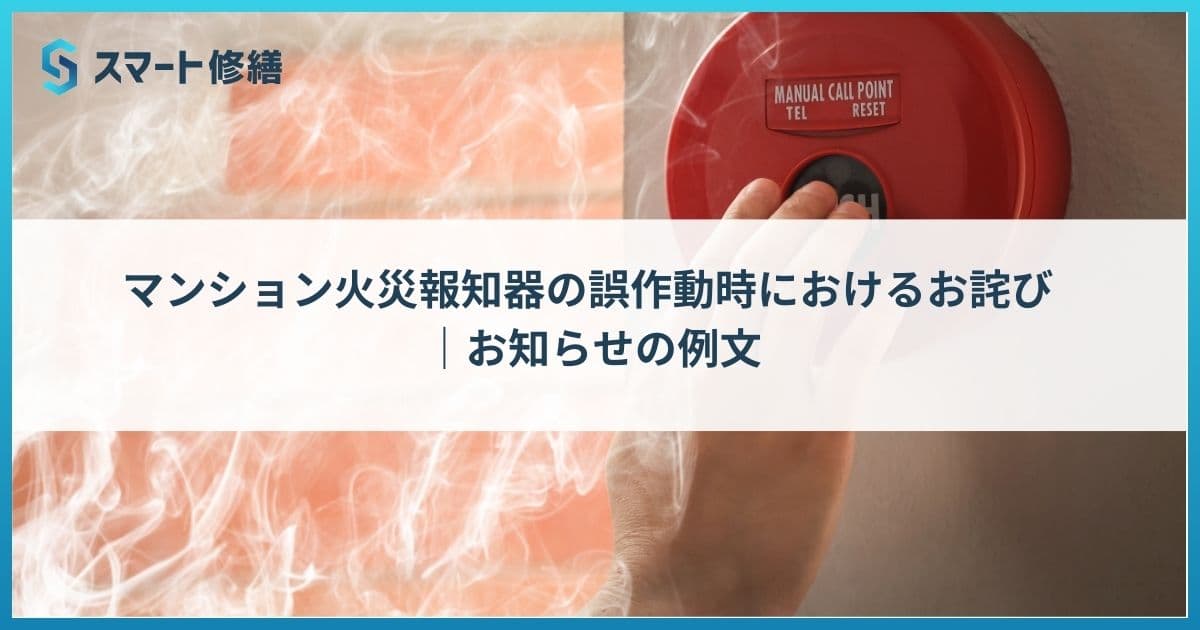火災報知器の設置費用はいくら?安く発注するコツや工事の流れを解説
更新日:2025年03月11日(火)
火災報知器(住宅用火災警報器)は火災の早期発見に欠かせない設備です。法律の改正により、すべての住宅で設置が義務化されており、安全な暮らしのためマンションやタワマンでも適切に火災報知器を設置・維持する必要があります。 しかし、「設置にはどんなルールがあるのか?」「設置費用はどのくらいかかるのか?」「安く設置する方法はある?」と疑問に思う管理組合やオーナーの方も多いでしょう。 本記事では火災報知器の設置ルールや設置費用の相場、設置費用を安くするコツ、工事の流れ、さらにオーナーが依頼する際の注意点やDIY設置の可否まで詳しく解説します。
- 本記事のポイント
- 火災報知器の適切な交換タイミングや耐用年数を理解できる。
- 設置・更新費用の相場と予算を抑えるためのポイントがつかめる。
- 火災報知器の誤作動が起きる理由と効果的な対策が身につく。
自動火災報知器/住宅用火災警報器の設置ルール(法律・設置基準・マンションとタワマンの違い)
火災報知器(住宅用火災警報器)は、火災の早期発見に欠かせない設備であり、2011年6月以降、すべての住宅で設置が義務化されました。一戸建てや共同住宅(マンション・アパート)、店舗併用住宅も対象です。
マンションの設置基準では、各住戸に住宅用火災警報器を設置するほか、延べ床面積500㎡以上のマンションには自動火災報知器の設置が義務付けられています。自動火災報知器は、感知器や発信機、受信機で構成され、建物全体で火災を検知・警報します。さらに、各自治体の条例により、居室・階段・台所に煙感知式・熱感知式の警報器を設置することが求められています。
タワーマンション(タワマン)の防災基準では、高さ31m超(11階建以上)の建物には、自動火災報知器に加え、スプリンクラー設備や避難設備の設置が義務付けられています。火災報知器はインターフォンと連動し、警報が迅速に各住戸へ通知される仕組みになっています。
設置義務があるにもかかわらず、火災報知器の未設置は罰則がないため見落とされがちです。しかし、火災時の安全確保のため、設置基準を守ることが非常に重要です。
自動火災報知器/住宅用火災警報器の設置費用(相場・建物タイプ別の違い・コスト要因)
マンション全体の自動火災報知器の導入費用は、建築された年代や設置されている機器によって大きく変わるのが前提ですが、
- 中規模マンション(500㎡超、23戸):約128万円(1戸あたり5~6万円)
- タワーマンション(高層賃貸):500万円~数千万円
自動火災報報知器は、受信盤や配線工事が必要なため、高額になりがちです。
費用を左右する主な要因
1.建物の広さ・階数(戸数が多いほど設備台数が増える)
2.機器の種類(煙式センサーは約4万円、熱式センサーは約1.5万円)
3.新築か後付けか(後付けは配線工事の手間がかかる)
住宅用火災警報器の設置費用は、
- 単独型(電池式):1台2,000~3,000円(高機能品は1万円前後)
- 業者に依頼する場合:1台あたり数千円の工賃が加算
寝室2部屋+階段+台所の計4台設置する場合、機器代1万円+工事費で2万円程度が目安となります。
火災報知器の設置費用は、数千円から数百万円と幅広いため、管理組合やオーナーは事前に適切な予算計画を立てることが重要です。
火災報知器の設置費用を安くするコツ
火災報知器の設置にかかる費用をできるだけ抑えるためのコツをいくつかご紹介します。業者への発注方法から公的制度の活用、DIYまで、知っておくと安く安全に設置するために役立つポイントです。
複数業者から相見積もりを取る
・価格や工事内容を比較し、不必要な提案を避ける。
・特にマンション全体の工事では2〜3社以上から見積もりを取得。
まとめて発注してコスト削減
・インターフォン設備の更新と同時に発注すると、作業費の削減が可能。
・大規模修繕と並行して行うことで、足場代・工事費の削減が期待できる。
国や自治体の補助金・助成金を活用
・高齢者世帯向け補助や、防災力向上助成を受けられるケースもある。
・市区町村の制度を確認し、適用可能なら活用する。
DIY(自分で取り付け)
・住宅用火災警報器(電池式)は天井や壁にネジで固定するだけなので、個人でも設置可能。
・業者依頼では1台あたり数千円の工賃がかかるが、DIYなら機器代のみで済む。
・ただし、高所作業には注意し、安全確保を優先することが重要。
これらの方法を活用することで、火災報知器の設置費用を抑えつつ、適切な防火対策を実施できます。
火災報知器の設置費用は建物の構造や既存設備の状態によって大きく変動し、実際には「どこにどれだけ最適化の余地があるか」を判断するのが難しい場合もあります。こうしたときは、余計な工程を省きつつ必要な部分だけを的確に見極められる専門家に一度相談してみることで、思わぬコスト削減のヒントが得られることがあります。検討段階で相談を後回しにしてしまうと、知らず知らずのうちに割高な工事を選んでしまうことも。まずは気軽に専門家の見解を聞いてみるだけでも、よりムダのない判断につながります。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
火災報知器の設置工事の流れ
ここでは火災報知器設置工事の一般的な流れを解説します。業者に依頼する場合、事前準備から完了後までどのように進むのか把握しておくと、管理組合やオーナーとして適切に対応できます。
事前調査と設置計画の立案
・業者が建物の現況を確認し、適切な設置箇所を決定。
・消防法に準拠した配置計画を策定。
消防署への工事申請
・自動火災報知設備の新設・増設には消防署への届け出が必要。
・申請後、消防署の許可を得て工事開始。
機器の取り付け・配線工事
・天井や壁内に配線を通し、感知器や警報ベルを設置。
・配線工事の難易度によって費用が変動。
動作テスト・消防検査
・感知器の煙テスト、警報作動確認を実施。
・消防署の検査を受け、合格すれば工事完了。
引き渡しと維持管理計画の確立
・設置後の使用方法を関係者へ説明。
・定期点検とメンテナンスの計画を策定。
火災報知器は設置して終わりではなく、適切な管理・点検を継続することが重要です。設備の老朽化や故障に備え、長期的な維持管理計画を立てておくことが求められます。
マンション管理組合・オーナーが火災報知器の設置工事を依頼する際の注意点
マンション管理組合やオーナーが火災報知器を設置する際には、以下の点に注意が必要です。
管理組合の合意を得る
分譲マンションでは、共用部の設備工事には管理組合の承認が必要です。理事会や総会で計画を共有し、費用負担の明確化や住民の理解を得ることが大切です。賃貸物件の場合も入居者への周知が不可欠となります。
入居者・周辺住民への配慮
工事中の騒音や作業員の出入りに配慮し、事前通知や試験時の警報音周知を徹底します。特に室内設置時は、立ち会いや鍵預かりの対応を丁寧に行うことが重要です。
信頼できる業者の選定
消防設備士の資格を持ち、消防署への申請代行や完了検査に対応できる複数社の見積もりを取得し、相場を把握することが重要です。
設置後の維持管理
設置後も定期点検と交換が必要です。消防法で年1~2回の点検が義務付けられており、火災報知器は10年程度で交換が必要となります。維持管理計画を立て、専門業者と契約するのが望ましいです。
自分で火災報知器を設置・交換できるのか?
費用を抑える方法の一つとして、火災報知器を自分で設置・交換(DIY)できないか検討する方もいるでしょう。結論から言えば、住宅用火災警報器の設置・交換は基本的にDIY可能ですが、自動火災報知設備の施工は消防法上、有資格者のみ施工可能です。
DIY可能なケース
住宅用火災警報器(電池式)は、自分で設置することも可能です。
工具と脚立があれば、比較的簡単に取り付けられ、コストも抑えられます。
実際、「4個セットで8,000円程度で購入し、安く簡単に設置できた」という声もあります。
DIYの注意点
・高所作業による落下リスクに注意
・取り付け位置を説明書通りに守る(煙感知式は壁から60cm以上離すなど)
・連動型(無線式)の設置には専門知識が必要
DIY不可のケース
マンション共用部の火災報知器設置・交換は、消防法上、有資格者のみ施工可能です。
自動火災報知設備(感知器・受信盤など)の施工は専門業者に依頼する必要があります。
配線工事や消防署の申請が必要なため、資格がないと工事ができません。
DIYによりコスト削減が可能ですが、確実に作動することが最優先です。不安がある場合は、一部DIYを行い、最終的な点検だけ業者に依頼するのも有効な方法です。総じて、DIYできるのは「戸建てや個別住戸内の独立型警報器まで」と考えるのが賢明です。「安く済ませたいが、ちゃんと火災時に作動するか心配…」という場合は、無理せず専門業者に依頼しましょう。重要なのは、適切に設置され確実に作動することです。
まとめ
火災報知器は命と財産を守る保険のようなものです。適切な設備を適正な費用で導入し、賢くコストを抑えつつ、しっかりと維持管理していくことが理想です。
本記事で解説したポイントを踏まえ、信頼できる専門家の力も借りながら、安全・安心な住まいづくりを進めてください。火災報知器は「備えあれば憂いなし」の代表格。この機会にぜひ見直し、万全の体制で万が一に備えましょう。
火災報知器等修繕工事の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- 自動火災報知設備やインターホンのリニューアル工事の支援実績は多数(過去半年で数千戸分、2025年1月現在)。数百戸の多棟型マンションでの実績も複数。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。インターホンのメーカー系のを含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料