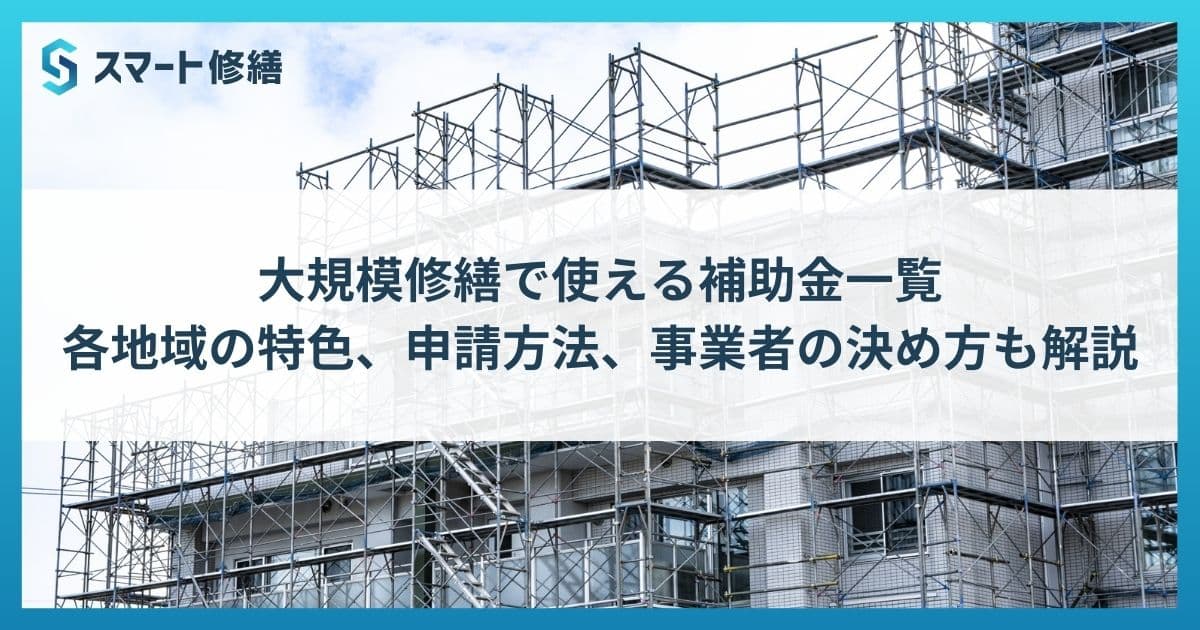マンションのサッシ交換と補助金の重要性とは?
更新日:2025年10月31日(金)
- 本記事のポイント
- 高性能サッシ交換で省エネ・防音・快適性を向上させ、資産価値もアップする効果がわかる。
- 国や自治体の補助金制度を活用し、費用負担を大幅に軽減する方法が理解できる。
- 補助金申請の手順や注意点、管理組合との合意形成など、トラブルを防ぐ実務知識が得られる。
マンションのサッシ交換と補助金の重要性とは?
マンションで古い窓サッシを高性能なものに交換することは、断熱性・防音性を飛躍的に向上させ、快適な住環境と資産価値の向上につながる重要な取組みです。また国や自治体の補助金を活用すれば、費用負担を大きく軽減できます。
一般に住宅の中で窓は熱や音が出入りしやすい弱点であり、省エネと居住性向上の鍵を握ります。実際、冬場に室内の暖房熱が逃げる原因の約5~6割が窓など開口部と言われています。夏も強い日射や外気熱の侵入の多くが窓経由で起こります。そのため古い単板ガラス・アルミ枠の窓を断熱性能の高い複層ガラスサッシや二重窓に換えると、冷暖房効率が格段に向上し光熱費削減につながります。加えて窓の気密性が高まることで外部騒音の遮断効果も大きくなり、交通量の多い道路沿いでも室内の静けさを確保しやすくなります。
国も住宅分野の省エネ促進策に力を入れており、高性能な断熱リフォームを支援するため多額の予算を投じています(例:先進的窓リノベ事業には環境省予算1,350億円が充てられました)。実際に補助制度を活用してマンション全戸の窓ガラスを高断熱仕様に改修した事例では、結露の大幅な軽減や室内環境の改善が報告されています。居住満足度が上がれば資産価値の向上にも直結するため、サッシ交換はマンション管理組合や区分所有者にとって検討する価値の高い施策といえます。
例えば北海道など寒冷地では窓の断熱改修による効果が顕著で、多くの自治体が窓リフォーム支援策を講じています。マンション管理組合が中心となり補助金を活用して一斉にサッシ交換工事を行えば、各戸の負担を抑えつつ建物全体の省エネ性能と快適性を一挙に高めることができます。
エネルギー価格高騰やカーボンニュートラル推進の流れもあり、マンションの窓交換は今まさに計画的に進める意義が大きいでしょう。マンションのサッシ交換で断熱・防音性が向上し、光熱費削減や資産価値アップも期待できます。国や自治体の補助金制度を活用し、計画的な窓リフォームで快適で省エネな住まいを実現しましょう。
利用できる主な補助金制度(国・自治体・2025年版)
マンションのサッシ(窓枠・ガラス)交換や断熱化リフォームに対して活用できる補助金制度には、大きく分けて 国が実施する「住宅省エネ2025キャンペーン」 による支援事業と、 各地方自治体が個別に設ける補助・助成制度 があります。これらを組み合わせることで、窓リフォームの費用を大幅に軽減できる可能性があります。
国制度の中心となるのは、環境省が推進する「先進的窓リノベ2025事業」で、戸あたり最大で 200万円の補助が設定されており、工事費用の1/2 相当額(定額補助)を支援する仕組みです。また、子育てグリーン住宅支援事業など、窓改修を含むリフォームを支援する関連制度も用意されています。
窓の交換や内窓設置の場合、補助額は窓の大きさ・性能・工法・グレードによって変動します。たとえば内窓 Sグレードの大サイズで約 65,000 円補助等の例も公表されています。一方で、2025年では内窓補助金額の見直し・減額傾向が報じられており、注意が必要です。
制度運用上の注意点として、2025年9月15日以降に設置される外窓・ドアについては、補助対象要件が見直されており、窓数を増やすような改修は原則補助対象外となる可能性があります(ただし断熱等性能等級5を満たす証明があれば例外となる可能性あり)。また、補助金申請は予算上限到達で締切となるため、早めの申請が肝要です。
申請の手続きには、事前に窓リノベ事業者登録をした登録施工業者を介する必要があります。申請書類(契約書、性能証明書、工事写真など)をオンラインで提出する形になります。
地方自治体においても、国制度とは別枠で窓改修・断熱リフォーム補助を行っているケースが多数あります。東京都では戸あたり最大 130 万円の助成を行う制度も報じられています。大阪府・大阪市では窓・外壁断熱改修と設備改修を含む省エネ改修補助があり、補助率や上限額例が公開されています。また、豊中市では窓改修を対象とした補助金(材料費 1/3、上限 20 万円)を設けているなどの事例もあります。
これら自治体制度は、国補助と併用できる場合も多いため、両制度の要件や重複申請可否を事前に確認し、最も有利な組み合わせを検討することが重要です。
マンションの場合、管理組合として国補助+自治体補助を組み合わせて申請を行えば、窓改修プロジェクトの費用をかなりの範囲で補助金でまかなえる可能性があります。ただし、制度の適用可否・手続き条件・申請締切日は地域や年度によって変わるため、まずは信頼できるリフォーム事業者に相談し、利用可能な補助制度を確認することをおすすめします。
対象となるサッシ交換の条件と仕様(2025年版)
補助金を受けられるサッシ交換工事には、一定の条件や性能基準があります。主な要件は、既存住宅であること、高断熱性能を持つ登録製品を使用すること、そして国の補助事業に登録された施工業者による工事であることです。
「先進的窓リノベ2025事業」など国の制度では、新築直後の住宅は対象外で、すでに居住・使用実績のある既存住宅が対象となります。また、補助の目的が省エネ性能の向上にあるため、交換後のサッシ・窓は Uw値1.9W/m²K以下程度 の高断熱性能を有する製品であることが求められます(性能区分により異なります)。
対象となるのは、二重サッシ用の内窓や高断熱複層ガラス窓など、国が定めた性能基準を満たす登録製品です。例えば東京都など一部自治体の助成制度では、国の補助対象製品または北海道環境財団の登録製品であることが交付条件とされています。これは製品の断熱・気密性能が公的に保証されたものに限定することで、補助金の効果を確実にする狙いがあります。
補助対象となる工法も幅広く、内窓の新設、既存枠を活かしたカバー工法による外窓交換、高性能ガラスへの交換、さらには玄関ドアの断熱改修まで含まれます。マンションの場合、専有部分内で行う内窓設置が比較的容易に実施できる一方、外窓サッシの交換は外観や防水への影響があるため、カバー工法など専門的な施工が一般的です。
なお、補助対象額の合計が5万円未満となる場合は申請できません。対象要件を満たすためには、事前にリフォーム会社を通じて製品のカタログスペック(Uw値・遮音性能など)を確認し、性能証明が取れる製品を選ぶことが重要です。特に「アルミ樹脂複合サッシ+Low-E複層ガラス」の組み合わせは補助対象になりやすい仕様です。性能が基準に満たない場合は補助対象外となるため、工事契約前に必ず施工業者と交付要件を確認し、条件に適合するサッシを選定しましょう。
補助金申請の流れと必要書類
補助金の申請手続きは基本的に施工業者(事業者)が代行して行い、区分所有者や管理組合は必要書類を準備して協力する形になります。工事完了後に申請・審査を経て補助金が支給されるため、着工から入金まで数か月程度のスケジュールに余裕を持つことも大切です。
国の住宅省エネ補助事業では、補助金の申請者はリフォーム事業者として定められており、一般の消費者(施主)は施工業者から補助金の還元を受ける仕組みです。このため窓リフォームを依頼する際には、その業者が補助事業に登録済みかどうか(いわゆる「住宅省エネ支援事業者」であるか)を確認する必要があります。申請はオンラインで行われ、工事内容や使用製品の証明書類一式を業者が取りまとめて提出します。管理組合が一括して申し込む場合も、実際の手続きは請負業者が代理で行います。
補助金申請の一般的な流れは次の通りです。
まず補助対象工事を扱う施工業者と工事契約を締結し、着工前に業者がオンライン上で交付申請の予約登録を行います。その後工事を実施し、完了後に正式な交付申請書類の提出となります。提出書類には工事請負契約書の写し、工事内容の写真、製品の性能証明書のほか、工事発注者(施主)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等のコピー)や住民票などが含まれます。必要書類の準備は基本的に業者側が案内してくれるため、指示に従い書類提供や署名捺印を行えば難しい作業はありません。審査は事務局で行われ、問題がなければ交付決定となります。
気を付けたいのは補助金の振込時期です。補助金は工事完了後の交付決定を経てから支払われる後払い方式であり、実際に施主が受け取るまで完了から3~4か月程度要するケースがあります(申請時期や事務局の処理状況による)。その間、一時的にリフォーム代金の全額を自身で支払っておく必要がある点に留意しましょう。ただし補助金相当額は後日確実に還元されますので、資金計画上は「忘れた頃に補助金が振り込まれる」くらいの心構えで待つと良いでしょう。管理組合で実施する場合も同様に、補助金入金までの間は修繕積立金等から立て替えを行い、補助金受領後に精算する流れとなります。
サッシ交換による効果(省エネ・防音・資産価値)
高断熱サッシへの交換により冷暖房エネルギー消費の大幅削減と結露防止が実現し、マンションの省エネ性能が向上します。また二重窓化による防音効果で騒音ストレスが軽減し、快適性が飛躍的に向上します。こうした住環境の質的向上はマンションの資産価値アップにも寄与します。
窓の断熱改修効果は数値にも表れます。省エネの観点では、サッシ交換によって壁や天井からの熱損失に比べ開口部からの熱損失割合を劇的に低減できます。古いアルミサッシ+単板ガラス窓から樹脂枠+複層ガラス窓に替えた場合、室内から外に逃げる熱量が大幅に減り、冬期の暖房エネルギー消費を20~30%以上削減できるとの報告もあります(地域や住戸条件による)。さらに窓際の表面温度が上がり結露発生が抑えられるため、カビやダニの発生リスクも低減します。
防音効果についても、内窓を追加して二重窓化することで顕著な改善が得られます。国の補助事業でも生活騒音対策として内窓設置が推奨されており、「JIS規格で遮音等級T1以上」の製品が対象になるなど一定の防音性能が確保された窓が支援対象です。これは例えば鉄道や幹線道路沿い住宅のケースで、80dB前後の屋外騒音が二重窓により室内では40dB程度(図書館や静かな住宅街レベル)まで低減できることを意味します。実際、厚みのある防音合わせガラスを用いた内窓を設置すれば体感上半分以下の静かさになるとも言われ、在宅勤務や子育て環境にも好影響を与えます。
あるマンションでは全戸の窓ガラスを高性能な複層ガラスに交換した結果、「冬場の結露がほとんど発生しなくなった」「窓まわりが暖かくなり暖房の効きが良い」といった声が多数寄せられました。また「外の車や電車の音が気にならなくなり、室内でテレビや会話を快適に楽しめるようになった」という居住者の体感報告もあります。これらは断熱・防音性能向上によって住み心地が改善した証拠であり、そのマンションの魅力・価値も向上したといえるでしょう。窓は毎日の生活品質に直結する要素だけに、適切なサッシ交換リフォームの効果は投資以上に大きなリターンをもたらします。
【2025年版】補助金利用時の注意点とよくある誤解
補助金を活用する際は、申請期限や予算枠、マンション特有のルールなどを正確に把握し、制度の仕組みを正しく理解することが重要です。よくある誤解として「いつでも補助金がもらえる」「勝手に窓を交換できる」といった点がありますが、実際には計画的な準備と手続き、管理組合での合意形成が不可欠です。
1. 申請期間・予算枠に関する注意点
国の住宅省エネ補助事業(先進的窓リノベ2025など)は年度ごとに予算が設定されており、申請期間や予算枠に上限があります。2025年度も同様に、予算消化状況によっては早期に受付が終了する可能性が高いため、交付申請は早めに済ませることが望ましいです。補助事業の継続は概ね予定されていますが、内容や条件は毎年度見直されるため、将来も同条件で利用できる保証はありません。そのため「来年に回そう」と先延ばしにするリスクがあります。
2. マンション特有のルールと管理組合の合意形成
分譲マンションの窓サッシは多くの場合「共用部分」として管理組合の管理下にあります。
したがって、外窓の交換工事を補助金を利用して行う場合は、管理組合の正式な承認や総会決議が必要です。場合によっては管理規約の改定や一括工事に向けた住民合意の形成も求められます。
一方、内窓設置などの専有部分内改修は個人で実施可能な場合が多いですが、こちらも事前に管理組合への届け出や承認を得ることが推奨されます。これによりトラブル防止と補助金の申請要件の確保につながります。
3. 補助金の併用ルール
国の補助事業間では、同一工事に対する重複申請は原則不可です(例:先進的窓リノベと子育てエコホームの併用はできません)。
一方で、自治体が独自に実施する補助制度(地方単独事業)は国の補助金と併用可能なケースが多いです。例えば東京都の断熱改修補助制度では「国の住宅省エネ補助との併用可」と明記されており、理論上は国の最大200万円+都の最大130万円の支援を合わせて受けられる場合もあります。
ただし同一工事費用に対して二重に補助を受け取ることはできないため、申請時には対象範囲や費用配分の調整が必要です。
4. よくある誤解と注意点
- 「申請すれば必ず補助金がもらえる」わけではない
申請が適正であっても、予算超過や審査の結果により減額や不採択となる可能性があります。 - 「補助金があるから高額工事にすれば得」ではない
補助金には上限額が設定されているため、上限を超えた部分は自己負担となります。予算超過に注意し、工事計画は費用対効果を考慮して適切に立てましょう。 - 「申請してすぐに補助金が支給される」わけではない
補助金は工事完了後の審査・交付決定を経てから後払いされるため、完了から数か月のタイムラグがあります。資金計画では補助金が遅れて入ることを見込んでおく必要があります。
まとめ:計画的に補助制度を活用しよう
マンションのサッシ交換リフォームは、断熱性や防音性の向上により快適な暮らしと省エネ効果をもたらし、結果的に建物全体の資産価値を高める重要な施策です。国や地方自治体の補助金制度を上手に活用すれば、高性能な窓へのリフォーム費用の負担を大幅に軽減できます。
まずは利用可能な支援制度を正しく把握し、管理組合や専門業者と連携して計画を立てることが肝心です。補助金の対象条件を満たす製品選びや申請手続きの準備は早めに行い、期限内に確実に申請しましょう。
補助金制度の活用にはルールの理解と段取りが求められますが、適切に進めれば強力な後押しとなり、マンション全体の窓リフォームを実現できます。快適で省エネな住まいづくりのために、ぜひ各種支援制度を賢く利用し、計画的にサッシ交換を進めてください。
ドア/サッシ等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- 玄関ドア、サッシ等の金物の支援実績は多数あります。約450戸 多棟型マンションでのハンスフリー/非接触キーのドアへの交換(補助金≒2千万円活用)実績もあります。社内にはゼネコン、修繕会社や修繕コンサルティング会社など出身の建築士等が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。ドア/サッシメーカー系を含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)