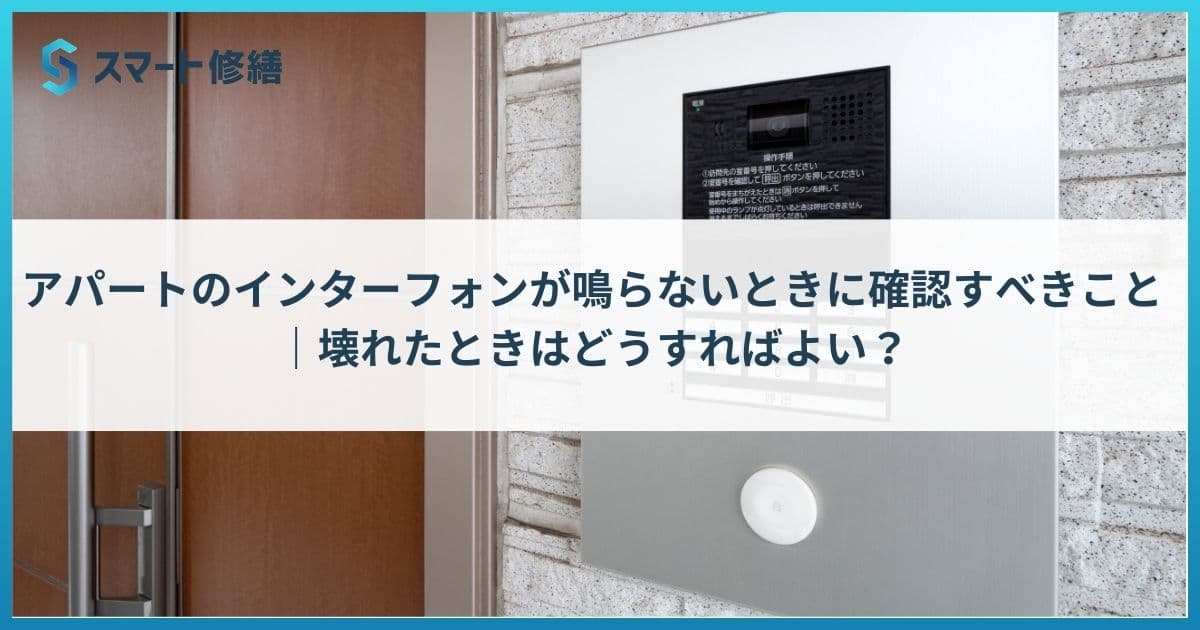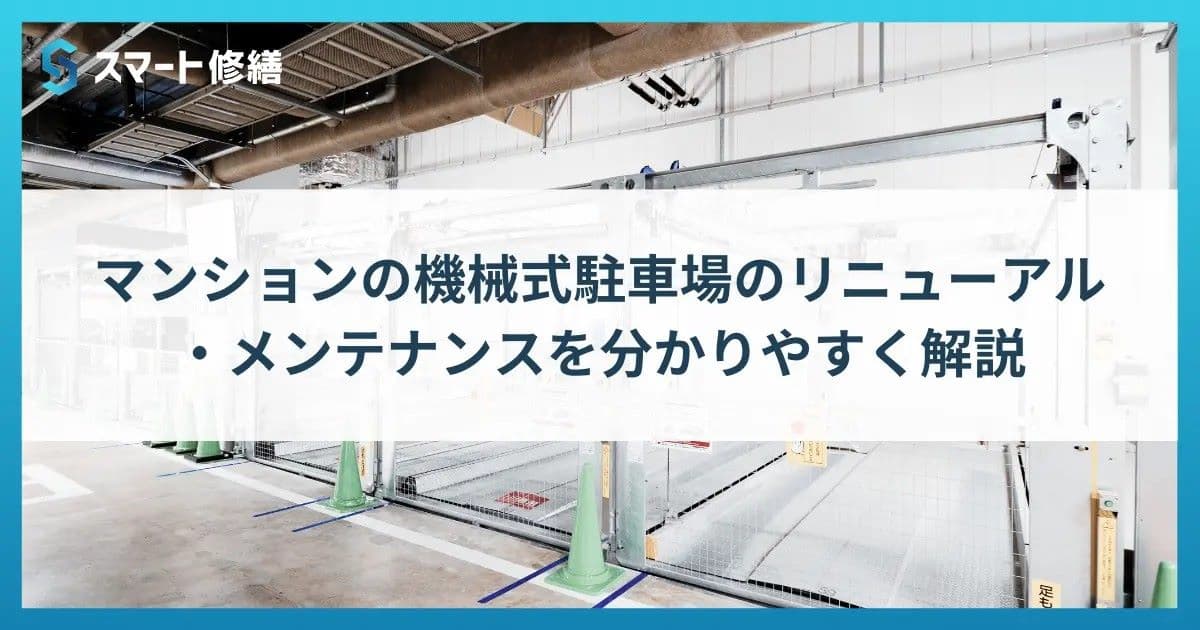マンションのドアホン交換方法・費用を徹底解説
更新日:2025年06月29日(日)
本記事では、マンション管理組合やオーナーの方向けにドアホン交換の方法、費用、注意点、そして費用を抑える工夫について網羅的に解説します。これから7つのポイントに沿って順に説明しますので、マンションのドアホン交換を検討する際の参考にしてください。
- 本記事のポイント
- インターホン更新の流れと必要性を学べる。
- 費用相場や負担区分の考え方がわかる。
- 住民合意やコスト削減の実践方法を把握できる。
マンションのドアホン(インターホン)とは?
マンションのドアホン(インターホン)とは、共用エントランスと各住戸をつなぐ通信設備であり、防犯と非常時対応に不可欠なシステムです。管理組合にとってドアホンは共用設備の一部で、住民の安心・安全な暮らしを支える重要インフラと言えます。
多くの分譲マンションではエントランスにオートロック対応の集合玄関機が設置され、各住戸内に親機(室内インターホン)が備わっています。居住者は室内から来訪者と通話し、エントランスのロックを解錠できます。さらに集合住宅用インターホンは自動火災報知設備等とも連動可能で、火災時にはインターホンを通じて警報を鳴らしたり全戸へ一斉放送する機能を備えます。非常時の館内放送設備としても機能するため、ドアホンは単なる来客用の呼び鈴以上の役割を持っています。
マンションのインターホンには大きく2種類のシステムがあります。一つは「集合住宅システム(オートロック式)」で、エントランスのオートロックと連動した全館一体型のインターホンシステムです。この場合、各住戸の親機は共用エントランス機と接続されており、個別に勝手に交換することはできません。もう一つは「住戸完結システム」で、オートロックの無い小規模マンション等で各戸が独立したインターホンを設置するタイプです。住戸完結型では無線式インターホンなど各戸で交換可能な場合もあります(※)が、基本的にマンション全体で統一して交換する方が外観の一体感も保たれ、1戸あたりの費用も安く抑えられます。
※各戸で交換できる場合でも管理規約上共用部分扱いになっていないか確認が必要です。
マンション向けインターホンの主要メーカーは現在パナソニックとアイホンの2社に集約されています。各社から様々な機種が出ていますが、最近の機種では録画機能付きカメラ・ハンズフリー通話など高機能化が進んでいます。いずれにせよ、マンションのドアホンは共用部と専有部を繋ぐ安全設備であり、定期的なメンテナンス・更新が必要なものとして位置付けられています。
ドアホンの交換方法
マンションのインターホン交換工事は、計画準備から施工完了までいくつかのステップを踏んで進めます。管理組合が主体となって適切に計画立案し、業者選定や住民合意を経て工事を進めることが重要です。以下に、ドアホン交換の一般的な流れを示します。
交換工事の主な進め方
現状調査と計画準備
まず現在のインターホン設備の状況を把握します。設置からの経年(15年前後が目安)や故障の発生状況を確認し、交換の必要性を検討します。管理組合が中心となり、各戸のインターホン不具合状況や新しい機能への要望をアンケート調査することが推奨されています。これにより故障件数や住民ニーズを把握し、計画立案の資料とします。また現在の設備が自動火災報知設備や警報と連動しているか、既存配線の仕様など技術面の調査も行います。
概算見積もり取得と予算計画
次に交換に必要なおおよその費用感を把握し、予算の目安を立てます。この段階では、管理会社からの提案をベースに、必要に応じて別の事業者にも概算見積もりを依頼しましょう。管理会社任せにせず複数の視点を持つことで、適正な費用感を掴みやすくなります。なお、検討を円滑に進めるためには、管理組合内にプロジェクト担当(理事会や専門委員会など)を設けることをおすすめします。
機種・工事内容の検討
予算の範囲内で導入する機種や工事範囲を決定します。メーカー(パナソニック/アイホン)のどのモデルにするか、防犯カメラや宅配ボックスとの連動機能、録画機能など必要な仕様を検討します。現在の設備が古い場合、最新型すべてに対応できないケースもあるため(消防設備と連動するタイプでは導入できない機種もあります)、専門業者と相談しながら自マンションに適した機種を選定します。管理会社に依頼すればメーカーからデモ機を借りて説明会で操作体験することも可能なので、住民に新機能を周知する良い機会になります。
正式見積もりと業者選定
機種と工事内容が固まったら、施工業者から正式な見積書を取得します。理事会で発注先候補の業者を比較検討し、信頼でき適正価格の業者を選定します。必要に応じて修繕コンサルタント等の専門家の意見も仰ぎます。発注先が決まったら、工事請負契約の内容(工期、範囲、保証、金額など)を確認しましょう。複数業者から見積もりを取得することで、中間マージンが減り費用が下がる可能性があります。
総会での承認(合意形成)
分譲マンションの場合、インターホン全戸交換工事は重要事項のため、管理組合の総会での決議が必要です。とくに各住戸内親機が「専有部分」扱いの場合は、管理組合が共用費で交換するには区分所有者の合意(特別決議など)が求められます。理事会で作成した議案書に工事の目的・内容・費用負担区分を明記し、総会で承認を得ます。住民への十分な説明と合意形成が重要なステップです。
発注と製品納期の確認
総会で承認されたら、選定した業者と契約を結び正式に発注します。インターホン機器は受注生産となる場合が多く、発注から納品まで通常2〜4か月程度かかります。納期を考慮し、早めにスケジュールを組むことが重要です。
工事日程の調整と周知
機器の納期が確定したら、実際の工事日程を計画します。共用部(玄関機等)工事と各専有部(室内親機)工事の日程を決め、全住戸に工事スケジュールを知らせます。工事当日は各住戸内で作業が必要なため、居住者の在宅協力が不可欠です。一斉交換の場合、あらかじめ各戸の希望日程をアンケート調整するとスムーズです。50戸規模のマンションでは共用部2日+専有部5日程度、合計約1週間が標準的な工期の目安です。各戸の作業時間はおよそ40分〜1時間程度で、工事担当者がインターホン親機の取替えと動作確認を行います。工事期間中はインターホンや警報が一時的に使えないため、防犯・防災上の注意喚起も必要です。例えば「○月○日〜○日は工事のためオートロックが使用停止」「非常警報は管理人室・警備会社に送信されない」等を事前に周知し、代替措置を検討します。必要に応じて警備員の巡回を強化するなどリスク軽減策も取ります。
交換工事の実施
決められたスケジュールに沿って交換工事を実施します。まずエントランスの集合玄関機・制御盤等共用部の機器を設置・交換し、その後各戸を順次回って室内親機の交換工事を行います。古い機器の撤去・新機器の取り付け・配線接続・動作確認という流れで一戸ずつ完了させます。各戸工事完了時には居住者とともに通話や解錠、警報連動などの動作チェックを行い、問題がないことを確認します。
完了検査と引き渡し
全戸の交換が終わったら、管理組合立会いのもとシステム全体の最終検査を実施します。エントランスから全住戸へ正しく呼出音・通話が届くか、オートロック解錠や火災連動警報が正常作動するかなど、施工業者とともに点検します。問題がなければ工事完了となり、新しいインターホン設備の取扱説明書や保証書の受け渡しを受けます。最後に管理組合から居住者へ新システムの使用方法の周知(配布資料や掲示板での案内)を行い、住民からの質問に対応します。これで一連の交換プロジェクトが完了です。
各マンションの規模や状況によって詳細は異なりますが、以上がドアホン交換工事のおおまかな流れです。ポイントは早めの計画策定と合意形成、信頼できる業者選定、そして住民への丁寧な周知です。
ドアホンの交換工事にかかる費用
マンションのインターホン交換工事費用は、建物規模や仕様(機器のグレードや工事内容)によって異なりますが、戸あたり費用は約10万円~18万円(税別)となります。
費用の内訳としては、機器本体価格+工事費(配線工事・取付作業)+諸経費から成ります。工事費用には古い機器の撤去処分費や、業者の人件費、交通費なども含まれます。またエントランスが複数あるマンションでは玄関機を複数設置する必要があり、その分費用が増加します。たとえばサブエントランスを持つマンションでは玄関機追加1台ごとに数十万円規模の費用加算となります。さらに、既存の配線を流用できるか新規に配線し直すかも費用に影響します。近年の機器は多くが既存の2線式配線に対応していますが、大幅にシステム仕様を変える場合は配線工事費がかさみます。
分譲マンションの場合、インターホン交換費用を誰が負担するかも重要なポイントです。一般的には、全戸一斉の更新工事であれば管理組合が修繕積立金から負担するケースが多くなっています。インターホン更新も長期修繕計画に組み込まれており、更新時期(約15年)に備えて積立金を積み立てているのが通常です。
実際、「マンションのインターホン交換費用は管理組合が修繕積立金から負担するのが一般的」との解説があります。ただしケースによっては費用区分が異なることもあります。各住戸内の親機は専有部分扱いとなるため本来は各区分所有者負担だが、一斉更新時に管理組合が共用工事として実施する場合もあります。
例えば「各戸の室内機は各自負担、エントランス機等共用部分は組合負担」とするケースや、全て組合負担とするケースなど、管理規約や総会決議で費用負担ルールを定める必要があります。一方、賃貸マンションではオーナー(大家)が費用負担するのが通常で、入居者は負担しません。
以上のように、ドアホン交換にはまとまった費用がかかりますが、建物の資産価値向上や防犯機能強化という効果も得られます。適正な相場を把握した上で、次に述べる注意点に留意しつつ計画を進めることが大切です。
ドアホン交換工事の注意点
マンションのドアホン交換工事を円滑に進め、トラブルを防ぐために押さえておきたいポイントを3つ解説します。管理組合やオーナーの視点で特に注意すべき事項です。
注意1:費用負担のルールと責任区分を明確にする
インターホン交換を計画する際は、対象設備が共用部分か専有部分かを管理規約で確認し、費用負担のルールを明確にしておくことが重要です。特に親機が専有部分に該当する場合でも、火災警報など共用の警報設備と連動しているケースでは、管理組合で一括交換・費用負担することも合理的とされます。
設備の性質や接続状況、費用負担の範囲はマンションごとに異なるため、理事会や総会で方針を整理・共有し、必要に応じて管理規約の見直しや明文化を行っておくことが望まれます。
注意2:計画的な工事準備と住民への周知徹底
インターホン交換工事は、長期修繕計画に基づき、築15年前後を目安に計画的に進めることが重要です。
設備の老朽化を放置すると、突然の故障による緊急対応や臨時総会の開催が必要になるなど、管理組合に大きな負担がかかります。また、オートロックや火災警報と連動している場合、防犯・防災機能にも支障が出る恐れがあるため、早めの更新検討が望まれます。
工事の実施にあたっては、住民の理解と協力が不可欠です。工事日程や各戸の作業予定、インターホン停止時間、来客・宅配対応などの代替措置を事前に周知し、特に高齢者世帯などには個別対応も検討しましょう。騒音や人の出入りへの配慮として、掲示板や回覧による事前告知も効果的です。
また、メーカー発注から納品・工事着手までには通常数ヶ月(約2~4ヶ月程度)を要するため、総会決議から逆算したスケジュール管理が必要です。近年は半導体不足などで納期が長期化する例もあるため、余裕をもった計画と進捗管理が工事成功の鍵となります。
注意3:適切な機種・業者選定と契約交渉を行う
インターホン交換では、機種と業者の選定、契約内容の精査が重要です。複数の業者から見積もりを取り、費用だけでなく提案内容やアフターサービス、保証条件なども比較しましょう。管理会社任せにせず、競争原理を働かせることでコスト削減と品質確保が期待できます。
選定時は、信頼性・実績のある直接施工が可能な業者を優先し、不要な中間マージンを避けるのが理想です。また、機器は既存の消防・セキュリティシステムと互換性があるかどうかも要確認です。
契約時には、工事範囲・金額・支払条件・保証内容を明記した契約書を交わし、不明点は事前に確認・交渉しておきましょう。インターホン更新を機に、警備会社や保守契約の見直しで維持費を削減できるケースもあるため、設備本体だけでなく付帯コストも含めた総合的な視点で検討することが大切です。
最後に、専門知識を持つ第三者の活用も検討してください。ただ闇雲にコスト削減を追求すると必要な品質まで損なうリスクもあります。マンション管理士や建築士など経験豊富な専門家に相談しながら進めることで、適正な範囲でのコストダウンと品質確保のバランスを取ることができます。
以上、3つの注意点をまとめると、「契約面・計画面・費用負担面」で事前にリスクを潰しておくことがドアホン交換工事成功の秘訣と言えるでしょう。
マンションのドアホン交換におけるコストダウンの工夫
インターホン交換工事は高額になりがちですが、計画や選定の工夫次第でコストを抑えることが可能です。以下に、実際に効果があったとされる取り組みを紹介します。
複数見積もりの取得
業者によって提案内容や費用に大きな差が出ることがあるため、複数社からの見積もりを比較検討することで、大幅なコスト削減につながる場合があります。
中間マージンの抑制
管理会社を介さず、一次代理店と直接契約することで、余計な中間コストを排除できたケースもあります。業者選定の透明性を確保することがポイントです。
一斉交換によるスケールメリット
全戸一括での交換により、機器の単価や工事単価が下がり、1戸あたりの費用を抑えることが可能になります。統一感の維持にもつながります。
既存設備・配線の有効活用
既存の配線や設置位置をそのまま活かせば、工事の手間やコストを抑えられます。互換性のある機種を選ぶことも工事簡略化の鍵です。
維持コストの見直し
更新を機に警備契約や保守契約を見直し、ランニングコストを削減した例もあります。設備導入後の維持費まで含めたトータルコストの視点が重要です。
以上のような施策により、「インターホン交換費用=高いもの」と諦めずに賢くコスト圧縮を図った成功例があります。ただし、安さだけを追求して肝心の機能やアフターサービスを犠牲にしないよう注意も必要です。管理組合としては複数の専門業者やコンサルタントの意見を取り入れつつ、必要十分な性能を確保した上で最も経済的なプランを選定することが理想です。
まとめ:インターホン交換は計画的に、費用は慎重に見直しを
インターホンは防犯・防災の要となる設備であり、約15年を目安に計画的な更新が必要です。老朽化によるトラブルを防ぐためにも、長期修繕計画に組み込み、適切な時期に備えましょう。
交換工事は、事前調査・住民合意・業者選定・工事中の対応まで、段取り良く進めることが成功の鍵です。特に費用負担の区分(専有か共用か)や総会決議の取得は、事前に整理しておく必要があります。
費用相場は目安がありますが、仕様や発注方法によって大きく変わるため、見積内容をよく確認し、比較検討を怠らないことが重要です。相見積もりや一括発注、中間マージンの見直し、保守契約の再検討など、工夫次第で費用を抑えられる可能性があります。
提示された費用に不安がある場合は、ガイドラインや専門業者の意見を参考に、再検討の姿勢で適正価格を見極めましょう。適切な設備更新は、単なる支出ではなく、安全性や資産価値向上につながる投資です。
インターホン等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- インターホンのリニューアル工事の支援実績は多数(過去半年で数千戸分、2025年1月現在)。数百戸の多棟型マンションでの実績も複数。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。インターホンのメーカー系のを含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
佐藤 龍太
不動産会社および管理会社にて、マンションやビルの修繕・管理業務に長年従事。マネージャー職を歴任し、これまでに300件近い修繕工事に携わる。特にインターホン設備においては、年間3,000戸以上(2025年現在)の見積取得を行うなど、設備改修の実務に精通。豊富な現場経験と管理業務の知見を活かし、マンション修繕に関する実践的かつ専門的な視点で記事を監修。
こちらもおすすめ
24時間対応通話料・相談料 無料