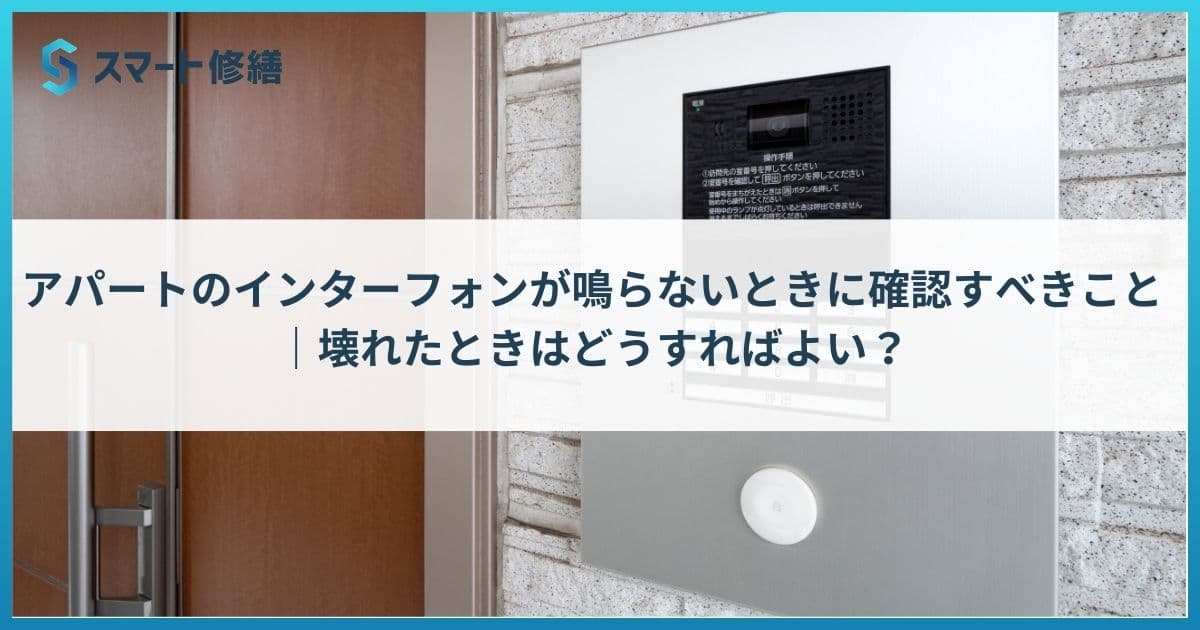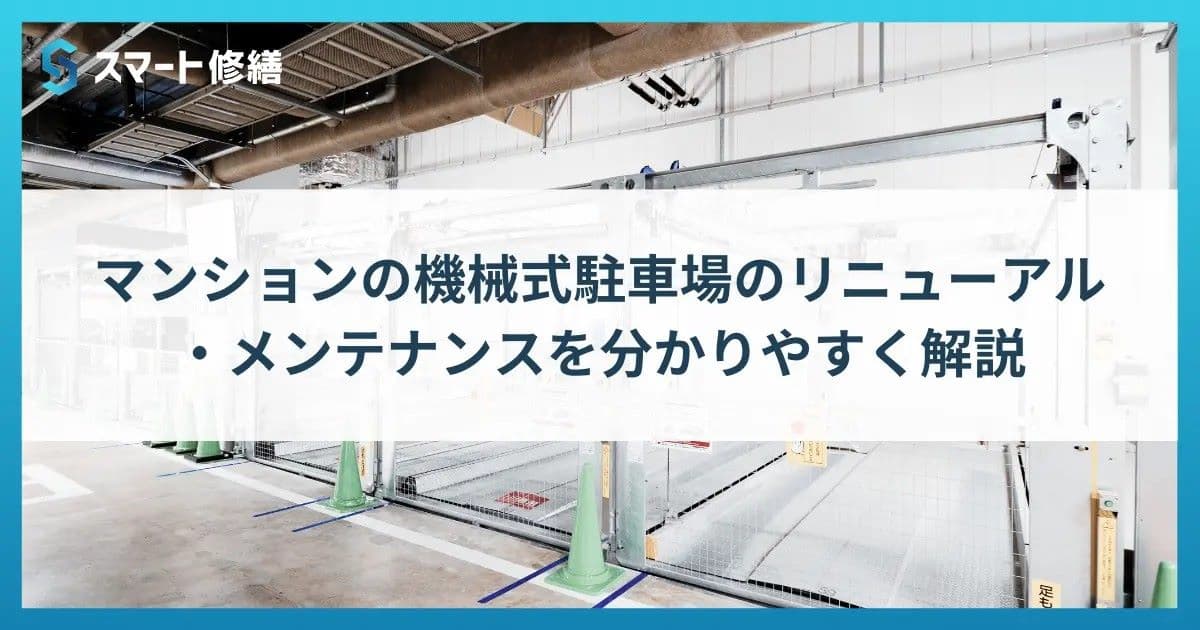賃貸マンションのインターホンを交換する方法|気になる費用の相場は?
更新日:2025年06月30日(月)
本記事では、賃貸マンションのオーナー向けに、インターホン交換の方法や費用相場について詳しく解説します。費用を抑えるためのポイントや工事を進める際の注意点についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
賃貸マンションのインターホンを交換する方法
賃貸マンション(集合住宅)におけるインターホン交換は、オーナーとして適切な判断と段取りが求められます。以下では、設備の更新を進めるうえでの一般的な流れを解説します。
1.交換計画の立案と準備
まずは、現在のインターホン設備の状況を把握し、交換の必要性を確認することから始めます。経年劣化や故障が頻発している場合は、更新を検討すべきタイミングです。
特に集合住宅に多く導入されている「集合住宅用システムインターホン」(エントランスの集合玄関機と各住戸の親機が連動しているタイプ)では、機器同士の互換性の問題から部分的な交換が難しいケースが一般的です。そのため、共用部の集合玄関機や制御装置から、各住戸内の親機までを一括で更新するのが現実的です。
交換対象を明確にしたうえで、長期的な修繕計画や建物全体の維持方針と照らし合わせ、予算や実施時期を検討しましょう。なお、インターホン工業会では、集合住宅用インターホンの更新目安を「設置から約15年」としており、メーカーの部品供給も製造終了後7年程度で止まるケースが多いため、交換時期の見極めが重要です。
また、賃貸物件では入居者の生活に影響が出る可能性があるため、交換工事に伴う通知や調整(後述)も忘れずに計画に組み込む必要があります。
2.業者への問い合わせと現地調査
次に、インターホン交換工事に対応する専門業者へ連絡を取り、見積もり取得に向けた現地調査を依頼します。この際には、以下のような情報を用意しておくとスムーズです。
マンションの所在地
総戸数
現在使用しているインターホンのメーカーや型番
現地調査では、業者が実際の配線状況や機器設置状況を確認し、交換に適した機種の提案も行ってくれます。録画機能付きテレビモニターなど、入居者にとって魅力的な機能の追加も検討材料にするとよいでしょう。
3.見積もり取得と業者選定
調査後に提示される見積書を比較検討します。できれば複数の業者から見積もりを取り、内容を慎重に確認しましょう。
比較ポイントは以下の通りです。
工事費用の内訳(撤去費用・機器代・設置工賃など)
含まれていない費用の有無
アフターサービスの内容(保証期間、不具合時の対応)
金額だけでなく、施工の信頼性や長期的なサポート体制も重視すべきポイントです。
4.費用負担と入居者対応の検討
賃貸マンションの場合、インターホン設備は原則としてオーナー側の管理・維持責任となるため、工事費用は基本的にオーナーが負担することになります。
ただし、入居者に直接関係する住戸内機器の交換を伴う場合は、事前に通知を行い、立ち会いの調整などの協力を求める必要があります。トラブルを避けるためにも、改修の目的や期間、メリットを丁寧に伝えることが重要です。
5.工事日の調整と周知
業者との契約後、具体的な工事日程を調整します。住戸内作業が必要なため、入居者全員に対して工事日を周知し、協力を依頼する必要があります。
通常は、業者が案内チラシを配布したり、エントランスの掲示板に工事予定を掲示する形で対応します。留守世帯がある場合は、個別に再調整するケースもありますので、事前に業者と段取りを確認しておきましょう。
6.交換工事当日の対応
工事当日は、共用部の集合玄関機や制御装置の設置を行った後、各住戸内の親機を順番に交換していきます。各戸の作業時間は約40分~1時間程度が目安です。
例えば50戸のマンションであれば、工期の目安は以下の通りです。
共用部工事:2日
専有部工事:5日
合計:7日間程度
工事完了後は、業者による動作確認が行われます。不具合があれば即時に対応してもらえるよう、最終確認にも立ち会えると安心です。
賃貸マンションのインターホン交換をお得に実行するコツ
賃貸マンションのインターホン交換工事は、規模によっては数百万円から数千万円に及ぶ大規模な投資になります。オーナーとしては、コストを抑えつつも安全性や入居者満足度を維持・向上させることが重要です。ここでは、賢くコスト管理をしながら工事を進めるための具体的なコツをご紹介します。
工事費用の相場を調べる
まずは、インターホン交換にかかる費用の相場を把握することが基本です。相場を知ることで、業者の見積もりが適正かどうか判断でき、費用の見通しを立てやすくなります。
一般的には、1戸あたり10~18万円(税抜)が交換費用の目安です。機種や機能によって価格は大きく変動します。例えば、音声のみのシンプルなタイプであれば安価ですが、録画機能やスマホ連動といった高機能モデルを導入すれば、その分費用は上がります。ただし、高機能モデルは入居者満足度や防犯性向上につながり、空室対策にも効果がある場合があります。
また、配線の状況もコストに影響します。既存の配線が再利用できる場合は工事費用を抑えられますが、老朽化によって新規配線が必要となる場合は追加費用が発生します。
相場調査には、国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」や、インターホン工業会の推奨更新周期(15年)なども参考になります。すでに作成済みの修繕計画があれば、その中に含まれるインターホン更新費用と市場価格とのギャップを確認して、必要に応じて予算を見直しましょう。
また、インターホンの不具合が一部に限られている場合、修理と交換のどちらが適切かも悩ましい点です。修理費は1台あたり1万~3万円程度ですが、製造終了後の部品不足や繰り返しの故障リスクを考えると、築15年以上経過している場合は早期に全体交換したほうが長期的には経済的になるケースもあります。
複数の業者に見積もりを取る
インターホン工事では、複数の業者から相見積もりを取ることが、コスト削減につながる最も現実的な方法のひとつです。最低でも2〜3社以上に依頼し、内容と金額を比較しましょう。
実際、管理会社任せにしてしまうと、下請け業者を使った場合に中間マージンが上乗せされることが多く、相場より割高になる傾向があります。とくにインターホンは、主要メーカー(パナソニック、アイホンなど)が市場を寡占しており、販売ルートや取引先によって価格に差が出やすいのが特徴です。
見積もりを比較する際は、単なる金額だけでなく、以下のようなポイントも確認しましょう。
提案されている機種のグレードと機能
工事の内訳明細(撤去費・設置費・諸経費)
アフターサービス・保証の内容
担当者の対応や説明の分かりやすさ
また、「追加費用が後からかかるケース」を避けるため、見積書にすべての工事項目が含まれているかを必ず確認します。条件を統一したうえで複数の業者から見積もりを取ることで、不明瞭なコストを可視化しやすくなります。
注意点としては、「極端に安い業者」は品質やアフター対応に不安が残ることがあるため、価格と信頼性のバランスを見極めることが大切です。これまでに同規模の集合住宅で実績があるか、トラブル対応の体制が整っているかといった点も評価材料になります。
専門家に相談する
インターホンの交換は、配線や機器構成、建物全体の設備バランスに関わる専門性の高い工事です。不安や疑問がある場合は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
たとえば、マンション管理士や設備コンサルタントなどの専門家であれば、第三者の視点から工事計画や見積もり内容の妥当性をチェックし、必要に応じて改善点を提案してくれます。こうしたサポートを受けることで、不要なコストの発生を防ぎ、より効率的な進め方が可能になる場合もあります。
賃貸マンションのインターホンを交換するときの注意点
賃貸マンションでインターホン交換工事を実施する際、オーナーとしては「どこまでが自分の責任で」「どのように進めればトラブルを避けられるのか」といった点に十分注意が必要です。
ここでは、管理規約との整合性、入居者とのコミュニケーション、法令や施工品質の遵守という3つの観点から、インターホン交換工事の注意点を整理して解説します。
注意1:工事範囲と責任区分
まず最初に確認しておくべきは、インターホン交換の対象となる機器が「どの範囲に該当し」「誰の責任で対応すべきか」という点です。
賃貸マンションにおけるインターホン設備は、共用部分と各住戸内の設備が連動しているため、工事範囲と管理責任の線引きをあらかじめ整理しておく必要があります。
一般的な構成は次のとおりです。
エントランスの集合玄関機や制御装置などの共用部の設備 → オーナーが管理・更新
各住戸内の親機(受話器やモニター)および玄関前の子機 →こちらも通常はオーナーが設置・管理
つまり、賃貸マンションの場合は、建物全体をオーナーが所有・管理しているため、原則すべてオーナーの責任で交換対象となると考えるのが一般的です。
注意2:入居者への丁寧な周知と協力の確保
工事自体はオーナーが判断・発注するものですが、実際に室内で作業が行われるため、入居者の理解と協力が不可欠です。とくに全戸に立ち入っての親機交換を伴う場合は、事前の周知が行き届いていないとトラブルになりかねません。
以下の点を押さえて、信頼関係を損なわないよう丁寧な対応を心がけましょう。
工事の目的(防犯性向上、設備の老朽化対応など)を明確に説明する
作業日程の候補を事前に共有し、入居者の都合も考慮する
高齢者や子育て世帯など配慮が必要な家庭には柔軟に対応する
工事に関するチラシ・掲示・文書などは管理会社と連携して丁寧に実施する
入居者の立場では、「自分の部屋に業者が入ること」に不安を感じる方も多いため、業者が信頼できる事業者であることや、当日の作業内容・所要時間を具体的に説明しておくと安心につながります。
注意3:法令遵守と施工品質の確保
インターホン交換は、法令の遵守と施工品質の確保が不可欠です。特に、電源直結式(100V接続)機器の設置には電気工事士の資格(第二種以上)が必要であり、無資格者の施工は違法なうえ感電・火災のリスクも伴います。業者選定時には、有資格者が作業を行うかを必ず確認しましょう。
また、火災報知器やオートロックなどと連動する設備がある場合、インターホンの交換によりシステム全体へ影響が及ぶことがあります。事前に動作確認や連動試験を行い、必要な認定手続きも確認してください。
施工業者は、実績や技術力、アフターサービス体制を重視して選定しましょう。保証内容や対応力を事前に確認し、契約時には保証書の発行も求めましょう。
さらに、使用するインターホン機器は国内正規品で技適マークのある信頼性の高い製品を採用するのが安心です。
以上のように、法令遵守と品質確保のためには「資格を持ったプロによる施工」「関連システムへの配慮」「保証と保守の充実」が欠かせません。管理組合として契約前に十分確認を行い、工事完了まで安心して任せられる体制を整えましょう。
まとめ:無料相談の仕組みを活用しよう
賃貸マンションのインターホン交換は、建物の安全性・防犯性・入居者満足度に大きく関わる重要な工事です。しかし、費用規模が大きく、機器構成や法令対応、入居者対応まで多方面への配慮が必要なため、オーナー単独で判断・実行するのは簡単ではありません。
本記事では、インターホン交換工事をスムーズに進めるためのポイントとして、以下を解説してきました。
交換にかかる費用相場の把握
複数業者からの見積もり取得によるコスト削減
工事対象範囲と責任区分の整理
入居者への丁寧な周知と協力依頼
施工業者の選定と品質・法令対応の確認
こうした基本ステップを丁寧に踏めば、過度なコストやトラブルを避けながら、安心してインターホンの更新を進めることができます。
特に強調したいのは、無料相談や専門家のアドバイスを積極的に活用することです。
「相場が妥当かどうか判断がつかない」「この設備は交換すべきか迷っている」「信頼できる施工業者を紹介してほしい」といった不安や疑問は、建築・設備・マンション管理の専門家に相談しましょう。不明点をそのままにせず、プロの知見を取り入れて判断の精度を高めることが、結果的にリスクやコストの最小化につながります。
インターホンの更新は、賃貸物件としての安全性・快適性・魅力を高め、資産価値の維持にも直結する投資です。ぜひ本記事を参考に、計画的かつ確実に進めていきましょう。
インターホン等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- インターホンのリニューアル工事の支援実績は多数(過去半年で数千戸分、2025年1月現在)。数百戸の多棟型マンションでの実績も複数。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。インターホンのメーカー系のを含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
佐藤 龍太
不動産会社および管理会社にて、マンションやビルの修繕・管理業務に長年従事。マネージャー職を歴任し、これまでに300件近い修繕工事に携わる。特にインターホン設備においては、年間3,000戸以上(2025年現在)の見積取得を行うなど、設備改修の実務に精通。豊富な現場経験と管理業務の知見を活かし、マンション修繕に関する実践的かつ専門的な視点で記事を監修。
こちらもおすすめ
24時間対応通話料・相談料 無料