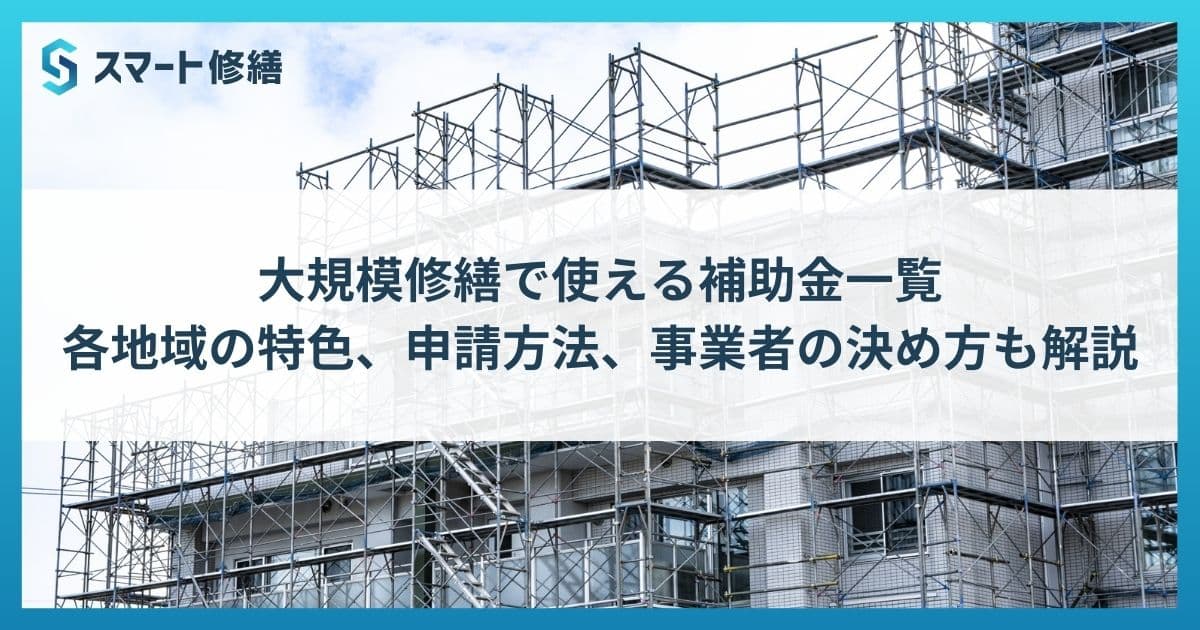築古マンションの窓交換ガイド ~共用部としての扱い・手続き・補助制度を徹底解説~
更新日:2025年10月31日(金)
築年数が経過した分譲マンションでは、老朽化した窓の断熱性や防音性の低さが問題となり、窓の交換リフォームを検討する管理組合も増えています。とはいえ、マンションの窓は建物全体に関わる部分であり、法的な位置づけや必要な手続きを正しく理解することが不可欠です。 本記事では、マンション管理組合向けに、「マンションの窓交換」に関する基礎知識とポイントを整理して解説します。窓が共用部に該当するかどうかの法的位置づけ、交換時に確認すべき管理規約、総会決議や区分所有者の同意の必要性、断熱・防音目的の改修ニーズ、さらに自治体の補助制度についてご紹介します。
- 本記事のポイント
- 窓は共用部分であり、個人判断での交換には管理組合の承認が必要なことが理解できる。
- 総会決議や管理規約、細則に基づく適切な手続き方法がわかる。
- 断熱・防音性能向上や補助金制度を活用し、費用負担を軽減する方法を知ることができる。
マンションの窓は共用部分?その法的位置づけ
結論から言えば、マンションの窓枠・窓ガラスは多くの場合「共用部分」に該当します。区分所有法および標準管理規約では、専有部分(各住戸の所有部分)の範囲から窓枠・窓ガラスを除外する形で規定されており、その結果窓は建物全体の共用部分として扱われます。
ただし各住戸ごとに使用されるものであるため、「専用使用権が付いた共用部分」というカテゴリになります。専用使用権とは、特定の区分所有者(住戸の所有者)が排他的に使用できる共用部分を指します。
共用部分であって専用使用権がある設備(窓や玄関扉、バルコニー等)については、日常の清掃や軽微な維持管理は各住戸の区分所有者が行うのが一般的です。しかし重要なのは、あくまでも窓はマンション全体の共用財産であるという点です。そのため、区分所有者個人の判断で勝手に取り替えたり改造したりすることはできません。
管理規約にも「玄関扉、窓ガラス、バルコニー等が専用使用権のある共用部分となるが、日常的な管理は区分所有者が行うものの、共用部分である以上、無断で取り替えや改造はできない」と明記されています。
要するに、マンションの窓は法的には建物全体に属する部分であり、個人の所有物ではありません。窓サッシやガラスを交換・リフォームする際には、管理組合としての適切な手続きを踏む必要があることをまず押さえておきましょう。
窓交換前に確認すべき管理規約と細則
窓の交換を検討する際には、まず自分たちのマンションの管理規約を確認しましょう。各マンションの管理規約によって、共用部分と専有部分の範囲や、共用部分を区分所有者が変更する場合の手順が定められています。一般的には前述のとおり標準管理規約に倣い「窓枠および窓ガラスは共用部分(専用使用部分)とする」旨が規定されています。したがって、管理規約上も窓は共用部扱いとなっているかをまず確認します。
次に注目すべきは、窓の改良工事に関する規定が管理規約や使用細則に設けられているかどうかです。2016年(平成28年)のマンション標準管理規約改正で、新たに第22条「窓ガラス等の改良」が追加されました。この規定では、各住戸に属する窓枠・窓ガラス・玄関扉等の開口部について、防犯・防音・断熱など住宅性能の向上に資する改良工事は、本来は管理組合の責任と負担で計画修繕として実施するものとすると定めています。つまり、本来窓の性能向上工事(複層ガラス化など)は、管理組合が長期修繕計画等に組み込んで主体的に行うべきものという考え方です。
もっとも、標準管理規約第22条は続けて第2項で例外規定も設けています。管理組合が速やかにその改良工事を実施できない場合には、「各区分所有者の責任と負担」で当該工事を行うことを可能にする細則を定めるものとするとされました。これは、防犯上緊急に改善したいケースや、結露によるカビ・ダニ発生といった健康被害を防ぐために断熱性を向上させたいケースなど、マンション全体ではなく一部住戸において切実なニーズが生じる場合もあり得ることを踏まえた条項です。
管理組合として全戸一斉の改修工事をすぐには実施できない場合でも、あらかじめ細則で定型的な工事内容や手続きを定めておくことで、個別住戸ごとの窓改修を許容しようという趣旨です。
例えば標準管理規約のコメントでは、「防犯・防音・断熱性等に優れた複層ガラスやサッシへの交換、既存サッシへの内窓設置」といった工事が具体例として挙げられています。細則であらかじめ材料や工法、窓の形状や色柄の統一基準などを定め、その範囲内で行われる窓改修工事であれば、都度総会の決議を経なくとも各区分所有者の責任・負担で実施可能とするのが標準管理規約22条の狙いです。したがって、理事会としては自マンションの規約・細則に同様の規定があるか確認し、必要に応じて整備を検討すると良いでしょう。最近では、既存のサッシ枠を活かしてガラスだけ複層ガラスに交換する工法なども普及しており、外観を変えず性能向上が図れるなら個別交換を認める管理組合も増えています。その際は、事前申請書・承認書の様式や施工業者の基準なども細則で定め、統一ルールに沿って進めることが望ましいでしょう。
ポイント: 窓交換を考えたら、まず管理規約で窓の位置づけと改修ルールをチェックすることが重要です。規約に特段の定めがない場合、基本的には組合全体の決議なしに個人で窓を交換することはできません。その場合は次に述べるような総会決議手続きが必要になりますし、必要に応じて規約改正や細則制定によるルール作りも検討しましょう。
窓交換工事に必要な総会決議と区分所有者の同意
マンションの窓を交換するには、管理組合の正式な意思決定が必要です。具体的には、所有者全員で構成する総会での決議を経ることが求められます。共用部分に手を加える行為は組合の意思に基づいて行われるべきものだからです。
総会決議の種類(普通決議か特別決議か)については、工事の内容や規模によって異なります。一般に、マンションの共用部変更は区分所有法第17条で「その形状または効用の著しい変更」を伴う場合には区分所有者数および議決権数の各4分の3以上の特別多数決議(いわゆる特別決議)が必要とされています。しかし、窓の交換工事については、建物の外観形状を大きく変えず、むしろ従前の性能向上を図る「改良を伴う修繕」とみなすことができます。そのため、標準管理規約のコメントでは「窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事」は普通決議(過半数決議)事項として例示されています。つまり全戸の窓交換工事は原則として総会における過半数の賛成で承認可能という位置づけです。
ただし、これは管理規約や既存の長期修繕計画に沿った通常の改修工事として行う場合です。もし窓の交換が単なる修繕の域を超えて建物の価値向上や機能拡張を目的とするような場合(例えばデザインを一新するような改造的工事)は、組合によっては重大な変更と捉えられ特別決議を要する可能性もあります。一般論としては「計画修繕工事として位置付けられる窓の一斉交換」は普通決議で決するケースが多いものの、個々の状況に応じて理事会が事前に専門家(マンション管理士や弁護士等)と協議し、必要な決議要件を判断しておくと安心です。総会に諮る前に、今回の窓工事が規約上どの決議区分に該当するかを明確にし、議案書等で組合員に説明することが望ましいでしょう。
区分所有者の同意・協力についても留意が必要です。総会決議で承認された工事であれば、反対者も含め区分所有者全員がその決議に従う義務を負います。つまり、多数決で可決された以上、各住戸の所有者は自身の窓について工事に応じる義務と費用負担責任があります。もっとも現実には、反対していた区分所有者が工事当日に自宅への立ち入りを拒否するといったトラブルも起こりえます。管理組合側には管理規約上、必要に応じて専有部分(室内)に立ち入って共用部分の工事や維持行為を行える権利が定められていることが一般的ですが(多くの規約でその旨の条項があります)、組合運営上はできるだけ円満に協力を得たいところです。
そのため、全戸一斉の窓交換工事を計画する際は事前に各区分所有者への丁寧な説明と同意取り付けが重要です。理事会や修繕委員会が中心となり、窓交換の必要性やメリット、費用負担の考え方、工事期間中の段取りなどを十分に説明し、質問や不安に答える場を設けましょう。特に高齢の居住者などは工事への抵抗感がある場合もありますので、工程や在宅の有無に配慮した対応策(例:在宅困難な高齢者宅は管理人や親族が立ち会う等)も検討します。
一方、個別住戸ごとの窓交換については、上述の細則整備がされている場合を除き、基本的にはその都度組合の許可(理事会承認や総会決議)が必要となります。細則で典型的工事が定められていないマンションで、ある区分所有者が自己負担で窓を二重サッシに交換したいと申し出たケースでは、管理組合として許可するか否かを判断しなければなりません。その判断にあたっては、単独の窓改修が他の住戸に影響を与えないか(外観統一性や将来の一斉改修との整合性など)を慎重に検討し、必要であれば総会で承認を得ることが望ましいでしょう。標準管理規約の方針にならえば、本来は細則で包括的にルール化しておき、条件を満たす限り総会決議なしで認められるようにするのが理想です。しかし現実には細則がないマンションも多いため、その場合はケースバイケースで総会に諮るか、臨機応変に理事会判断で認める代わりに後追いで規約改正を検討する、といった対応も考えられます。
まとめると、窓交換に際しては管理組合の正式決議が必要不可欠であり、通常は総会の普通決議(過半数決議)で行います。大規模修繕の一環として実施するなら過半数で問題ないケースが多いですが、工事内容が特殊な場合は要件が変わる可能性もあるため注意しましょう。また、決議が通った後も各所有者から協力を得る取り組みが重要です。工事の円滑な実施には合意形成と周知徹底が欠かせません。
古い窓の問題点と断熱・防音改修の必要性
築年数の経ったマンションでは、従来型のアルミサッシ+単板ガラスの窓が使われていることが多く、これが様々な問題の原因となっています。
具体的には以下のような点で、古い窓のままでは現代の住宅性能要求に応えられなくなっています。
- 断熱性の低さ(冬寒く夏暑い)
単層ガラス窓は熱の出入りが大きく、室内の冷暖房効率を下げています。実際、住宅の中でも熱の損失・侵入がもっとも多いのは窓・ドアなどの開口部であり、古いサッシや単板ガラスの窓では夏に外気の暑熱が伝わりやすく、冬には暖房の熱が逃げて室内が寒くなりがちです。。放置すれば結露によるカビ発生やヒートショックなど健康被害につながる恐れもあり、断熱性能向上は重要な課題です。
- 防音性の不足
単層ガラスでは遮音性能も低く、交通騒音や周辺環境の生活音が侵入しやすくなります。窓サッシを新しくして複層ガラス化したり気密性を上げたりすることで、防音性能が高まることが期待できます。実際にサッシ改修によって「断熱性が向上するほか、気密性・防音性が高まる」ことが確認されており、静かな住環境の実現にも窓交換は有効です。
- 老朽化による劣化・不具合
長年使用された窓枠やクレセント錠(金具)は摩耗し、建付け不良や開閉不調が生じやすくなります。ロックが甘くなれば防犯上のリスクも高まりますし、隙間風や雨水の侵入など生活上の支障も発生します。また経年劣化したゴムパッキンは硬化・収縮しており、気密・水密性能の低下を招きます。台風や豪雨時に雨漏りや窓枠からの浸水が起こるのも古いサッシでは珍しくありません。交換によってこれら不具合の解消と気密性・水密性の向上が期待できます。
- 防犯・防災面の不安
古いガラス窓は割れやすく、泥棒に侵入されやすい点や地震時に粉々に飛散して危険な点も問題です。近年は防犯合わせガラス(中間膜入り二重ガラス)等が普及し、一見すると通常の複層ガラスと変わりませんが、割れにくく貫通しづらいため侵入盗対策になります。また割れても破片が飛び散りにくいので防災安全上も優れた窓と言えます。実際、東京都の補助制度でも防犯性能の高い断熱窓を「断熱防犯窓」として推奨し、導入時の補助額を手厚くする措置が講じられています。災害時の備えや安全・安心の向上という観点からも、窓の性能アップはマンション全体の価値に直結する重要ポイントです。
以上のような理由から、断熱性・防音性の改善ニーズは高まっており、国や自治体も既存住宅の開口部性能向上に注目しています。管理組合としても、単なる修繕としての窓交換だけでなく、「省エネ改修」「性能向上リフォーム」という積極的な捉え方をしてみてください。窓を高性能化することで得られるメリット(快適性向上、健康リスク低減、光熱費削減、防犯防災力向上)は、築古マンションの居住価値を維持・向上させる上で無視できないものとなっています。
窓改修に活用できる自治体の補助制度
窓の断熱改修や性能向上工事には、国および地方自治体の補助制度を活用できる場合があります。近年は2050年カーボンニュートラル実現に向け、住宅の省エネ化を促進する政策が強化されており、窓のリフォーム支援策も充実してきました。管理組合で窓交換プロジェクトを進める際には、これらの補助金・助成金を上手に利用することで区分所有者の負担軽減が可能です。
- 国の補助制度
国土交通省・経産省・環境省による「住宅省エネ2025キャンペーン」では、高性能な断熱建材(窓・ガラス・玄関ドア等)を用いた住宅の断熱リフォームに対し補助金が交付されます。一定の省エネ効果(15%以上のエネルギー削減)が見込まれる窓改修工事が対象で、工事費用の一部を国が支援する仕組みです。
また環境省所管の「先進的窓リノベ事業」(2025年度)も、既存住宅の窓を高断熱化するリフォームに対し補助率1/2相当(上限額あり)で支援を行っています。これら国の制度は毎年度内容が変わる可能性があるため、最新情報を国交省や環境省の公式サイトで確認しましょう。
- 東京都など自治体の補助例
地方自治体独自の制度も見逃せません。東京都では「既存住宅における省エネ改修促進事業」という補助金制度を設け、戸建て・マンション問わず窓の断熱リフォームを支援しています。とりわけ分譲マンション向けには、管理組合が50戸以上を一括して窓・ドア改修する場合に補助単価と上限額を1.2倍に割増する措置や、防犯性能付きの断熱窓(断熱防犯窓)を採用した場合にその窓の補助単価・上限を2.5倍に拡充する措置が講じられています。さらに国の窓リノベ事業(補助率1/2)と東京都の補助(補助率1/3相当)を併用することで、実質的な自己負担が1/6程度まで圧縮されるケースもあります。例えば、窓改修費の総額の半分を国が、3分の1を東京都が補助すれば、残り6分の1が区分所有者負担となる計算です。
このように自治体と国の制度を組み合わせれば大幅なコスト減が実現でき、マンション全体の窓性能アップがより現実的なものとなるでしょう。
- その他の地方自治体
東京都以外でも、多くの道府県・市区町村で住宅リフォーム支援制度が用意されています。内容は地域によって様々ですが、「既存住宅の省エネ改修補助」「住宅リフォーム助成金」「環境配慮型リフォーム支援」などの名称で、窓の断熱改修や二重サッシ設置等が補助対象となっている場合があります。
最新の情報は各自治体の住宅課や環境課のウェブサイトで公表されています。また、国交省関連団体の「住宅リフォーム支援制度検索サイト」では、お住まいの市区町村名から利用可能な支援制度を検索できます。ぜひ該当サイトや自治体窓口で最新情報を調べ、使える補助金がないか確認してみてください。
なお、留意点として補助金には応募期間や予算枠、申請手続き(事前申請や施工業者の要件など)のルールがあります。マンションの管理組合が代表して申請する場合と、各区分所有者が個別に申請する場合がありますので、制度の条件に合わせて進める必要があります。場合によってはエネルギー計算や製品登録(例:一定の断熱性能を有する窓である証明)が必要となることもあります。理事会として補助活用を検討する際は、施工業者や専門コンサルタントの協力も得ながら、申請漏れや締切遅れのないよう準備しましょう。
まとめ:適切な手続きと計画的な窓改修でマンションの価値向上を
マンションの窓交換は、法的手続きを踏まえて計画的に進めることで、快適で安全な住環境づくりと資産価値の維持向上につながる重要プロジェクトです。窓は共用部分である以上、管理規約の確認や総会決議の実施は避けて通れません。理事としては、まず窓の位置づけと改修ルールを規約面から把握し、必要に応じて細則整備などの準備を行いましょう。
その上で、老朽窓の問題点(断熱・防音・防犯・防災性能の不足や劣化不具合)を区分所有者全体で共有し、窓改修のメリットを丁寧に説明して合意形成を図ることが大切です。幸い、昨今は国や自治体から経済的支援策も充実しており、適切に活用すれば費用面のハードルも下げることができます。
最後に、窓交換工事の具体的な進め方については、専門業者から複数社の見積もりを取り、工法や製品の違いを比較検討すると良いでしょう。マンション特有の課題(足場設置の要否、工程中のセキュリティ確保、騒音振動対策など)もありますので、実績のある施工会社の意見を仰ぎながら計画を詰めてください。必要に応じて専門家の助言を得るのも有効です。
築古マンションでも、適切な改修によって快適性・省エネ性・安全性を飛躍的に高めることができます。窓のリニューアルはその象徴的な取り組みです。管理組合主導のもと、ルール遵守と合意形成をしっかり行い、使える制度は賢く活用して、マンション全体の窓性能向上に取り組んでみてはいかがでしょうか。きっと住民の満足度向上と建物価値の維持に大きく貢献するはずです。
ドア/サッシ等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- 玄関ドア、サッシ等の金物の支援実績は多数あります。約450戸 多棟型マンションでのハンスフリー/非接触キーのドアへの交換(補助金≒2千万円活用)実績もあります。社内にはゼネコン、修繕会社や修繕コンサルティング会社など出身の建築士等が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。ドア/サッシメーカー系を含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)