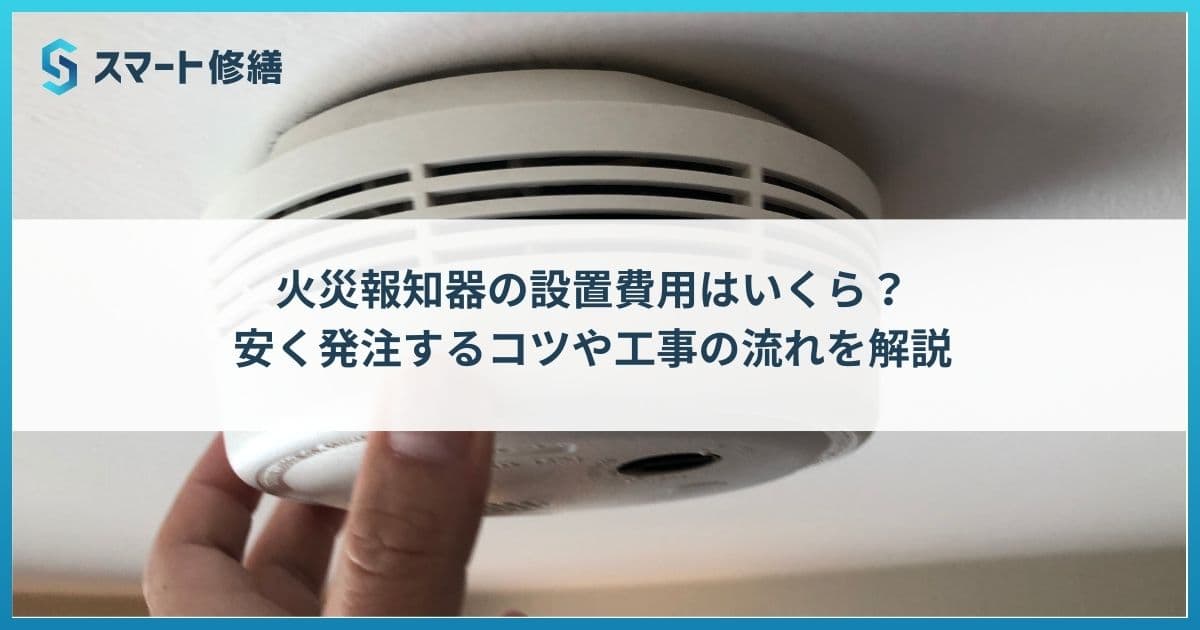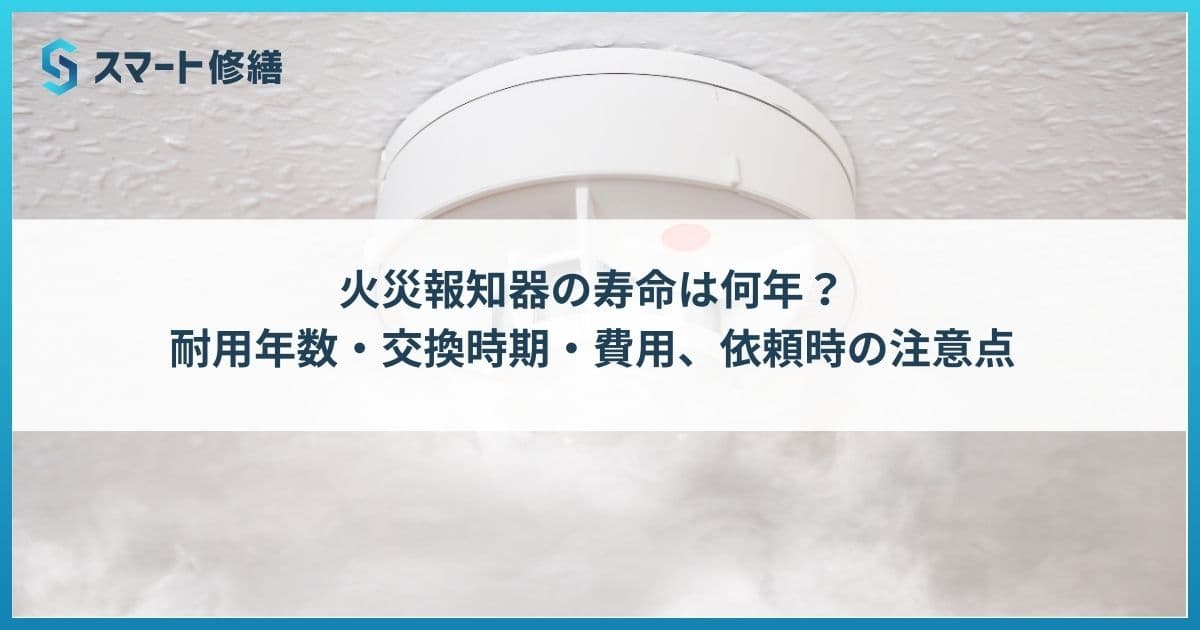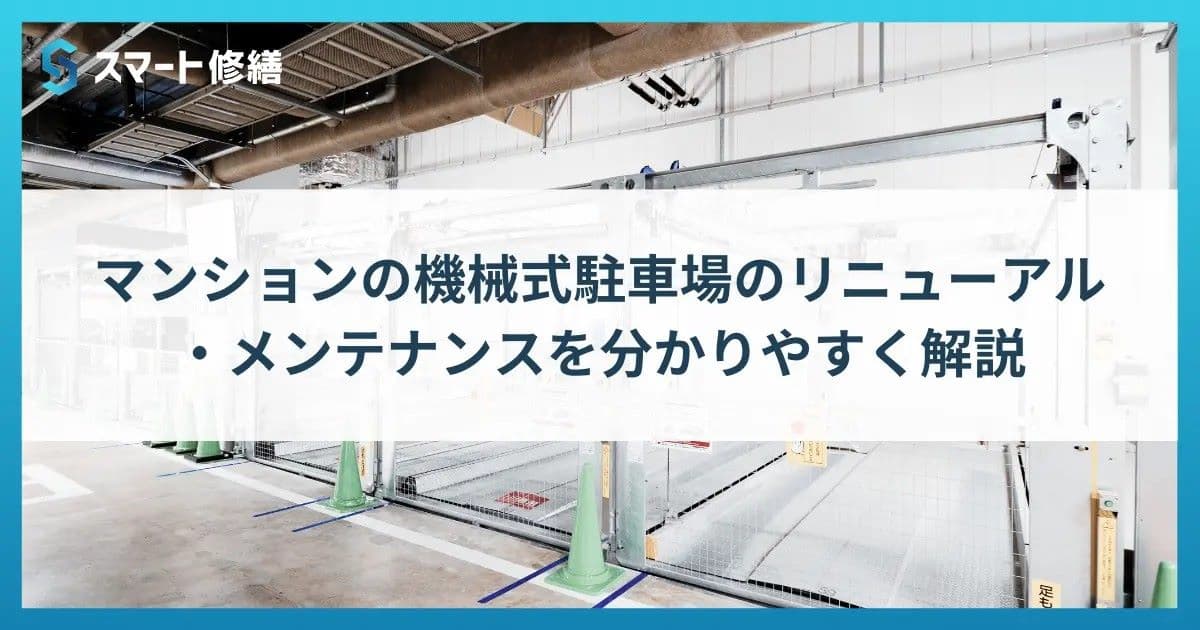マンション・ビルの火災報知器撤去費用と注意点
更新日:2025年08月29日(金)
マンションの管理組合やビルオーナーの間で、古くなった火災報知器の撤去や更新を検討するケースが増えています。たとえば、誤作動が頻発して居住者やテナントから苦情が寄せられたり、テナント退去に伴う内装工事で一時的に設備を取り外す必要が生じたりする場合です。 住宅用火災警報器は設置から約10年が交換の目安とされており、2006年前後の義務化時に設置された機器が寿命を迎えつつあることも背景にあります。しかし、消防法により設置が義務付けられているため、管理組合やオーナーは安全面や法令遵守の観点から、撤去や更新の際には慎重な判断と適切な手続きが必要です。 本記事では、マンション・ビルの火災報知器の撤去費用や注意点について詳しく解説します。
- 本記事のポイント
- 撤去の法的リスクと適法な手続きが理解できる。
- ケース別の撤去費用の相場が明確になる。
- 専門業者選定のポイントがわかる。
火災報知器は撤去しても良いのか?(消防法のルール)
結論から言えば、必要な火災報知器を勝手に撤去することは認められていません。消防法第18条では「何人も、みだりに火災報知器、消火栓等を損壊し、または撤去してはならない」と定められており、違反すると5年以下の懲役に処される重い罰則があります。これは、火災報知器が人命と財産を守る重要な設備であり、故意に外したり機能を損なう行為を厳しく禁止しているためです。
また、住宅用火災警報器の設置は消防法および各自治の火災予防条例で義務付けられており、マンションの各住戸やビル内の所定箇所には必ず設置・維持しなければなりません。
ただし、撤去が全く不可能というわけではなく、適法な手続きを踏めば可能なケースもあります。たとえば、
・老朽化した機器を新型に交換するため一時的に取り外す場合
・建物の用途変更により設置義務がなくなる場合
などです。このような場合でも、単に外すだけでなく原則として代替機器の設置や再設置が必要になります。
消防法施行規則では、消防用設備等の工事を行う際には所轄消防署への工事計画届け出・完了報告が義務付けられていますが、「撤去」単独の工事については着工届・設置届の提出義務はありません(※大規模・特殊施設では例外あり)。しかし、消防庁の通達によれば撤去時には事前に建物関係者から消防へ情報提供を求め、実態を把握することが望ましいとされています。
要するに、消防署への事前相談・承認なしに勝手に撤去しないことが重要です。撤去後に新たな機器を設置する際は、所轄消防署へ正式な設置届(概要表、図面等の提出)が必要になる点にも注意してください。
火災報知器の撤去にかかる費用相場とケース別目安
実際に火災報知器を撤去・交換する際の費用は、工事内容や機器の種類によって大きく異なります。代表的なケース別の費用目安を以下に示します。
共同住宅の各住戸内にある単体型(住宅用)火災警報器の撤去費用
電池式など単独型の住宅用火災警報器の場合、機器本体の価格は1個あたり約5,000~15,000円が相場です。実際に業者に依頼して取り外し・交換する場合は、新品代と作業費を含め1台あたり1~2万円前後が目安となります。なお、電池式の場合は自分で取り外すことも可能ですが、配線で連動した100V式(有線式)の場合は資格を持つ業者による工事が必要です。
連動式火災報知システムの一部撤去費用
ビルや大規模マンションで使われている自動火災報知設備の場合、感知器1つ外すだけでも受信盤(制御盤)側で回路の変更やダミー抵抗の設置など専門的な作業が伴います。そのため、部分撤去でも数万円の費用がかかることが一般的です。撤去箇所が複数に及ぶ場合や、受信盤の改造・交換を伴う場合はさらに費用が増加し数十万円規模になることもあります。
感知器や配線の大規模撤去工事費用
テナント退去に伴いフロア全体の自動火災報知設備を撤去する、あるいは建物の用途変更で不要になった感知器と配線をまとめて撤去する場合は、工事範囲が広くなる分コストも高くなります。天井裏や壁内の配線撤去、高所作業、撤去跡の穴埋め補修などが発生し、数十万円~数百万円規模になることもあります。大規模な撤去工事の際は、複数の業者から相見積もりを取り、慎重に検討することをおすすめします。
火災報知器を撤去する前に知っておきたい注意点
火災報知器の撤去・交換を進める場合、法令遵守と安全確保のために以下の点に注意してください。
消防署への届出・相談を確実に行う
消防法上は撤去工事のみでは書類届出の対象にならない場合もありますが、事前に所轄消防署へ相談し、必要な承認や手続きを確認することが不可欠です。消防当局も、関係者から情報提供を受けて実態把握することが望ましいとしています。無届けで設備を外した結果、消防検査で指摘を受けたり使用停止を命じられたりすれば、結局再設置の手間と費用が発生します。計画段階で消防署に相談し、必要な手順(書類提出や代替措置など)の指示を仰ぎましょう。
違法な撤去による罰則・行政指導のリスク
設置義務のある火災報知器を無断で撤去したまま放置すると、消防法第18条違反となり、最悪の場合は刑事罰の対象となり得ます。また、多くの自治体では建物の定期防火点検制度があり、点検報告で設備未設置が発覚すれば是正指導や改善命令が出されます。悪質な場合や火災発生時に設備未設置が被害を拡大させた場合には厳しい責任追及を受けるリスクがあります。「鳴りやまないから外しておこう」などと安易に撤去せず、必ず正規の手続きで対処してください。
誤作動が多い場合の代替策(更新・交換)
古い火災報知器で誤作動が頻発する場合、撤去ではなく機器の更新や環境改善によって解決できる可能性があります。煙式感知器はホコリや湿気で誤報しやすく、経年劣化も誤作動の一因です。メーカーや消防当局は設置後10年を目安に交換を推奨しており、誤作動が増えてきたら撤去ではなく新しい機器への交換を検討すべきサインといえます。
また、台所など誤報が起きやすい場所では煙感知器を熱感知器に替える、感知器の位置を変更する、防塵カバーを付ける等の対策も考えられます。最新の住宅用火災警報器には自己診断機能やリモート試験機能付きの製品もあります。「撤去」以外の安全策について、消防設備士や消防署に相談してみましょう。
業者選びのポイントと相見積もりのススメ
火災報知器の撤去や交換工事を依頼する際は、信頼できる専門業者を選ぶことが大切です。消防設備は人命に関わる重要設備のため、価格だけでなく技術力や適法な施工が担保されるかを見極めましょう。以下に業者選定の主なポイントをまとめます。
消防設備士(甲種)など有資格者に依頼する
消防用設備の工事は国家資格である消防設備士(甲種)の資格を持つプロでなければ施工できません。有資格者であっても日頃から消防設備工事に精通しているかは重要で、消防法改正への対応力も業者によって差があります。業者に依頼する際は、資格の保有状況や経験を確認し、消防署提出書類の作成・手続きまで含め対応できるか尋ねてみましょう。
見積内容の明確さと適正価格
見積書は内訳が詳しく書かれており、どの設備にいくらかかるか明瞭に示してくれる業者を選びましょう。「一式○○円」といった大雑把な見積りでは、後から追加費用が発生する恐れもあります。不明点は事前に質問し、丁寧に説明してくれる業者か見極めます。
また、費用面では業者によってばらつきがあります。自社施工でない業者は下請けに丸投げして中間マージンを載せるケースもあり、その分割高です。複数の業者から相見積もりを取り、価格と内容を比較検討することが大切です。相見積もりにより極端に高い・安い業者や不明瞭な見積もりを避け、適正価格で質の高いサービスを提供してくれる業者を選定しましょう。
アフター対応や専門性も考慮
撤去後の再設置工事や定期点検までトータルに任せられる業者だと安心です。消防設備は設置して終わりではなく維持管理も必要なため、長期的に信頼できる業者をパートナーに持つとよいでしょう。施工の迅速さや緊急対応力もポイントになります。過去の施工実績や他の管理物件での評価なども参考に、総合的に判断してください。
まとめ:撤去は慎重に。まずは専門家へ相談を
火災報知器の撤去費用や手順について解説してきましたが、最も重要なのは安全と法令順守です。火災報知器は人命を守るライフラインであり、安易な撤去は重大なリスクを伴います。費用面だけで判断せず、まずは信頼できる消防設備士などの専門家に相談してみましょう。専門家に相談すれば、撤去せずに済む代替策や最適な更新プランが見つかるかもしれません。仮に撤去が避けられない場合でも、適切な手続きを踏むことでトラブルや違法性を回避できます。本記事のポイントを踏まえ、慎重に検討した上で行動するようにしてください。消防署や資格者との連携のもと、安全かつ適正な方法で火災報知器の問題解決を図りましょう。
火災報知器等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- インターホンのリニューアル工事の支援実績は多数(過去半年で数千戸分、2025年1月現在)。数百戸の多棟型マンションでの実績も複数。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。インターホンのメーカー系のを含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料