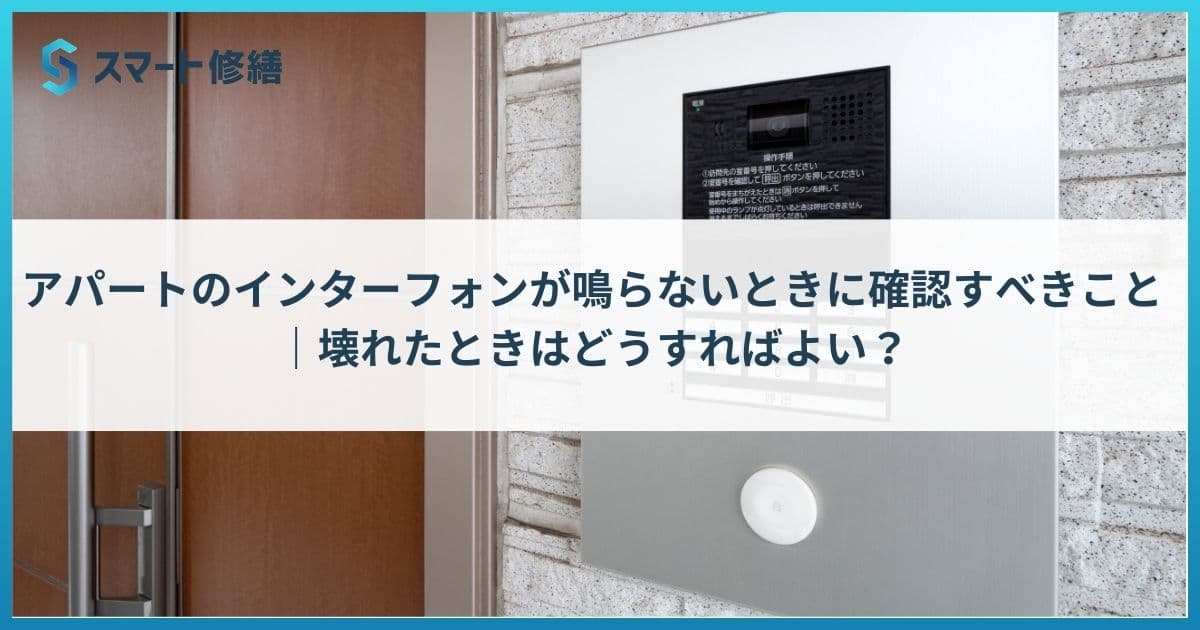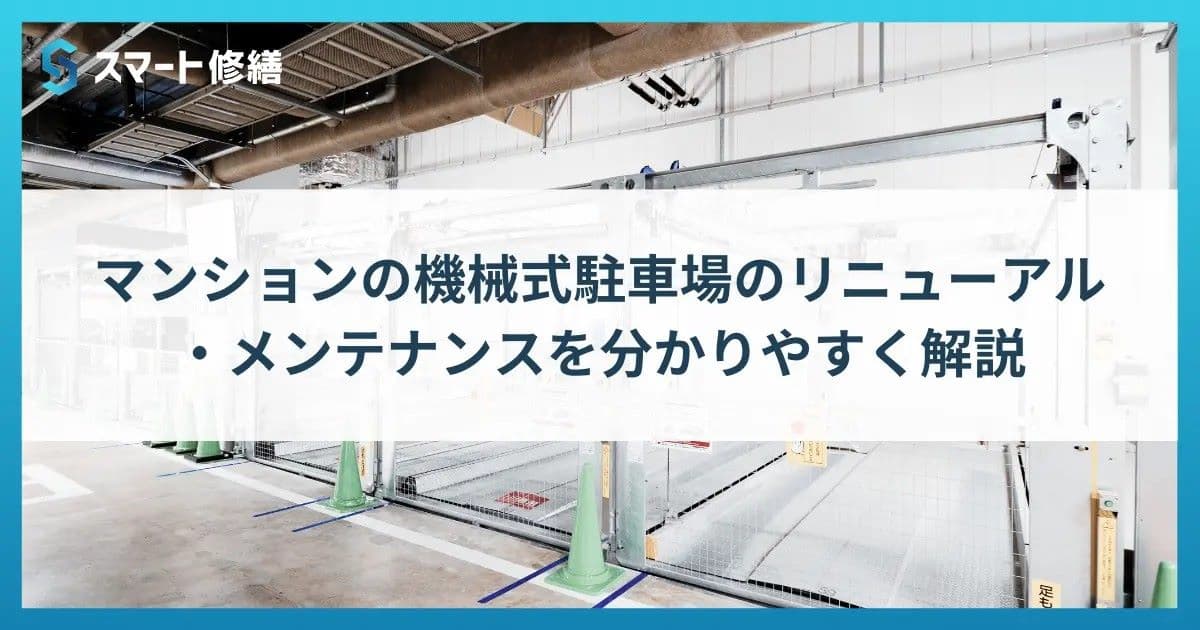マンションのモニター付きインターホン交換を成功させるコツ3選
更新日:2025年06月29日(日)
本記事では、マンション管理組合がモニター付きインターホンの交換工事を成功させるための実践的なコツと、最新の費用相場や注意点について解説します。経験豊富な専門家や公的機関の情報を交えながら、適切な計画立案と施工管理で安心・安全なリニューアルを実現しましょう。
- 本記事のポイント
- モニター付きインターホンの防犯・利便機能を学べる。
- 導入費用や見積比較の重要性がわかる。
- 導入工事の進め方や注意点を把握できる。
モニター付きインターホンとは?(機能・利便性・防犯性)
モニター付きインターホンとは、カメラとモニター画面を備えた集合住宅向けインターホンシステムです。エントランスに設置された集合玄関機(カメラ付きインターホン)と各住戸内の受話モニターが連動し、来訪者の映像と音声を室内から確認できます。居住者はオートロックドアを室内から解錠することができ、不審者や不要なセールスの侵入防止に効果を発揮します。警視庁も「訪問者を屋内から確認でき、見知らぬ人にもドア越しで対応できるので有効」とカメラ付きインターホンの設置を防犯対策として推奨しています。
実際、空き巣犯は留守かどうか確かめるためインターホンを鳴らすことが多いですが、録画機能付きのインターホンがある住戸は避ける傾向があり、防犯効果が高まるといわれます。
モニター付きインターホンの利便性も見逃せません。例えば留守中に来訪者があった場合でも、後から録画された来訪者の顔やメッセージを確認できる機種があります。高齢者にも配慮した大きな画面やボタン設計、広角カメラ&ズームで玄関前の様子を詳しく映す機能など、最新モデルは操作性・視認性が向上しています。また、スマートフォン連携機能を備えた製品も登場しており、外出先からインターホンに応答したり解錠したりすることが可能です。停電時でも非常放送ができるバックアップ機能など、防災面の強化も図られており、モニター付きインターホンへの更新は防犯性と利便性を同時に高める有効なリノベーションと言えるでしょう。
マンションのインターホンには主に 「集合住宅システム(オートロック式)」 と 「住戸完結システム」 の2種類があります。オートロック式ではマンション共用のエントランスにカメラ付き集合玄関機を備え、各住戸内のモニター親機と連動しています。来訪者は部屋番号を呼び出し、居住者が室内モニターで映像を確認して解錠する仕組みです。火災報知設備とも連携可能で、非常時にはインターホン経由で警報放送が流れるなど、マンション全体で一体のシステムになっています。
一方、住戸完結システムではオートロックの共用玄関が無く、各住戸の玄関前に子機(カメラ付き玄関インターホン)が設置される独立型です。この場合、配線工事不要のワイヤレスインターホンで各戸が個別に交換できるケースもありますが、機器の扱いが共用部分か専有部分か管理規約を確認する必要があります。なおマンションによっては、一斉に全戸交換することで1戸あたりの工事費用を割安にできるため、アンケートで意向を集約したうえで全戸同時のリニューアルを行うのが望ましいでしょう。
マンションのモニター付きインターホン交換を成功させるコツ3選
マンション管理組合がインターホン交換工事をスムーズに進め、適正な費用で高機能なモニター付きインターホンを導入するには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
コツ1:工事費用の相場を調べて予算計画を立てる
インターホン交換工事を検討する際は、まず概算費用の相場を把握することが重要です。相場感を持つことで、過度に高額な見積もりを見抜けるほか、組合内での予算調整や合意形成もスムーズになります。
交換費用は、マンションの規模(戸数)や導入する機種・機能によって大きく異なります。相場を知らないままでは、業者から提示された金額が妥当かどうかの判断が難しく、予算オーバーや不要な高額契約のリスクが高まります。事前に「30戸で約○百万円」といった大まかな金額感を把握しておくことで、総会での説明もしやすくなります。
一般的な目安として、集合住宅のインターホン交換費用は、1戸あたり税抜10〜18万円程度です。導入する機能が高度になるほど価格も上がり、特に火災報知設備との連動機能を加える場合は、機器代・工事費ともに大きく膨らむ傾向があります。
これらの相場を踏まえて、長期修繕計画に基づく積立金の範囲内で対応可能かを確認し、不足が見込まれる場合は一時金徴収などの手段も早めに検討しておきましょう。
コツ2:複数の業者に相見積もりを取って比較検討する
必ず複数の施工業者から見積もりを取得し、提案内容と金額を比較検討しましょう。相見積もりにより競争原理が働き、適正価格かどうかを判断しやすくなります。
マンション管理組合がインターホン更新を行う際、管理会社から紹介された1社だけに依頼すると、その業者の言い値で契約してしまう恐れがあります。特に管理会社や既存の設備業者との関係性から割高な見積もりが提示されるケースも指摘されています。
複数社に声をかけ相見積もりを取ることで、各社の提示金額や工事内容を比較でき、妥当な相場感に基づいた判断が可能になります。場合によっては数百万円単位で当初見積もりより安くなる例もあり、組合のコスト負担軽減につながります。
また、流通経路の無駄を省いた一次代理店兼工事会社を選ぶことや、既存業者とのしがらみがない独立系業者を含め比較することが、コストダウンのポイントです。管理組合自ら複数社に見積依頼し、公平に競争入札を行うことで、内容・金額とも適切な工事プランを見極められるでしょう。
実際に相見積もりを取る際は、少なくとも2~3社以上から見積もりを集めるのが理想です。各社に現地調査を依頼し、現状のシステム構成や要望する機能を伝えたうえで提案書と見積書を作成してもらいます。提示内容は、総額費用だけでなく内訳(機器代・工事代)や保証内容、工期、メンテナンス体制などもチェックしましょう。他社と比較して不明瞭な費用項目や過剰な金額がないか精査し、疑問点があれば遠慮なく問い合わせます。
相見積もりにより割高な項目の削減交渉やグレード見直しもしやすくなります。もし管理会社経由で依頼する場合でも、組合主導でセカンドオピニオン的に他社比較を行うことで、結果的に数十万円以上のコスト削減や内容充実が図れる可能性が高まります。
コツ3:専門家に相談し計画段階からサポートを得る
建物設備の専門家に相談し、計画立案から工事監理までプロの助言を得ましょう。マンション管理士や修繕コンサルタント、一級建築士事務所などの専門家は多数の事例経験があり、技術的・法規的な観点から最適な工事を提案してくれます。
モニター付きインターホンの更新工事は、機器選定や施工方法、法令遵守など検討すべき事項が多岐にわたります。管理組合だけで判断が難しい場合、第三者の専門家を活用することで失敗リスクを減らせます。例えば古いマンションではインターホンが非常通報装置を兼ねているケースがあり、消防法上の手続きが必要かどうか専門知識が求められます。また、各社の提案する機種の特徴や価格差を評価し、長期的に見た費用対効果を検証するにも専門的な視点が不可欠です。
ディー・エヌ・エーグループの一級建築士事務所「スマート修繕」には、ゼネコン・デベロッパー・管理会社出身の建築士や施工管理技士が在籍し、過去半年で数千戸分のインターホン工事支援実績があります。
マンションのモニター付きインターホンを交換するときにいくらかかる?(価格相場と変動要因)
マンションのモニター付きインターホンを交換する際、費用は建物の規模や設備仕様、工事の難易度などによって大きく変動します。一般的な工事相場は1戸あたり10〜18万円(税別)ですが、搭載機能や設置条件によって前後するため、費用構成と主な変動要因を把握しておくことが重要です。
費用の基本構成
インターホン交換にかかる費用は、大きく分けて以下の3つで構成されます。
機器本体代(親機・子機)
機能やグレードにより価格差が大きく、全体費用に占める割合も高めです。
設置・配線などの工事費
各住戸内の施工や共用部の配線作業により、1戸あたり数千円〜数万円の差が生じます。
調整・部材費等の付帯費用
小規模な項目ながら、工事の内容によって総額に影響します。
例えば、既存配線を再利用できる場合は工事費を抑えられますが、新たに配線ルートを引き直す場合や、高層階までの施工が必要な場合はコストが上昇します。
機能による価格差と拡張性の考慮
インターホンの機種は、「音声通話のみ」から「録画機能付き・モニター付き」「スマホ連携可能モデル」など幅広く展開されています。特に以下のような機能を追加する場合は、本体価格・工事内容ともに費用が増える傾向にあります。
カメラ付きモニターによる映像確認
録画・保存機能
スマートフォンとの連動
火災報知設備・非常ボタンとの連携
オートロック設備との連動(集合玄関機や管理室設備の更新を含む)
これらの高機能モデルを選ぶ場合、標準的なモデルよりも高額になるのは避けられませんが、組合の防犯対策方針に合致するのであれば、必要な投資として前向きに検討する余地があります。
コストを抑える工夫
費用面での工夫としては、以下のような取り組みが効果的です。
全戸一括での発注によるボリュームディスカウント
既存配線の活用が可能な機種の選定
機能の過不足を見極めたグレード選択
複数社からの相見積もり取得による価格比較
バランス重視の選定を
費用の目安を把握したうえで、機能性・将来性・施工性のバランスを見極め、組合の合意形成を図りながら最適なプランを検討することが、満足度の高いリニューアル工事につながります。
モニター付きインターホン交換工事の注意点
モニター付きインターホンの交換工事を成功させるには、費用や業者選定以外にもいくつか注意すべきポイントがあります。特にマンション特有の制約や手続きについて、事前に把握しておきましょう。ここでは「住民への周知徹底」「法令(消防設備)対応」「管理規約の確認」の3つの注意点を解説します。
注意点1:工事前後の住民への告知と調整を徹底する
モニター付きインターホン交換工事では、各住戸内に業者が立ち入って親機を交換する必要があります。そのため事前に十分な住民周知と日程調整を行うことが重要です。全戸の作業スケジュールが決まったら、少なくとも工事の2週間前までには各住戸にお知らせ文書を配布し、掲示板や回覧板でも周知しましょう。
必要に応じて工事内容の住民説明会を開催し、インターホンが一時的に使用できない時間帯の共有や、留守宅の場合の鍵の預け方など工事期間中の注意事項を詳しく説明します。
特に在宅が必要な作業日程については、事前のアンケート等で各戸の都合を把握し、可能な限り希望を反映した工程表を組むことが望ましいです。張り紙やポスティングによる告知に加え、理事会役員が声かけするなど双方向のコミュニケーションを心がけ、住民の不安や疑問に答えておきます。工事当日も開始・終了時刻を厳守し、作業員の出入り管理を徹底しましょう。十分な周知と配慮があれば、住民の協力も得られて工事はスムーズに進行し、完成後の新しいインターホンも安心して利用開始できます。
注意点2:法令・消防設備との関係を確認する
インターホン設備は単なる通話装置ではなく、防災設備の一部として機能している場合があります。たとえば、火災時に管理室へ自動通報したり、高齢者世帯向けに非常通報ボタンを備えていたりと、消防設備と連動しているケースです。
特に近年建設されたマンションでは、こうした通報機能がインターホンに一体化されていることがあり、このような機器は「消防用設備等」として扱われます。勝手に交換や撤去を行うと、消防法違反に問われる可能性があります。
そのため、管理組合として全戸一斉にインターホンを交換する場合は、まず既存設備に消防設備としての役割がないかを事前に確認しましょう。連動型の設備を交換する際は、所轄消防署への届出や事前相談が必要となるほか、図面提出や消防設備士による施工が求められるケースもあります。
届出を怠った結果、機能が既存より劣ると判断されれば、消防設備点検で「不適合」と指摘され、是正工事や再申請が必要になることもあります。
トラブルを避けるためには、計画段階から消防署・消防点検業者・施工業者との連携を図ることが重要です。消防法に精通し、届出代行も行ってくれる施工会社であれば安心ですし、交換後の初回点検で適合を得るための体制も整えやすくなります。
インターホン交換であっても、「防災の一部」という意識を持って慎重に取り組むことで、マンション全体の安全と安心を確保することにつながります。
注意点3:管理規約の確認と必要な手続きを踏む
マンションのインターホン交換工事にあたっては、管理規約上の位置付けと組合決議事項を事前に確認しましょう。インターホン設備が「共用部分」か「専有部分」かにより、費用負担者や工事の進め方が変わるためです。
通常、管理室内の制御盤やエントランスの集合玄関機などは共用部分とされますが、各住戸内の親機や玄関前の子機は専有部分とみなされるケースが多いです。規約に特段の定めがなければ住戸内インターホンの修理費用は各区分所有者の負担となります。しかし、住戸内親機が火災感知器等の警報装置と一体化し、共用の防災設備と連動している場合には、専有部分の機器であっても共用設備として管理することが合理的とされています。その場合、規約でインターホン設備を共用部分扱いに明記し、管理組合負担で補修・更新することが可能です。実際、一般社団法人マンション管理業協会の相談事例でも「火災警報と連動するインターホンは共用部分とみなし、管理組合が管理できる」との見解が示されています。したがって、ご自身のマンションの規約を確認し、必要なら専門家の助言を得てインターホン設備の区分を明確化しておきましょう。
また、共用部工事として全戸一斉交換を行う場合は、組合の総会での決議が必要です。インターホン更新は長期修繕計画に沿った改良工事の一種ですので、通常は普通決議または特別決議事項となります(管理規約や区分所有法の定めによる)。特に専有部分にも影響する設備更新のため、総会での合意形成は不可欠です。突然インターホンが故障し使えない状態になってから慌てて臨時総会を開くのは大変ですから、故障増加や部品供給期限(製造終了後7年など)を踏まえ竣工後15年ほどを目安に計画的に更新決議を行うことが望ましいとされています。実際に交換工事を進める段階では、理事会で機種と業者を決定し総会に上程、承認可決後に契約締結という手順になります。これらのプロセスを踏み、適法かつ組合合意のもとで工事を行うことで、後のトラブルを防止できます。
最後に、交換工事後は管理規約の付属設備一覧等に新しいインターホンの情報を追記し、維持管理上の扱い(共用/専有や管理組合/各戸の責任分界)を明確にしておきましょう。将来の理事会メンバー交代時にも引き継がれるよう、議事録や修繕記録に経緯を残すことも大切です。
まとめ:適切な金額で工事を依頼しよう
モニター付きインターホンへの交換工事は、マンションの防犯性・利便性を高める良い機会です。管理組合として、今回ご紹介したポイントを押さえて計画を進めれば、適切な料金で安心できる工事を依頼できるでしょう。まず費用相場を把握して予算を組み、複数業者の見積もりを比較することで適正価格を見極めます。必要に応じて専門家の意見も取り入れ、機種選定や法令手続きを万全に行いましょう。工事前には住民への周知と合意形成を十分に行い、当日は安全管理とマナーに配慮して作業を実施します。消防設備との絡みや管理規約上の手続きも確認し、法令順守と組合決議のもとで計画を遂行することが重要です。
インターホンは日常的には意識されにくい設備ですが、いざという時に住民の命と暮らしを守る縁の下の力持ちです。適切な時期に最適な機能を備えたモニター付きインターホンへ交換することで、マンションの価値と安全性は大いに向上します。経験と専門知識を活かして計画を立て、ぜひ管理組合主導で納得のいく工事を実現してください。新しいインターホンがもたらす快適で安心な暮らしは、きっと住民の方の満足度向上につながるでしょう。
インターホン等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- インターホンのリニューアル工事の支援実績は多数(過去半年で数千戸分、2025年1月現在)。数百戸の多棟型マンションでの実績も複数。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。インターホンのメーカー系のを含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
佐藤 龍太
不動産会社および管理会社にて、マンションやビルの修繕・管理業務に長年従事。マネージャー職を歴任し、これまでに300件近い修繕工事に携わる。特にインターホン設備においては、年間3,000戸以上(2025年現在)の見積取得を行うなど、設備改修の実務に精通。豊富な現場経験と管理業務の知見を活かし、マンション修繕に関する実践的かつ専門的な視点で記事を監修。
こちらもおすすめ
24時間対応通話料・相談料 無料