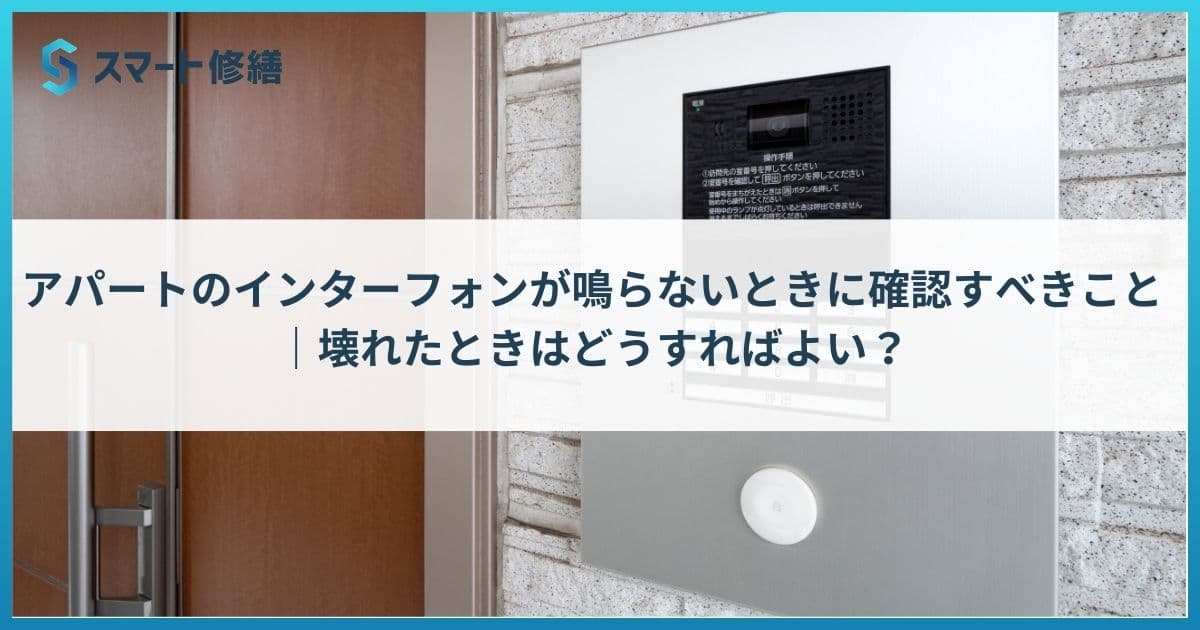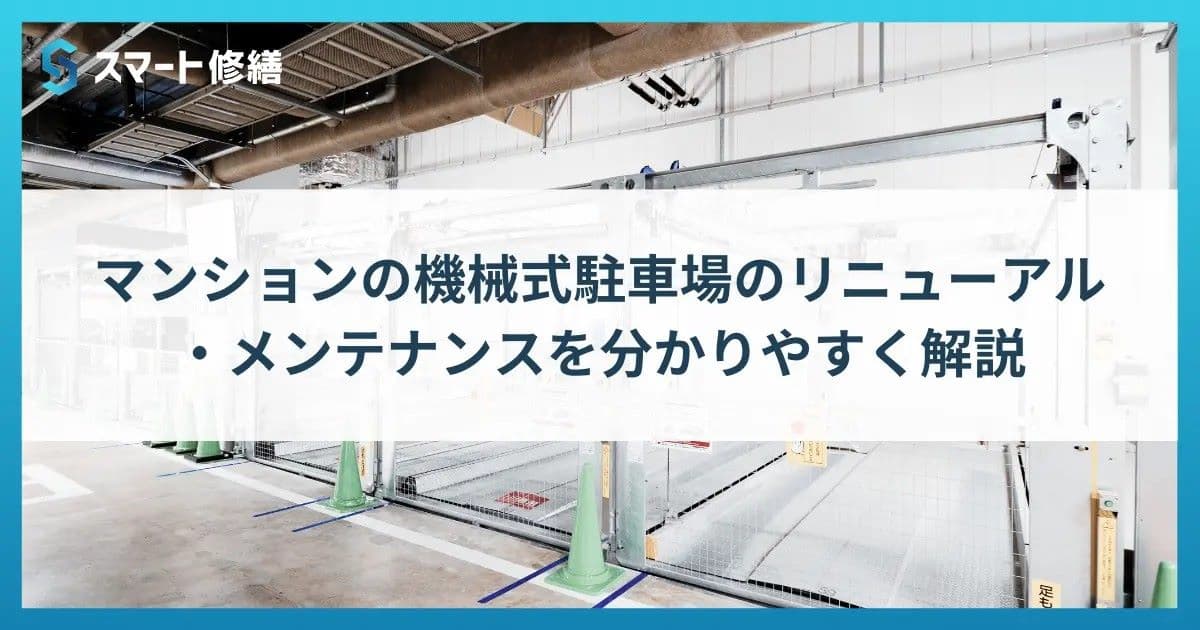【マンション】セコムのインターホン交換で知っておくべき工事の段取りと費用
更新日:2025年06月30日(月)
本記事では、セコムのインターホン交換を検討するマンションの管理組合や居住者の方向けに、セコム製インターホンの概要、交換工事の段取り(マンション特有の流れ)、費用の目安、そして注意すべきポイントを解説します。最後に、信頼できる専門家への相談方法についてもまとめていますので、マンションの安全・安心のための「セキュリティリフォーム」にぜひお役立てください。
マンション向けセコムのインターホンに関する概要
セコムのマンション用インターホンは、防犯会社セコムの24時間オンライン監視サービスと連携した高度なセキュリティシステムです。単なる「玄関の呼び鈴」ではなく、火災や非常ボタンによる通報機能まで一元管理できるのが特徴で、古いインターホン設備からのリニューアルで安全性と利便性が大きく向上します。
セコムが提供する「セコム・マンションセキュリティシステム」は、各住戸のインターホン親機(室内機)とエントランスの集合玄関機を中心に、火災監視や非常通報などを24時間セコムが見守る仕組みです。公式サイトにも「インターホン+セキュリティを一元管理」し、「24時間セコムとつながっている安心」を提供するシステムと明記されています。
具体的には、各住戸に設置されたインターホン親機でエントランス来訪者の映像確認・解錠を行えるほか、非常ボタンで緊急通報すればセコムの警備員が駆け付けるなど、防犯・防災・緊急対応が一体となった機能を備えています。例えばセコムの最新システムでは、管理人室や共用部・各住戸の火災センサー監視、各住戸の非常通報を標準機能とし、オプションで各住戸の防犯センサー連動や高齢者見守りサービスまで追加可能です。
このようにセコムのインターホンは、Panasonic(パナソニック)やアイホンなど一般的なインターホンメーカーの機器をベースにセコム仕様にカスタマイズし※、常時プロの目で見守るという「プラスαの安全」を提供している点が大きな特徴です。※あるマンションではセコム製インターホンMS-5M(パナソニック製品をベースにセコム向けカスタマイズされた機種)を導入し、火災報知機連動やセコムへの自動通報機能を利用しています。
インターホン工業会によれば、集合住宅用インターホン市場はパナソニックとアイホンで約9割を占めますが、セコムのシステムはそうした信頼性の高い機器にセコム独自の通報サービスを組み合わせたものと言えるでしょう。
セコムのインターホン交換で知っておくべき工事の段取り(マンション専用)
マンションでセコムのインターホンを交換する際は、(1) 管理組合での事前計画と予算確保、(2) 発注から施工までのスケジュール調整、(3) 居住者への周知と施工立会い、という3つの段取りが重要です。
管理組合による計画立案と予算確保が必要
マンションのインターホン設備は共用部分に該当するケースが多く、基本的に個人の判断で勝手に交換できるものではありません。そのため、まず管理組合が中心となって全体の交換計画を立て、総会の議決や修繕積立金の活用など予算措置を講じる必要があります。適切な計画立案により、資金面と手続面の両方でスムーズな工事準備が可能になります。
共用設備としての扱い
オートロック式インターホンなど集合住宅システムの場合、エントランスの集合玄関機と各戸の親機が一体となったマンション全体の設備です。このため各住戸がバラバラに機種変更することはできず、管理規約に従い管理組合が一括して更新するのが通常です。まずは管理規約を確認し、インターホンが共用部分に該当するか、区分所有者(各戸)の負担範囲がどう規定されているかを把握しましょう。規約によっては各戸内のインターホン機器を専有部分扱いとする場合もありますが、その場合でもマンション全体で統一機種に交換する方が1戸あたりのコストを抑えられるため、管理組合として一斉交換することが望ましいとされています。
総会決議と資金確保
インターホン交換はマンションの修繕計画に沿って行われる改修工事の一種です。多くのマンションでは、長期修繕計画の中でおおよその交換周期(15年)と費用積立が検討されていますが、いざ実施となれば管理組合の総会での決議が必要になる場合があります。特に費用が高額になる場合や、修繕積立金を充当する場合は、区分所有法や管理規約に従い所定の決議が求められます。費用負担の考え方はマンションにより様々ですが、一般的には共用部であるエントランス集合玄関機等は管理組合負担、各戸内の親機は各所有者負担とするケース、あるいは全て管理組合負担(積立金から支出)とするケースがあります。どちらにせよ、総事業費の見積もりを把握し、資金計画を明確にすることが重要です。インターホン交換費用の相場は後述するように1戸あたり10~18万円程度とされ、数百万円~数千万円規模の工事となります。
発注から施工まで十分なリードタイムを確保する必要がある
マンション用インターホンの交換工事では、機器の調達に時間がかかる点に注意が必要です。メーカー生産品のため発注から納品まで通常数ヶ月(約2~4ヶ月程度)を要します。そのため、工事実施時期から逆算して早めに発注手続きを行い、工期に余裕を持たせることが大切です。
受注生産と納期
マンションのインターホンシステムは一般的に受注生産品であり、在庫品ではありません。現在(2025年6月時点)は、各メーカーおおむね2~4ヶ月程度で納品されるようになっています。ただし、機種や時期によっては納期が再び変動する可能性もあるため、常に最新情報の確認が重要です。管理組合としては、工事実施の少なくとも半年前までに見積取得・機種決定・発注手配を完了しておくのが安全です。余裕をもったスケジュールで計画を立てることで、納期の変動リスクにも柔軟に対応できます。
工事業者の選定
発注時期と併せて、どの業者に工事を依頼するかの選定も重要なステップです。セコムのインターホン(セキュリティシステム)を導入する場合、セコム本体やセコム提携業者が施工するケースが多いですが、他の電気工事会社が請け負う場合もあります。注意すべきは、工事業者選定に時間をかけすぎると納期に影響する点と、逆に業者選定を拙速に行うと割高な契約になる点です。見積はなるべく複数社から取り、代理店など中間マージンの少ない業者を選ぶことがコスト面で有利です。一方で防犯設備の特殊性から、セコムのオンライン通報機能などを利用する場合はセコム指定の機器・工事でないと保証が受けられない可能性もあります。そのため、複数のセコム関連業者や他社防犯会社(ALSOKなど)の提案を比較検討しつつ、信頼できる施工業者を決定しましょう。業者決定後は、速やかに契約・発注を行い、機器納品までの期間を確保します。
施工期間中の住民協力と安全確保の計画が必要
インターホン交換工事は各住戸内での作業を伴うため、住民の立会いやスケジュール調整が不可欠です。さらに工事中は一時的にインターホンや警報システムが使えなくなるため、セキュリティや生活面のフォロー策を事前に講じておく必要があります。
施工日程と立会い
マンション全戸のインターホンを交換するには、規模に応じた工事日数がかかります。目安として50戸のマンションで約1週間です。この内訳は、エントランスや管理人室など共用部の工事に2日間、各住戸内の親機交換に5日間となります。各戸の作業時間はおよそ40分~1時間程度で、その間は居住者または代理人の立会いが求められます。「在宅できない」「平日は難しい」という世帯には事前にスケジュール調整し、土日や予備日を用意するなど柔軟な対応が必要です。管理組合と施工業者は協力して工事日程表を作成し、各戸に通知しましょう。場合によっては棟ごと・フロアごとに日程を分けるなど、住民の負担が少ない計画とすることが望ましいです。
工事中の安全対策
インターホン交換工事期間中は、一時的にインターホンシステムおよび連動する警報機能が制限されます。例えば、共用部や各住戸からの火災警報・非常通報が管理人室や警備会社(セコム等)へ連絡されない状態になります。また、玄関オートロックが停止したり、各戸で呼び出し音が使えない時間帯も発生します。これらの点を踏まえ、工事前に全居住者へ周知徹底することが重要です。具体的には、「●月●日~●日はインターホン交換工事のため、非常ボタン押下時のセコム自動通報が停止します」「工事期間中の緊急連絡先(管理会社や警備員直通番号)はこちら」等、万一の場合の対処法を掲示・配布しましょう。
また、オートロック無効化で外来者が出入りしやすくなる場合は臨時の防犯対策も検討します。例えば、管理人や警備員による見回り強化、防犯カメラの活用、住民にも戸締りをより一層呼びかける等の対応です。実際に、玄関機と住戸機の両方を交換する間の短時間、オートロックを解錠したままにした結果、部外者が建物内に入ってしまった例も報告されています。こうしたトラブルを防ぐには、工事担当者と管理組合が綿密に打ち合わせ、各日の作業完了後に異常がないか確認するなどの対策が欠かせません。工事の段取り段階から「住民の安全最優先」を念頭に置き、計画を立てるようにしましょう。
実際の施工現場では、古いシステムと新しいシステムを並行稼働させながら順次切替を行うケースがあります。一日に全戸を交換しきれない場合、未交換の住戸では旧インターホンを暫定利用しつつ、他の住戸では新システムをテスト稼働するといった具合です。この際、旧システムと新システムを接続する中継器の設置や、配線の追加工事が必要になることもあります。
マンション向けセコムのインターホン交換に関する注意点
セコムのインターホン交換工事を成功させるため、以下のポイントにも注意が必要です。
注意1:交換時期を先延ばしにしないこと(適切なタイミングで実施)
老朽化したインターホンを放置せず適時に交換することが、マンション全体の安全確保につながります。インターホン工業会は集合住宅用インターホンの更新目安を約15年と定めており、20年近く経過すると故障頻発だけでなく「部品打ち切り」で修理不能に陥るリスクが高まると指摘しています。
実際に消費者事故情報でも、古いインターホンが原因の火災事故や誤作動の報告例があります。幸い大事に至らなくとも、「呼び出し音が鳴らない」「雑音で会話できない」等の不具合は高経年の機器で増える傾向です(15年を過ぎても不具合が無い場合は継続使用も可能ですが、20年を超えると急激に支障が出ることが多いとされています)。
防犯・防災設備は命に関わるインフラです。特にセコムと直結した非常通報システムを備える場合、正常に機能しないと有事に大きな危険が及びます。「まだ使えるから…」と先延ばしにせず、適切な交換時期に計画を進めましょう。メーカー公式発表や管理会社からの提案(「交換推奨」の通知等)があればそれも判断材料にしつつ、理事会で議論することが大切です。早めに動き始めれば、上記のように業者選定や資金準備の選択肢も広がります。
注意2:見積もりは複数取得し、信頼できる業者を選定すること
工事費用の妥当性を判断し、適正価格で契約するために相見積もり(複数社からの見積取得)は必須です。マンションのインターホン交換では、管理会社や従来から依頼している業者の提案だけで決めてしまうと、割高となる傾向があります。実際、「管理組合の無知に付け込んで高額な機種を押し付けられそうになった」という声や、適切に相見積もりを取った結果数百万円規模のコストダウンに成功した事例もあります。
管理会社経由の見積には、下請け業者や代理店の中間マージンが含まれているケースが多くあります。流通経路が「メーカー ⇒ 代理店 ⇒ 工事会社 ⇒ 管理会社 ⇒ 管理組合」と多段になるほど、その分コストアップ要因となります。したがって、できるだけ流通に無駄がない(自社施工可能な)業者を選ぶことが重要です。また、マンション業界は狭いため、「管理会社と特定業者とのしがらみで適正見積にならない」ケースも指摘されています。このため管理組合主体で広く業者を募り、公平な条件で見積依頼を行うことが望ましいでしょう。
セコムのインターホンに限定せず、他社の同等セキュリティシステム(ALSOKなど)や、オンライン通報なしの一般的なインターホンへの更新案も含めて比較すると、必要な機能と予算のバランスが見えてきます。万一管理会社から「相見積もりは不要」と言われても、組合の権限でセカンドオピニオンを求めるべきです。大切なマンションの工事ですから、価格だけでなく実績やアフターサービス体制も含めて総合的に信頼できる業者を選定しましょう。
注意3:居住者への周知徹底とセキュリティ維持に配慮すること
工事段取りの項でも述べましたが、居住者への情報共有と安全配慮は工事成功の鍵です。具体的な注意点をいくつか挙げます。
事前周知の徹底
工事内容・日程・各戸の協力事項を文書で明示し、全戸に配布・掲示します。特にセコムなど警備会社との契約がある場合、工事期間中は非常通報や火災連動が一時停止する旨を強調し、理解を得ましょう。「その期間中に火災が起きたら?」という不安に備え、例えば管理人室や警備員への直通電話番号を案内したり、「非常時は携帯電話で119番通報を」といった代替手段を周知します。エレベーターや掲示板にも工事のお知らせを貼り、周知漏れがないよう配慮します。
プライバシーと防犯
工事関係者が各戸を訪問する際のプライバシー保護と防犯対策も重要です。訪問時間帯はあらかじめ通知し、在宅確認をしておきます。住戸内の工事を行う際には、作業員の腕章やベストなどの着用を確認し、念のため身分証の確認も行いましょう。「工事を装った不審者」の侵入リスクを減らすためにも、オートロック解錠中の共用部見回りや、工事時間外は仮復旧しておく等の対策も検討します。
工事後のチェック
交換工事完了後には、管理組合と施工業者で最終点検を行います。各戸の通話・映像が正常か、非常ボタンでちゃんと通報されるか、火災連動は作動するか等を確認しましょう。セコムのオンライン通報サービスの場合、新システムへの切替に伴い契約内容の変更やテスト通報が必要になることがあります。業者立会いのもと試験運用を行い、万全を期すことが望ましいです。不具合が見つかった場合は速やかに調整・再工事してもらい、完了後に正式運用開始となります。引渡し後一定期間は保証がありますが、なるべく早期に問題を洗い出せるよう、居住者からの声かけ(「何か不具合ありませんか?」アンケート配布等)も行うと安心です。
あるマンションでは、工事翌日に入居者から「インターホンが鳴らない部屋がある」と報告がありました。調べると、交換時に接続ミスがあったことが判明し、すぐに業者が再訪問して対応しました。このように初期トラブルはゼロにはできませんが、事前に周知していたおかげで入居者も冷静に対処できました。工事終了がゴールではなく、その後のフォローまで含めて安全対策であることを念頭に置きましょう。
まとめ:マンションのインターホン交換は専門家に相談しよう
セコムのインターホン交換は、マンションの安全性を高める重要なセキュリティリフォームです。適切な時期に計画を立て、信頼できる業者に施工を依頼すれば、古い設備による不便や不安を解消し、24時間監視の安心と最新の便利機能を手に入れることができます。今回ご紹介したように、工事の段取りや費用面では管理組合として準備すべきことが多々ありますが、専門家のサポートを活用すれば負担を軽減できます。マンション管理に詳しいコンサルタントに中立的な立場で相談に応じてもらうことが大切です。
インターホン交換は決して安い買い物ではありませんが、安全・安心という価値への投資です。経験豊富なプロに相談しながら計画を進めることで、後悔のない形でマンションの防犯インフラを一新できるでしょう。ぜひ早めに行動に移し、快適で安全な暮らしのための第一歩を踏み出してください。
インターホン等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- インターホンのリニューアル工事の支援実績は多数(過去半年で数千戸分、2025年1月現在)。数百戸の多棟型マンションでの実績も複数。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。インターホンのメーカー系のを含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
佐藤 龍太
不動産会社および管理会社にて、マンションやビルの修繕・管理業務に長年従事。マネージャー職を歴任し、これまでに300件近い修繕工事に携わる。特にインターホン設備においては、年間3,000戸以上(2025年現在)の見積取得を行うなど、設備改修の実務に精通。豊富な現場経験と管理業務の知見を活かし、マンション修繕に関する実践的かつ専門的な視点で記事を監修。
こちらもおすすめ
24時間対応通話料・相談料 無料