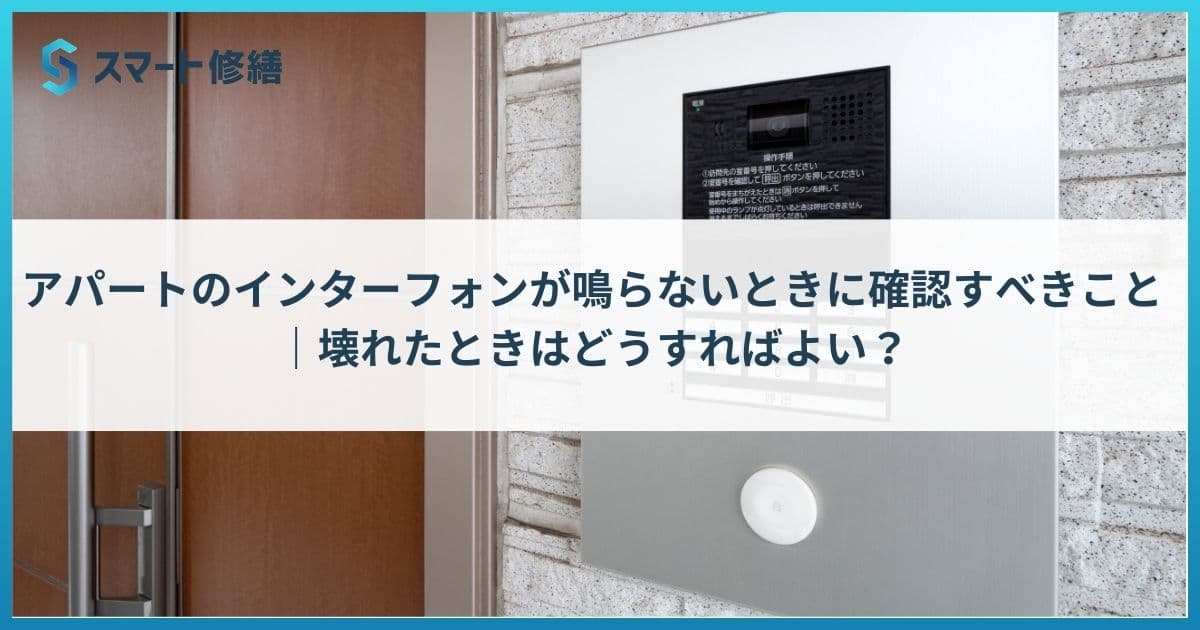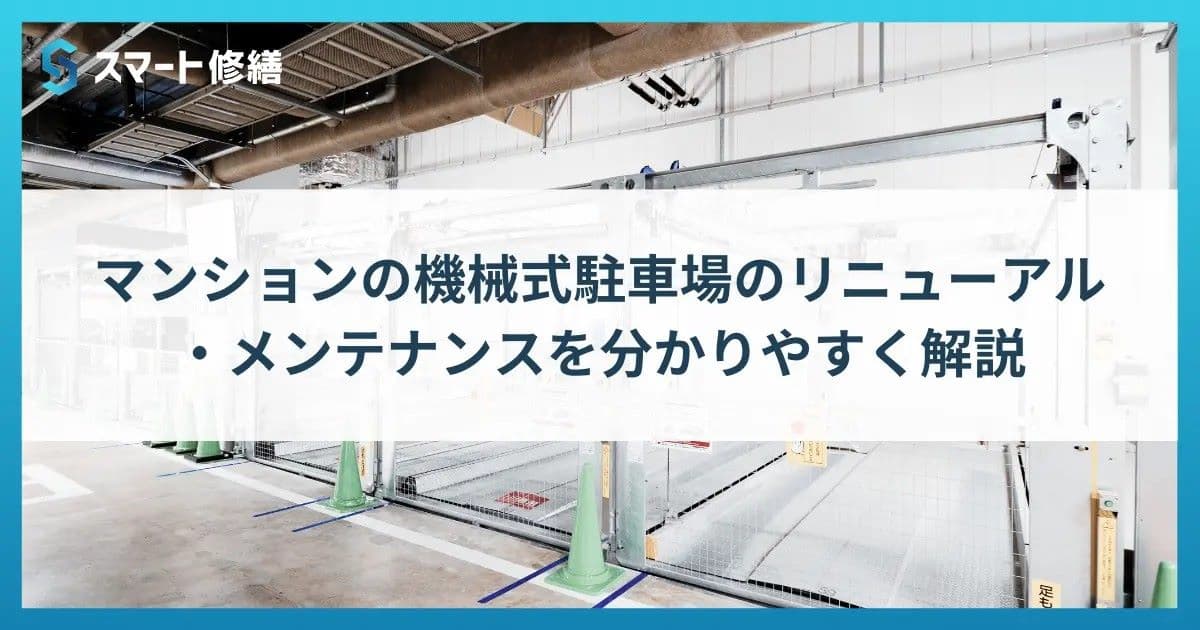中古マンションのインターホン交換工事を成功させる5つのこと【保存版】
更新日:2025年06月30日(月)
本記事では、中古マンションにおけるインターホン交換工事の基本的な進め方と、成功のために押さえておきたい5つのポイントについて、専門家の知見や公的機関の情報を交えながら詳しく解説します。中古マンションのインターホン交換を検討している人たちは、ぜひ参考にしてください。
中古マンションのインターホン工事の進め方
ここでは、中古マンションにおけるインターホン交換工事の一般的な進め方を説明します。マンション用の集合インターホン設備は建物全体で1つのシステムとして構成されているため、基本的に全住戸一斉の更新工事となります。
特にオートロック連動タイプの場合は個別に交換することができず、機器が古く交換部品が入手困難になれば全戸まとめて更新せざるを得ません。
そのため、管理組合の主導で計画立案から施工まで段階的に進めることが重要です。また、オートロックでない場合でもマンションの規約上インターホンが共用部分扱いとなっているケースがあり、居住者の一存で交換できないことがあります。
いずれの場合もまず管理組合に相談・連絡し、正式な手続きを経て進める必要があります。以下に典型的な進行ステップを示します。
事前調査と計画立案
管理組合内でインターホン更新の必要性を確認し、信頼できる業者に現地調査を依頼します。業者は共用エントランスの集合玄関機や管理室の制御装置、各住戸内の親機など現状システムを調査し、交換範囲や新システムの要件を整理します。その上で管理組合では修繕委員会等を設置して計画を立案し、長期修繕計画との整合も検討します。
見積もり取得と業者選定
調査結果をもとに業者からシステム提案と見積もりを受け取ります。分譲マンションの場合、この段階で理事会にて見積もり内容の審議を行い、必要に応じてメーカーによる実機デモや技術説明も実施されます。提示された費用や工事計画に理事会が納得できれば業者と契約を結び、管理組合の総会で正式承認を得てプロジェクトが始動します。
工事日程の調整と周知
工事実施前に、各住戸内に業者が立ち入る日程の調整が必要です。業者は管理組合と協力して住民アンケート等で各戸の希望日を把握し、それらを考慮した工程表を作成します。全戸の作業日程が決まったら、少なくとも工事の2週間前までに各住戸にお知らせを配布し、掲示板や回覧板で周知します。必要に応じて住民説明会を開催し、インターホンが使用できない時間帯など工事期間中の注意事項を説明します。
交換工事の実施
定められた日程に沿って専門業者が機器の交換工事を行います。共用部ではエントランスの集合玄関機や制御盤、管理室モニター等を新品に交換し、専有部(各住戸内)では室内親機(モニター付き受話器)と玄関子機(玄関先インターホン)を取り替えます。各戸の作業時間はおよそ40~60分程度です。50戸規模のマンションなら、共用部2日+専有部5日程度の合計約1週間で完了するのが一般的です。工事期間中は既設インターホンが使えずオートロックからの解錠もできないため、エントランスを解錠状態にして作業します(※入居者は従来通り鍵で出入り可)。防犯上、必要があれば工事期間中のみエントランスに仮設の監視カメラを設置するサービスを業者に依頼することも可能です。
動作確認と引き渡し
全戸の機器交換後、業者と管理組合によるシステム全体の試験・調整(発着呼び出しやオートロック解錠の確認)を行います。問題がなければ各住戸への操作説明や保証書類の受け渡しを経て引き渡しとなり、インターホン設備リニューアル工事は完了です。工事完了後も業者によるアフターフォローが迅速に受けられる体制かどうか、保証内容は十分かなども確認しておくと安心でしょう。
中古マンションのインターホン交換工事を成功させる5つのこと
インターホン交換工事を成功させるために重要な5つのポイントを説明します。
1.住民合意と綿密な計画立案
まずはマンション全体で合意形成を図り、綿密な計画を立てることが成功への第一歩です。管理組合内で交換の必要性・目的を共有し、費用負担や工事内容について住民の理解を得ることが欠かせません。
分譲マンションの共有設備を更新するには、理事会の決議だけでなく所有者全員による正式な承認が必要です。実際、インターホン更新工事でも理事会検討後に総会または臨時総会で正式決議を経るケースが一般的に報告されています。
また、十分な説明なく計画を進めると「本当に必要か」「負担が大きい」など反対意見が出てプロジェクトが停滞する恐れがあります。質疑応答の場を設けて費用負担や工事中の生活影響など住民の不安や疑問に丁寧に回答することが大切で、特に高齢の方や機械操作が苦手な方には「操作方法は今までと大きく変わらない」「サポート体制がある」ことを説明しましょう。こうした説明により住民の理解が深まり安心感が生まれるでしょう。
合意形成のためには、管理組合主体で以下のような対応を行います。
修繕委員会の設置
理事だけでなく有志の組合員も交えた委員会を組織し、専門家の意見も参考にしながら計画を練ります。必要に応じて業者やメーカーから直接説明を受ける場を設定し、情報をオープンに共有しましょう。
メリット・必要性の周知
新しいインターホン導入によるメリットを具体的に伝えます。例えば「来訪者をモニターで確認できる安心感」や「留守中の来客履歴が残せる便利さ」です。警視庁もカメラ付きインターホンの設置は「訪問者を屋内から確認でき、見知らぬ人にもドア越しに対応できるので有効」な防犯対策になると公式に述べています。こうした公的機関のデータを示すことで、交換工事の必要性への納得感が高まります。
総会での正式決議
規約に則り、工事内容と支出案を総会の議案に上程します。事前に配布する議案書には工事の目的・効果、費用の内訳、施工業者の選定理由などを明記し、住民に判断材料を提供します。十分な説明と質問対応を行った上で決議を取り、正式な合意を得てから契約・工事へ進みます。
2.ニーズに合った機器・機能の選定
次に、マンションの規模や利用ニーズに見合ったインターホン機器と機能を選定することが重要です。最新だからといって過剰な高機能モデルを導入するとコスト増に直結しますし、逆に必要な機能を満たさない機種では更新の意義が薄れてしまいます。
また、最近はスマートフォン連携など先進的な機能を備えたシステムも登場していますが、高齢者などスマホ非所持の住民もいるため、こうした最新機能を導入すべきかは慎重な検討が必要です。
実際、国内の集合インターホン市場ではパナソニックとアイホンの2社が大半を占めていますが、各社から複数世代のモデルが発売されており型番により機能や価格が異なります。
一般に古いバージョンの方が安価ですが、その分メーカーのサポート終了も早いため次回更新までの寿命が短くなる傾向があります。一方、新しいモデルほど長く使えますが価格は高めです。このようなトレードオフを考慮し、マンションの予算と将来計画に合った機種選びをする必要があります。
機器・機能選定にあたって考慮すべきポイントを整理します。
基本機能の充実
モニター付き親機(カメラ付きインターホン)は防犯上ほぼ必須といえます。来訪者録画機能や留守中の呼び出し通知機能があると防犯性・利便性が高まります。また、エントランスのオートロックや火災警報設備、宅配ボックスとの連動機能も現代では標準的です。これら必要不可欠な機能を満たす範囲で機種を選びます。
過剰な高機能は避ける
たとえばスマホ連携機能やネット経由の見守りサービスなどは便利ですが、その分コストが増し、マンションの年齢層によっては使いこなせない方もいるため、「あれば便利」程度の機能なら必ずしも導入せず予算優先で割り切る判断も必要です。
既存設備との適合
可能であれば既存の配線や機器ボックスを再利用できる機種を選ぶと、壁の大掛かりな工事や配線引き直しが不要になるため工事費を抑えられます。例えば現在と同じメーカーの後継機種を選べば互換性が高く、配線工事が最小限で済む場合があります。また新機器が既存機器より小型だと取り付け跡が露出するため、化粧パネルの追加が必要になり費用増となります。こうした点も踏まえ、現状の設備環境に適した仕様を検討しましょう。
将来の保守性
メーカーの部品保有期間(生産終了後7年間など)が切れると修理不能となるため、そのタイミングで全交換を迫られるリスクがあります。したがって、将来にわたり保守・部品調達がしやすいメジャー機種を選ぶ、あるいは逆に安価な機種で導入コストを下げ次回交換を早めに予定しておくなど、長期的な視点で戦略を立てることもできます。
3.信頼できる業者の選定と相見積もり
工事を依頼する業者は、マンション設備工事の実績が豊富で信頼できる会社を選びましょう。また必ず複数の業者から相見積もりを取得し、提案内容と価格を比較検討することが大切です。
管理会社に設備更新工事を一任している場合、管理会社が提示する見積もりには大きなマージン(中間手数料)が上乗せされているケースが少なくありません。
実際、集合インターホンの販売経路は管理会社系列で押さえられていることが多く、管理会社が元請けとなるとどうしても割高になる傾向があります。そのため「管理会社任せにせず必ず相見積もりを取るべき」というのが専門家の共通したアドバイスです。実際に複数社から見積もりを取って比較することで適正価格が把握でき、結果的に費用を抑えられることに繋がります。
管理会社経由で紹介された1社だけで決めず、独立系の専門業者など複数社に声をかけることで、同程度の仕様でも30%以上安くなるケースも多数あります。
業者選定と見積もり評価のポイントをまとめます。
相見積もりの取得
最低でも2~3社からは見積もりを取りましょう。マンション管理会社の系列業者だけでなく、他の独立系の設備工事会社やインターホンメーカー指定業者などにも声を掛けると良いでしょう。各社の提案内容(機種や工法、保証条件など)と見積金額を比較し、妥当な相場感を掴みます。他社との比較を嫌がったり、見積もり明細を開示しないような業者は避けた方が無難です。
見積書の内容精査
提出された見積書は項目ごとに明細が明確に示されているか確認します。例えば機器代(玄関子機・各戸親機・制御盤など)と工事費用(既存機器の撤去処分、新規機器取り付け、人件費、調整費等)に分かれているか、追加工事の有無や諸経費の内訳などが不明瞭でないかチェックしましょう。不明点があれば遠慮せず業者に質問し、内訳を把握して納得できるまで説明を受けることが大切です。
業者の信頼性
過去の施工実績や創業年数、資格保有状況(電気工事士資格は必須)などを確認します。可能であれば同規模マンションでのインターホン更新工事の実績を教えてもらい、その評価や事例を参考にしましょう。知人のマンションで既に交換工事を経験している場合は、紹介や評判を聞くのも有効です。さらに、保証内容とアフターサービスも重要な選定基準です。見積もり段階で、メーカー保証とは別に施工不良に起因する不具合への独自の保証期間を設けているか確認しましょう。「工事後○年間は無償対応」など明言する業者は信頼できます。契約前には工事範囲・工期・支払条件・保証内容などを記載した契約書面を取り交わし、責任の所在を明確にしておくことも信頼性確保につながります。
4.工事スケジュールの調整と丁寧な周知
工事日程の調整は念入りに行い、全住戸への事前周知・説明を徹底しましょう。住民への配慮ある対応が、工事を円滑に進めるカギとなります。
インターホン交換工事では各戸内に作業員が入りますし、工事期間中は一時的にインターホンやオートロックが使用不能になる時間帯も生じます。そのためスケジュール調整を誤ると、留守宅があって作業が進まない、住民がインターホン不通に戸惑う、セキュリティが手薄になるといったトラブルにつながりかねません。
事前に住民一人ひとりの都合を聞き取り工程表を作成し、少なくとも2週間前までに通知するなど周到な準備を行うことが推奨されます。大規模マンションの事例では、工事開始の3~4週間前から各戸の希望日アンケートと日程調整を行い、決定後は各戸へのお知らせ配布と掲示板告知で周知徹底しているケースがあります。また、工事の数日前には再度リマインドし、必要に応じて住民説明会を開いて疑問点を解消している管理組合もあります。さらに、防犯面では工事期間中オートロックを解錠状態にするため、業者が仮設防犯カメラをレンタル設置するサービスを提供している例もあります。こうした対策により、セキュリティリスクを最小限に抑えつつ工事を進めます。
5.適切な予算管理とコスト削減の工夫
インターホン交換工事にかかる費用を適切に管理し、可能な限りコストダウンの工夫を行うことも成功には欠かせません。マンションの長期修繕計画に沿って資金を準備しつつ、無駄な出費を省いて経済的な負担を最小限に抑えましょう。
マンションのインターホン更新工事費用は、規模や仕様によって変動しますが1戸あたり約10万~18万円前後が一般的な範囲です。50戸規模で総額500万~900万円程度と見込まれる大きな支出です。この費用は多くの場合修繕積立金から拠出され、計画的に準備しておくことで各戸の臨時負担を避けられます。反面、計画不足で急な機器故障が頻発すると、応急修理や早急な全交換が必要になり割高な緊急対応費が発生しかねません。そこで、適切な時期に計画的な更新を行い、なおかつ複数業者への相見積もり取得や仕様の精査によってコストを抑える努力が重要になります。
インターホン更新は築15年前後で計画的に実施するのが望ましく、そうすることで故障頻発による緊急修理費用の増大を避けられます。また、実際に多くのマンションで修繕積立金を活用してインターホン更新費用を賄っており、あらかじめ積立計画に織り込んでおくことで住民の負担感を和らげている例が多いです。
費用削減の工夫としては、第3ポイントで述べたように相見積もりで適正価格を追求することが挙げられ、管理会社任せにせず複数社を競合させた結果、品質を落とさずに30~50%ものコストダウンに成功したケースもあります。
予算管理とコスト削減に関して押さえておきたいポイントをまとめます。
長期修繕計画への組み込み
インターホン更新時期と概算費用を長期修繕計画に盛り込み、毎月積み立てる修繕積立金で賄えるよう調整します。仮に積立金が不足する場合でも、前もって把握していれば一時金徴収や管理組合の修繕積立金貸付制度利用など検討する時間が確保できます。計画的な資金準備が肝心です。
適切な時期での更新
寿命を過ぎ老朽化した設備をだましだまし使い続けると、故障のたびに修理費がかさみ結果的に割高になる恐れがあります。故障が多くなり始める前に計画的に更新することで、余計な維持費支出を抑える効果があります。メーカーの部品保有期間(通常製品生産終了後7年)を念頭に、交換のタイミングを見極めましょう。
コストダウンの工夫
複数見積もりによる競争原理の活用、機能の取捨選択による仕様最適化、既存配線の再利用で工事簡略化などでコスト削減を図ります。加えて、自治体によっては防犯設備の導入に対する助成金制度がある場合もありますので(主に防犯カメラ設置などが対象)、マンションに該当する補助がないか調べてみる価値もあります。
見積もり評価の徹底
単に金額の安さだけでなく、見積もり内容の妥当性・包括性を評価します。安価な見積もりでも必要な機器が含まれていなかったり、後で追加費用が発生するようでは意味がありません。工事範囲や支払条件、保証内容まで含め総合的に見積もりを比較検討し、最良のコストパフォーマンスとなる提案を採用しましょう。
まとめ:適切な見積もり評価を実行しよう
中古マンションのインターホン交換工事を成功させるには、綿密な計画と住民合意、的確な機器選定、信頼できる業者の採用、周到な工程調整、そして予算管理とコスト意識が欠かせません。
とりわけ管理組合として肝に銘じたいのは、複数の情報源から見積もりや知見を集めて適切に評価する姿勢です。経験豊富な専門家の助言や公的機関の情報を参考にしながら、提示された見積もり金額だけでなく内容・条件まで細部を確認し納得した上で契約判断を行うことが、後悔しない工事につながります。
インターホンは日々の安心・安全な暮らしを支える重要インフラです。適切な時期に適切な方法で更新工事を行い、マンションのセキュリティと利便性を高めることは、そこに暮らす全ての人に大きな価値をもたらします。
管理組合と居住者が一丸となって計画を成功させ、快適で安全な住環境の維持を実現しましょう。本記事で挙げたポイントを参考に、ぜひ適切な見積もり評価と賢明な意思決定を実行してください。そうすれば、費用面でも施工面でも納得のいく形でインターホン交換工事を成し遂げることができるはずです。皆様のマンションでのプロジェクトの成功をお祈りしています。
インターホン等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- インターホンのリニューアル工事の支援実績は多数(過去半年で数千戸分、2025年1月現在)。数百戸の多棟型マンションでの実績も複数。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。インターホンのメーカー系のを含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
佐藤 龍太
不動産会社および管理会社にて、マンションやビルの修繕・管理業務に長年従事。マネージャー職を歴任し、これまでに300件近い修繕工事に携わる。特にインターホン設備においては、年間3,000戸以上(2025年現在)の見積取得を行うなど、設備改修の実務に精通。豊富な現場経験と管理業務の知見を活かし、マンション修繕に関する実践的かつ専門的な視点で記事を監修。
こちらもおすすめ
24時間対応通話料・相談料 無料