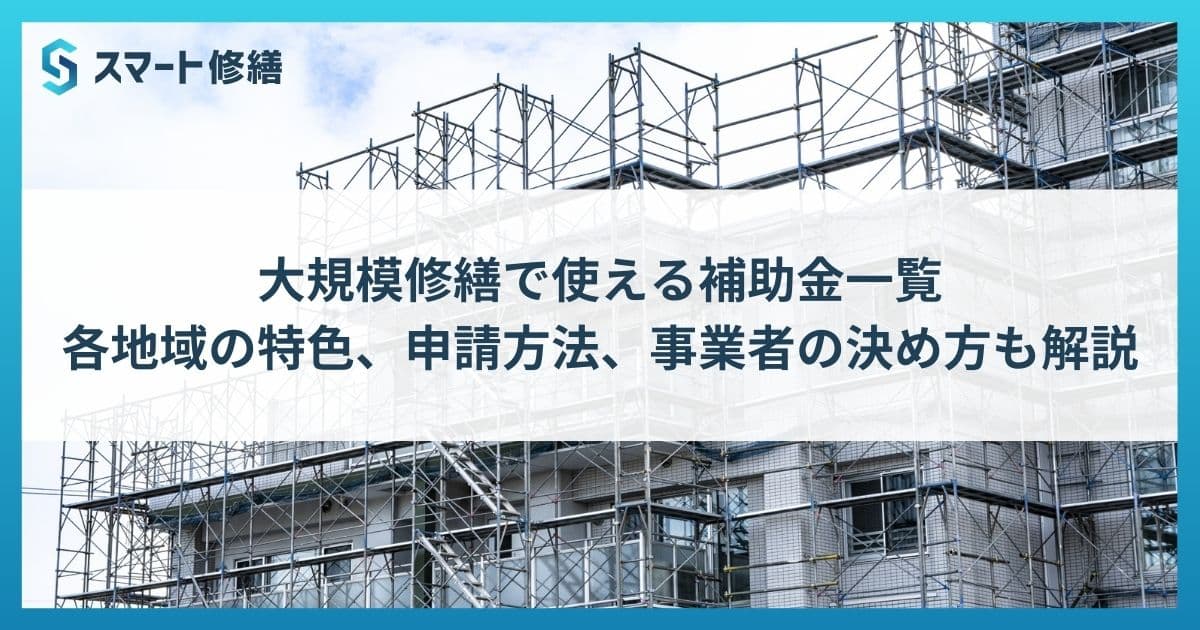分譲マンションのサッシ交換ガイド:なぜ必要?費用・手続き・成功のポイントを解説
更新日:2025年09月17日(水)
分譲マンションで窓枠(サッシ)の交換を検討する管理組合や区分所有者の方向けに、サッシ交換が必要になる理由から工事の進め方、費用相場、管理規約上のポイント、さらに補助金制度やトラブル対策について解説します。 マンションのサッシは共用部分に該当し勝手な交換ができないため、適切な合意形成と計画立案が欠かせません。本記事を参考に、快適で省エネ性能の高い住環境づくりにお役立てください。
- 本記事のポイント
- 経年劣化による不具合や性能低下が、居住者の快適性や健康に直結する問題であることを理解できる。
- サッシは共用部分に該当し、個人の判断で勝手に交換できないため、管理組合としての適切な合意形成が重要であることを学べる。
- サッシ交換にかかる費用相場や工期の目安、国や自治体の補助金制度を活用する方法がわかる。
分譲マンションでサッシ交換が必要になる理由
長年使用したマンションの窓サッシには、さまざまな不具合や性能低下が生じます。経年劣化により窓の開閉がスムーズにできなくなる、サッシ枠の歪みや摩耗で隙間風が入るといった問題は典型的です。
エアコンをつけても部屋が暖まりにくい・冷えにくい、窓ガラスの結露でカビが発生しやすい、外部の騒音が気になる、クレセント錠(カギ部分)が劣化して施錠しづらい、など築年数とともに悩みが増えてきます。これらは居住者の快適性や健康にも直結する問題です。
古いサッシを高性能な新品に交換することで得られるメリットも大きいです。気密性・断熱性の高い最新のサッシに更新すれば、室内の冷暖房効率が向上し、電気代の削減につながります。冬の冷気や夏の熱気の侵入を防ぎ、室内温度が安定するため、一年中快適に過ごせます。
さらに、結露の発生が抑えられ、窓周りのカビ・ダニ発生リスクも軽減されます。遮音性が向上すれば外部の騒音ストレスも緩和され、防犯性能も高まります。サッシ交換はマンション全体の寿命延伸や住民の快適性向上に直結する、重要な改修工事と言えるでしょう。
サッシは共用部!管理規約上の制約と合意形成のポイント
マンションの窓サッシは区分所有者の専有部分ではなく、共用部分扱いとなるのが一般的です。そのため、個人の判断で勝手に交換することは基本的にできません。サッシ交換を行うには、管理組合として他の共用部修繕と同様に総会での決議を経る必要があります。管理規約や使用細則に明記がある場合のみ、一定条件下で個人負担による交換が認められるケースもあります。まずは管理規約や細則を確認し、理事会や管理会社に相談しましょう。
区分所有者による個別交換のポイント
国土交通省のマンション標準管理規約(2004年改正、2011年省エネ改訂)では、管理組合がすぐに実施できない場合、各区分所有者の責任で窓まわりの改良工事が可能と規定。
標準管理規約22条では、理事長への事前申請と書面承認を条件に、個人による窓サッシ交換を許可。
個別交換でも、メーカーや型番の指定、工事仕様の確認など、管理組合の統一ルールの遵守が必要。
マンション全体での交換に必要な合意形成
長期修繕計画に組み込まれていない場合は、理事会で必要性を検討し、専門家の意見や概算費用を収集。
総会で議案として提起する際、住民に対して交換のメリットや緊急性を丁寧に説明。
光熱費削減効果、工事期間中の生活影響、騒音対策などを資料で示すと理解が得やすい。
必要に応じて専門家説明会を開催し、質疑応答の場を設けるのも有効。
こうしたプロセスを経て総会決議(多くのマンションでは特別決議が必要)をクリアすれば、マンション全体で安心して工事に臨むことができます。
サッシ交換工事の流れ(大規模修繕時・住民提案時の進め方)
マンションでのサッシ交換は、大規模修繕工事に合わせて行う場合と、住民提案による単独実施の場合があります。大筋は同じですが、計画のタイミングが異なります。一般的には築後30~40年程度の第3回目大規模修繕で全戸一斉に交換するのが望ましいとされます。
大規模修繕と同時施工のメリット
工事調整を一本化できる
総会決議などの手続きを一度で済ませられる
別々に工事するより日常生活への影響が少ない
計画外で住民提案が出た場合でも、基本的な流れは同様です。
現状把握と計画立案
サッシ不具合や住民の要望を理事会で確認
長期修繕計画で交換予定の有無・時期を把握
必要に応じて専門家(マンション管理士・建築士)に相談
概算費用、工法、補助金活用の可能性を情報収集
管理組合内での合意形成
理事会で基本方針を決定し、組合員に提案
総会または臨時総会で議案を上程し決議
交換メリット、費用負担、工事内容、工事期間中の生活影響を説明
質疑応答の場を設け、住民理解を促進
管理規約で特別決議が必要な場合は、事前の根回しも重要
業者選定・発注方式の決定
複数業者から相見積もりを取得
工事内容・価格・工法(カバー工法など)を比較検討
必要に応じてコンサルタントや専門家の支援を活用
見積もり内容に不明点があれば精査
工事準備と日程調整
業者と契約後、詳細な工事計画を策定
各住戸ごとの工事日程を調整
居住者への連絡と協力依頼
留守宅や賃貸住戸の鍵手配や後日工事対応の取り決め
協力が得られない住戸は、将来自費での対応を想定
工事施工・引き渡し
管理組合・管理会社と施工業者が連携し、進捗・品質を管理
カバー工法では1住戸あたり半日~1日程度で施工完了
全戸施工は数週間~数か月
騒音・立入への配慮、作業時間帯制限、養生措置を実施
全戸交換後、窓の動作確認・気密検査を実施
問題がなければ引き渡し、保証書・メンテナンス案内を受け取って完了
サッシ交換の費用相場(1戸あたり・1棟あたり)と工期の目安
マンションのサッシ交換にかかる費用相場は、サッシの大きさや種類、戸数、工法によって大きく変動します。
一般的なマンションで標準的なサイズの窓サッシ交換を行う場合、1戸あたり30~80万円程度が目安です。金額に幅があるのは、各住戸の窓数・大きさ、採用するサッシの素材(アルミか樹脂か等)やガラスの種類(単板ガラスか複層ガラスか)によって費用が大きく異なるためです。
例えば高さ約180cmの掃き出し窓(ベランダに面した大窓)なら1窓あたり約20万円前後、高さ約90cm程度の腰高窓なら1窓あたり12~15万円前後が一つの目安となります(いずれも複層ガラス仕様の場合の概算)。居室の間取りによりますが、リビングの大窓+各部屋の腰高窓という組み合わせで1住戸あたり合計50~70万円前後が目安です。玄関ドアも同時に断熱タイプへ交換する場合は別途1戸あたり25~30万円程度かかります。断熱性・気密性向上の観点では窓と玄関ドアをセットで交換することが望ましく、予算に余裕があれば同時施工がおすすめです。
一方、マンション全体で見た1棟あたりの総工事費は戸数に応じて算出されます。例えば50戸規模で各戸50万円なら約2,500万円、100戸規模で各戸70万円なら7,000万円前後といった具合です。高層階が多い大規模マンションになると対象サッシも増えるため、億単位の工事費となることもあります。大規模修繕の積立金で賄えない場合は、一時金徴収や長期修繕計画の見直し(工事周期を延長して資金を確保するなど)も検討が必要です。
発注方式によってもコストは変わります。設計事務所に仕様書作成を依頼し入札する方法、あらかじめメーカー系の業者に相談して概算見積を取りながら進める方法、施工会社が提案から参加するプロポーザル方式など様々です。修繕積立金という大切な資金を「まっとうな工事」に使うためには、業者選定方法の工夫が重要です。中間マージンを省き適正価格で施工できるよう、複数社からの見積比較や信頼できる第三者の助言を活用しましょう。
工期の目安は工法によって異なります。カバー工法の場合は既存枠を撤去しないため作業時間が短縮でき、1窓あたり約1~2時間程度、1住戸でも半日~1日程度で完了します。一方で枠ごと全て取り外すはつり工法(全撤去工法)の場合は、撤去作業と足場設置が必要になる分時間がかかり、費用がかさむ上に工期も延びがちです。工期短縮とコスト低減の両面で、マンションのサッシ改修にはカバー工法が採用されるケースが多いです。
マンション全体の工事期間としては、たとえば50戸規模なら数週間程度、100戸以上なら1~2か月程度が目安です。もちろん業者の作業体制や同時進行する他工事との兼ね合いで前後しますが、事前にスケジュールを明示して住民に共有し、工期延長のないよう管理することが大切です。
高断熱サッシへの交換で活用できる国・自治体の補助金制度
近年、住宅の省エネルギー化や断熱改修を支援するため、国や自治体による補助金・助成金制度が充実しています。マンションの窓サッシ交換は断熱性能向上に直結する改修であることから、該当する補助制度を上手に活用すれば工事費の負担を大幅に軽減できます。具体的に2025年前後で利用可能な主な制度として、以下のようなものがあります。
先進的窓リノベ事業(環境省)
高性能な断熱窓への改修を支援する国の大型補助金制度。マンションの場合は管理組合経由で申請可能で、全戸の窓断熱改修に対して補助が受けられます。一定の省エネ性能を満たす窓への交換が条件となり、採択されれば工事費の相当割合(数割程度)の補助金が交付されます。
子育てグリーン住宅支援事業(国土交通省)
元々は子育て世帯向けの住宅支援策ですが、2025年現在リフォームにも対象が拡大されており、マンションの窓・ドア断熱改修も補助対象になっています。子育て世帯でなくても断熱リフォームなら申請可能で、こちらも管理組合でまとめて申請できます。
既存住宅の断熱リフォーム支援事業(環境省)
既存住宅全般の断熱改修支援策で、窓の断熱性能向上工事に補助金が出ます。上記「窓リノベ事業」と併用できるケースもあり、組み合わせることで更なる補助額アップが期待できます。
自治体の断熱リフォーム助成金
東京都や各地方自治体でも、住宅の省エネリフォーム助成を独自に行っている場合があります。窓の二重サッシ化や高断熱サッシ交換は代表的な補助対象工事なので、お住まいの自治体の制度を確認しましょう。自治体によって補助額や条件(世帯所得制限や工事規模要件など)は様々ですが、国の補助金と合わせて利用できる場合もあります。
これら補助金を利用するには事前申請と承認が必要で、多くは工事着手前に申請書類を提出しなければなりません。管理組合として補助金活用を検討する場合は、早い段階で施工業者やコンサルタントに相談し、必要書類(工事計画書や見積書など)を整備して締切までに申請することが重要です。補助金ごとに予算枠や期間があるため、タイミングを逃さない計画づくりがポイントとなります。なお、申請手続きは施工業者が代行してくれるケースも多いので、補助金申請に慣れた業者に依頼するとスムーズでしょう。しっかり活用すれば「思ったより自己負担が少なく高性能なサッシに交換できた!」ということも十分可能です。
サッシ交換工事でよくあるトラブル事例と対策
マンション全体のサッシ交換工事は大掛かりなプロジェクトであり、事前に注意点を押さえておかないと思わぬトラブルに発展することがあります。ここでは起こりがちなトラブルと対策をいくつか挙げます。
工期が予定より延びてしまうトラブル
「工事が当初の予定より長引き、日程変更が相次いで住民から不満が噴出した」という事例があります。対策として、契約時に工期厳守の取り決めを交わし、施工業者と十分に工程を詰めておくことが重要です。工事中も進捗を定期的に確認し、遅延の兆候があれば早期に対処しましょう。また、進行状況をこまめに居住者へ共有することで不安を和らげる効果もあります。
製品不良による施工不良
「交換後に窓から雨漏りが発生した」といったケースも報告されています。これを避けるには、工事前の現地調査(実測)を徹底し、既存枠の寸法や建物の歪みを正確に把握しておくことが大切で。また実績あるメーカーの商品を選び、施工後には必ず性能確認試験(散水試験など)を行って問題がないかチェックしましょう。万一不具合が見つかった場合に迅速に対処・補修できるよう、アフターサービスが手厚い業者を選定することもポイントです。
一部住戸が非協力的で工事が進まない
マンションによっては、居住者が高齢で立ち会いが難しかったり、賃貸に出しているオーナーが連絡不通だったりして、特定の住戸だけ交換工事ができない事態も起こり得ます。このような場合、管理組合として事前に対策を講じておきましょう。反対意見のある所有者には「将来的に不具合が発生しても自己負担で交換する」旨の了承を得る覚書を交わす、賃貸住戸のオーナーには代理人や管理会社を通じて鍵を預かる手配を依頼するなどの対応が考えられます。また工事日程の通知は早めに行い、在宅が難しい場合の代替措置(予備日の設定等)も示しておくと親切です。
住民間のトラブル・クレーム
工事中の騒音・振動への苦情や、共用部のエレベーター使用による不満など生活面のストレスからトラブルになる例もあります。対策として、工事開始前に「作業時間帯は〇時~〇時まで」「騒音作業日はこの日とこの日」など具体的に通知し、理解を求めます。可能であれば騒音の大きい作業は時間帯を限定する、エレベーター養生を徹底し作業員にはマナー教育をする、といった配慮を施工業者と共有しましょう。また、交換後に「うちだけ思ったほど効果を感じない」等の不満が出ることもありますが、これは部屋の位置や気密性向上による換気不足など原因が様々です。必要に応じ各戸で換気扇の使用や調整措置を案内し、きめ細かくフォローすることも大切です。
以上のように、事前準備とコミュニケーション次第で多くのトラブルは防げます。管理組合と施工業者が協力し、綿密な計画とチェックリストに基づいて工事を進めることで、円滑で満足度の高いサッシ交換を実現しましょう。
第三者支援サービスの活用でスマートに修繕を進める
マンションのサッシ交換など大規模改修は、管理組合だけで計画・実施するのは簡単ではありません。専門知識を持つ第三者のサポートを活用することで、工事内容や費用の適正性を確認しつつ、スムーズに進められます。
「スマート修繕」では、一級建築士事務所の専門家が管理組合に伴走し、以下のような支援を提供します。
見積取得や内容の精査、施工業者選定のアドバイス
工事内容・仕様のチェック
補助金活用手続きのサポート
住民説明会での質疑応答支援など
例えば、約450戸の大型マンションで玄関ドアとサッシをハンズフリーキー対応に交換した際には、約2,000万円の補助金を活用することができました。専門家の知見を活用することで、こうした費用面のメリットも最大限に引き出せます。
さらに、審査済みの信頼できる施工業者の紹介や、工事完成保証など、アフターケア面でも安心のサポートが受けられるのも特長です。相談や見積支援は無料で利用できるため、安心して利用できます。
マンションの価値向上と快適な住環境を守るために、サッシ交換は避けて通れない重要な修繕です。計画的に進め、利用可能な制度を活用しながら、専門家とともに賢く安全な修繕を実現しましょう。
まずは「スマート修繕」に相談して、あなたのマンションに最適な修繕プランを確認してみませんか?
お問い合わせ件数、数千組合様以上!
修繕のプロにぜひお任せください!!

Webから無料相談
専門家に相談する
ドア/サッシ等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- 玄関ドア、サッシ等の金物の支援実績は多数あります。約450戸 多棟型マンションでのハンスフリー/非接触キーのドアへの交換(補助金≒2千万円活用)実績もあります。社内にはゼネコン、修繕会社や修繕コンサルティング会社など出身の建築士等が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。ドア/サッシメーカー系を含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)