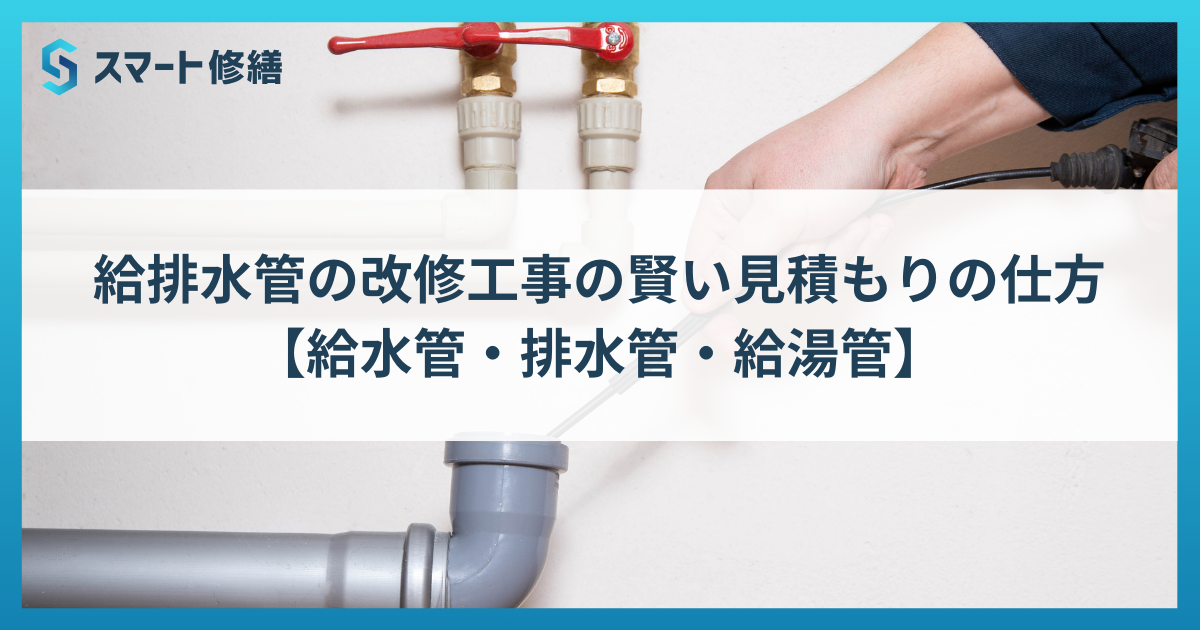マンションの水道管交換工事の進め方 |気になる費用と業者の選び方も紹介
更新日:2025年04月30日(水)
マンションでは建物の老朽化に伴い、給水管や排水管など水道管(配管)の交換工事がいずれ必要になります。管理組合としては、「いつ頃どのように水道管を交換すべきか」「費用はいくらかかるのか」「どんな業者に依頼すれば良いのか」といった疑問が生じるでしょう。 特に築年数が経過したマンションでは、赤茶色の水(赤水)の発生や漏水事故など、水道管の劣化によるトラブルが顕在化するケースも増えます。こうした事態に備え、適切な時期に計画的な水道管の交換工事を行うことが重要です。 本記事では、マンション管理組合向けに、水道管交換工事の基礎知識から工事の進め方、費用相場、業者選定のポイント、工事中・完了後の注意点まで詳しく解説します。最後にはマンションの大規模修繕に関する専門家に相談する必要性についても触れますので、ぜひ参考にしてください。
- 本記事のポイント
- マンションの給排水管の寿命や劣化のサインを学べる。
- 配管工事の「更新」と「更生」の違いやメリット・デメリットがわかる。
- 工事の進め方や業者選定の具体的ポイントを把握できる。
マンションの水道管交換工事の基礎知識
まず初めに、マンションにおける水道管(配管)交換工事の基礎知識を押さえておきましょう。
ここでは、① 給水管・給湯管・排水管それぞれの役割と種類、② 配管の寿命と交換のタイミング、③「更新工事」と「更生工事」の違いという3つのポイントについて説明します。
給水管・給湯管・排水管の役割と種類
マンションには主に「給水管」「給湯管」「排水管」の3種類の配管があり、それぞれ役割が異なるだけでなく使用される材質にも種類があります。適切な材質を用い定期的にメンテナンスすることで、配管の寿命を延ばしトラブルを防止できます。
給水管・給湯管・排水管は建物のライフラインを支える重要な設備です。公的機関のガイドラインでも、近年の新築マンションでは腐食しにくい材質(ステンレス管や合成樹脂製のプラスチック管など)が多く使われるようになっており、これにより配管内部の錆腐食を抑えて寿命を延ばせるとされています。逆に、古いマンションでは従来型の亜鉛メッキ鋼管(鉄製の配管)を使用していることが多く、経年で内部腐食しやすい傾向があります。
国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」でも、共用部の給水管や排水管は内部が腐食するため、一定期間ごとに洗浄・研磨してコーティングをやり直す“更生工事”か、配管自体を新品に取り替える“更新(取替え)工事”が必要になると明記されています。また同ガイドラインには、ステンレス管やプラスチック管等の腐食しにくい材料の採用によって更生工事の必要性が低下し、取替え工事の時期を遅らせることができる傾向にあるとも記されています。つまり材質によって配管の耐久性が変わるのです。
マンションの給水管とは、上水(飲用水)を各住戸に届けるための配管です。一般的に水道本管や受水槽からポンプで給水し、各階・各戸へと水を供給します。
給湯管は各住戸でお湯を使えるようにする配管で、ガス給湯器やボイラー、中央給湯設備等から各所の給湯栓(お風呂やキッチンの湯沸かし)にお湯を送ります。給湯管はお湯を通す分だけ給水管よりも高温による負荷がかかるため、耐熱性・耐腐食性の高い材質(銅管や架橋ポリエチレン管など)が使われます。
排水管は各住戸や共用部分の水回り(キッチン・洗面・浴室・トイレ等)から出る排水を集めて建物外へ流す配管です。排水には生活排水(雑排水)と汚物を含む汚水がありますが、マンションではしばしば用途に応じて雑排水管と汚水管を分け、それらが合流して下水道に接続されています。排水管の材質も耐腐食性を考慮した塩化ビニル管や鋳鉄管などが用いられます。要するに、給水管・給湯管・排水管はそれぞれ役割に適した材質で作られており、これら配管が正常に機能することでマンションの水まわり環境が維持されているのです。
配管の寿命と交換が必要なタイミング
マンションの給排水配管にはおおよその寿命(耐用年数)があり、一般的には築20年前後で劣化が進行し始め、築30~40年までに交換が必要になるケースが多いとされています。ただし材質や管理状況によって差があり、早期に更生工事で延命措置を行うことで交換時期を遅らせることも可能です。
国土交通省が公表している長期修繕計画作成ガイドラインでは、マンション共用部の給水管・排水管の修繕サイクルについて「19~23年目頃に更生工事、30~40年目頃に更新(取替)工事」を実施することがモデルケースとして示されています。これは多くのマンションで、築20年前後になると内部腐食や漏水リスクが高まるため一度ライニング(内面コーティング)等で補修し、さらに築30年以上経過した段階で配管そのものを新しいものに更新するのが望ましい、という考えに基づきます。
前述のガイドラインには、屋内外の共用給水管は19~23年で更生、30~40年で取替、および排水管も19~23年で更生、30~40年で取替と明確に記載されています。例えば、共用部の給水管について「19~23年目に内面更生を行い、30~40年目頃に配管の取替えを実施」といった周期がモデルケースとして提示されています。同様に排水管もほぼ同じ周期で、必要に応じて交換する計画となっています。このように、公的な基準からも30年程度が給排水管更新の目安と読み取れます。
配管交換の適切なタイミングは上記のような年数的目安に加え、実際の劣化症状によって判断されます。具体的には、給水管であれば蛇口から赤茶色の水(赤水)が出る、流水の勢いが弱くなる、ピンホールと呼ばれる微小な穴あき腐食による漏水が発生する、といった症状が現れたら注意信号です。排水管であれば、排水管内部に錆や汚れが付着して流れが悪くなり頻繁に詰まりが起こる、悪臭や虫の発生、あるいは階下への漏水事故(排水管からの水漏れ)が発生するといった事例が見られます。
こうした兆候が出始める築年数は建物により様々ですが、一般に築20年を超える頃から劣化が顕在化し始め、30年を超えるとトラブル件数が大きく増える傾向があります。もし築20~30年を迎えるマンションで上記のような問題が発生している場合、早めに配管更新(または更生)の検討を開始することが重要です。逆に、新築後まだ10年程度しか経っていない場合は通常大きな劣化は生じませんが、管理組合として長期修繕計画において将来的な給排水管更新の時期と費用を見込んでおくことが大切です。
更新工事と更生工事の違い
更新工事とは老朽化した配管そのものを新しい管に取り替える工事であり、根本的な更新策です。
一方、配管更生工事とは既存の古い配管を撤去せずに内部清掃・補修を行い内側に樹脂などでコーティング(ライニング)して延命する工事を指します。
それぞれメリット・デメリットがあり、マンションの状況に応じて適切な工法を選択する必要があります。
前述の国交省ガイドラインにも示されている通り、給排水管の維持管理には更生工事(ライニング工事)か更新工事(交換工事)のいずれかが必要になります。更生工事は配管内部の錆や付着物を除去し、防食塗料や樹脂ライニングで内面を再コーティングする方法で、配管を取り替えず寿命を延ばせる点が特長です。
一方、更新工事は劣化した配管を撤去し、新品の配管に取り替える方法で、根本的に配管を一新できる修繕積立金ガイドラインの記述では、「配管内部が腐食することから、これらを洗浄・研磨し、再度コーティングする“更生工事”や、“更新工事”が必要」と明示されています。
更生工事では配管をそのまま活かすため廃材が少なく工期も短めになる利点がありますが、既存配管の状態が悪いと施工できない場合や、更生後もいずれ交換が必要になるため根本的解決にはならないという制約もあります。
一方、更新工事は確実に新しい配管に切り替えるため長期的な安心感がありますが、壁や床を開口する大掛かりな作業を伴うため居住者への影響(騒音・断水等)や工事費用の高さといった課題があります。
マンションの水道管交換工事の進め方
マンションで水道管(給水管・排水管)の交換工事を行う際は、事前調査から計画立案、合意形成、業者選定、施工監理、完了後の確認まで系統立てて進めることが大切です。
具体的には、配管の劣化状況を調べた上で計画を策定し、総会決議などで組合の合意を得てから、信頼できる施工業者を選定・契約します。その後、工事の工程管理や居住者対応を適切に行い、完了後に検査・引渡しを受けるという流れになります。
国土交通省のガイドライン等によれば、マンションの大規模修繕や設備改修工事を成功させるには「事前の建物調査診断」「修繕計画の見直し」「資金計画の確認」「組合内合意」「施工者の適切な選定」「工事監理と住民周知徹底」などのステップを踏むことが重要とされています。給排水管の交換工事も同様に大きな工事の一つであり、場当たり的ではなく計画的な進め方が必要です。
水道管交換工事の一般的な進め方を、順を追って説明します。
Step1: 劣化状況の把握(事前調査)
まずは現在の給水管・排水管の状態を正確に把握します。専門の調査会社や設備業者に依頼して配管劣化診断を実施すると良いでしょう。具体的には、配管の一部を切り取って断面を調べる、ファイバースコープカメラで内部を撮影する、水質検査を行い錆成分の有無を確認する、といった方法で劣化度を評価します。調査結果に基づき、「更生工事で対応可能か」「早急に交換工事が必要か」「あと何年程度猶予がありそうか」といった判断材料を得ます。
Step2: 計画立案と資金確認
調査の結果、例えば「築25年で漏水が発生しており5年以内に交換推奨」となれば、その方針で修繕計画を具体化します。交換範囲(共用部のみか、専有部分の立ち上がり管も含めるか)、工事方式(一斉交換か、系統ごと段階的に行うか)などの方針を検討します。また資金計画も重要です。現在の修繕積立金残高や今後の積立見込みを踏まえ、工事費用を賄えるか確認します。場合によっては国土交通省の指摘のように修繕積立金の増額や一時金徴収、金融機関からの借入れ検討が必要になるかもしれません。
Step3: 組合内の合意形成
修繕委員会や理事会で計画案と資金計画がまとまったら、組合員への周知と合意形成に移ります。区分所有者への説明会を開催し、工事の必要性・内容・費用・スケジュールなどを丁寧に説明します。その上で管理規約に従い総会決議を行います(規約上に特段の定めがなければ、普通決議)。組合員の理解と賛同を得るプロセスを疎かにすると後々トラブルの元になりますので、疑問や不安には真摯に回答し、十分な情報提供とコミュニケーションを図ることが大切です。
Step4: 業者選定と契約
工事実施が組合として正式決定したら、具体的に施工を担う工事業者の選定を行います(詳細は後述の「業者選びのポイント」で解説します)。複数の設備工事会社から提案・見積もりを取り、価格だけでなく施工実績や提案内容を比較検討します。必要に応じて管理会社の意見や、建築コンサルタント等第三者専門家の助言も参考にしましょう。適切な業者が決まったら工事請負契約を結びます。契約書には工事範囲・仕様、金額、工期、支払条件、アフターサービス内容(保証期間等)を盛り込み、管理組合と業者双方で内容を確認します。
Step5: 工事準備と周知
契約後は実際の着工に向けた準備段階です。工事業者は詳細な施工計画を立て、資材や人員の手配、役所への届出(道路占有や給水停止届など必要に応じて)を行います。管理組合側では居住者への周知徹底が重要になります。工事期間や各戸への立ち入り作業日、断水を伴う日時など、生活への影響事項を事前に通知します。掲示板や回覧、メール等あらゆる手段で知らせ、特に高齢者や日中不在世帯にも行き届くよう配慮します。また工事中の問い合わせ窓口を明示し、苦情や要望に迅速に対応できる体制を整えておきます。
Step6: 工事施工と監理
工事期間中、管理組合(理事会)は定期的に進捗報告を受けましょう。外部コンサルタントなどを通じて工事監理(工程・品質・安全のチェック)を行うことが望ましいです。具体的には、図面どおりに新しい配管が設置されているか、継手や接合部は確実か、漏水試験は適切に実施されたか等を専門家の目で確認します。また、居住者から騒音や断水に関する苦情が出た場合の調整役も管理組合の役割です。工事業者とは毎週打合せを行い、問題点や工程変更があれば共有して迅速に対処します。
Step7: 完了検査と引き渡し
工事が終わったら、完了検査を行います。工事業者の社内検査に加え、管理組合側でも立会い検査を実施しましょう。配管からの漏れがないか、水圧は十分か、水質に異常はないか(必要に応じ水質検査)を確認します。共用部の見える範囲だけでなく、天井裏やパイプスペースなど目視できる箇所は全てチェックし、不具合があれば手直しを依頼します。問題がなければ工事引き渡しとなり、新しい配管設備の図面や保証書類一式を受け取ります。最後に工事代金の支払いを契約通りに行い、一連の工事プロセスが完了します。
以上が水道管交換工事の大まかな進め方です。大切なのは、計画段階から完了まで管理組合が主体的に関与し、情報共有と合意形成を丁寧に行うことです。また、必要に応じてマンション管理士や建築設備の専門家にサポートを依頼しながら進めると、より確実でしょう。
マンションの水道管交換工事の費用
水道管の交換工事費用はマンションの規模や工事範囲、工法、業者によって大きく変動しますが、一般的な目安として数百万円から数千万円単位の費用がかかるのが普通です。戸当たりに直すと1戸あたり数十万円程度になるケースが多いですが、状況次第では追加費用も発生し得ます。費用捻出のため、修繕積立金の計画的な積み立てと不足時の対応策を用意しておくことが重要です。
マンションの修繕積立金ガイドラインでは、給排水管の取替え工事費を長期修繕計画に織り込む必要性が指摘されています。これによれば、新築時の計画に配管更新費用が盛り込まれていない場合でも、築後15年以降の見直し時には取替え費用を計上しなければならなくなるとされ、結果として修繕積立金の増額が必要になる可能性があると述べています。
費用は以下のような要因で左右されます。
マンションの規模・構造
戸数や階数が多いほど延べ配管長が長くなり、工事費用は高くなります。またワンフロア当たりの戸数や配管系統の複雑さによっても手間が変わります。
工事範囲
共用部の竪管・横枝管だけ交換する場合と、各住戸内の分岐配管(専有部分の一部)まで交換する場合では、後者の方が戸内工事が増える分コストアップします。専有部分の工事費は基本的に各所有者の負担ですが、実際には一括して組合が発注し負担配分することも多いです。
工法
更生工事で対応できる場合は更新工事より費用を抑えられます。一方、老朽管を撤去して新設する場合は人件費・材料費ともに高くつきます。ただし更生工事を行った後に結局追加で更新工事が必要になると二重の費用がかかるため、長期的視点で判断が必要です。
並行工事
他の大規模修繕(外壁や屋上防水工事など)と同時に実施する場合、仮設足場や工事管理費用を按分できるため単独で配管工事を行うより割安になることがあります。逆に単体工事だと諸経費が割高になりがちです。
地域差
工事費単価は地域の物価水準によっても異なります。都市部では人件費・資材費が高く、地方都市に比べて費用が高めになる傾向があります。
予備費・リスク要因
工事を開けてみないと分からないリスクにも備えます。例えば床下の腐食が酷く補修が必要になった、想定外の箇所から漏水が見つかった等で追加工事が発生すると、その分費用が上乗せされます。見積もりには通常数%程度の予備費を含めますが、それを超える事態もゼロではないため、余裕を持った資金計画が求められます。
業者選びのポイント
水道管交換工事の成否は業者選びに大きく左右されます。
ポイントは、①複数社から見積もりを取得して比較検討すること、②マンションの給排水設備工事の実績が豊富で信頼できる業者を選ぶこと、③提案内容やアフターケアも含めて総合的に判断することです。加えて、管理組合だけで判断が難しい場合は第三者の専門家にアドバイスを求めると安心です。
大規模修繕工事に関する国交省やマンション管理センターの資料でも、工事発注者である管理組合が価格・内容ともに適正な業者を選定する重要性が繰り返し述べられています。
また、トラブル事例として「相見積もりを取らず1社に絞った結果、相場とかけ離れた高額工事となった」「安易に選んだ業者の施工不良で再工事が必要になった」といったケースも報告されています。そうしたリスクを避けるためにも、慎重な業者選定プロセスが求められます。
業者選びの際にチェックすべき具体的なポイントを以下にまとめます。
実績・経験
候補業者がマンションの給排水管更新工事の実績をどれだけ持っているか確認しましょう。戸建住宅や公共施設の工事実績しかない業者よりも、マンション特有の構造や住民対応に慣れた業者の方が安心です。過去に類似規模・構造のマンションで何件の配管更新を手掛けたか、成功事例はどうか、といった点をヒアリングします。信頼できる業者であれば実績一覧や施工写真、施主(管理組合)からの評価なども開示してくれるでしょう。
資格・許可
水道管工事には管工事業の建設業許可や、水道事業者からの給水装置工事主任技術者などの資格が必要です。適切な許可・資格を有する会社であることは大前提となります。また工事規模によっては一級管工事施工管理技士など高度な資格保持者の在籍も望ましいです。さらにマンションの場合、居住者とのコミュニケーション能力も重要ですので、現場代理人や担当者の人柄・対応力もチェックポイントです。
提案内容
単に見積金額だけでなく、提案内容の質も比較しましょう。たとえば配管経路の計画(できるだけ居住者への影響を減らす工夫があるか)、使用する配管材料の種類やグレード、工事工程の妥当性(無理のない工期か、居住者配慮の段取りか)、更生工事併用など代替案の有無、アフターサービス(何年保証か、定期点検はあるか)など、詳細な計画を示してくれる業者は信頼度が高いです。逆に見積書が工事一式の総額しか書かれておらず内訳が不明確な業者や、質問に対する回答があいまいな業者は要注意です。
費用の妥当性
提案・見積の内容を精査し、費用が妥当か判断します。他社比較はもちろん、可能であれば第三者の専門家(建築設備に詳しいコンサルタントやマンション管理士等)に見積内容をチェックしてもらうのも有効です。相場とかけ離れて高すぎないか、逆に安すぎて手抜きや後から追加請求の恐れはないか、しっかり見極めます。工事項目ごとの単価や数量が適切かを確認し、不明な点は遠慮なく質問しましょう。修繕積立金ガイドラインにもあるように、マンションの条件次第で工事費には幅がありますので、自分たちのマンションに合った適正価格を掴むことが肝心です。
契約条件
最終的に契約する際には、契約条件もチェックします。工期の遅延時ペナルティや追加工事の扱い、支払いスケジュール、瑕疵担保(保証)の範囲などを確認しておきます。トラブル防止のため口頭ではなく書面で取り決めましょう。信頼できる業者ほど契約内容も明瞭で誠実です。
工事中および完了後の注意点
水道管交換工事の工事中は、居住者の生活への影響に十分配慮し、安全かつ円滑に工事が進むよう管理組合が注意を払う必要があります。また工事完了後は、新しい配管の試運転や検査を行い、問題がないことを確認してから引き渡しを受けます。さらに、工事後もしばらくは注意深く様子を見守り、何か不具合があれば早めに対処することが大切です。
〈工事期間中の注意点〉
断水のスケジュール管理
水道管工事では古い配管から新しい配管へ接続切替を行う際などに一時的に断水が発生します。断水時間帯は可能な限り短く設定し(通常日中の数時間程度で済むよう計画)、その日時を事前に全住戸へ周知します。断水に備えてポリタンク等に水を汲み置きしてもらうよう依頼したり、工事業者が仮設の給水栓(応急用の水タンク)を用意することもあります。断水作業は日程の変更が起きないよう綿密に段取りし、万一予定時間を超過しそうな場合は早めに居住者へ連絡を入れるなど柔軟な対応を取ります。
騒音・振動と作業時間
壁や床のコア抜き(穴あけ)作業などではどうしても騒音・振動が発生します。工事可能時間帯は管理規約や条例で定められていますが、常識的にも早朝・深夜は避け、平日昼間のみに限定するのが基本です。日中在宅している方(在宅勤務者や高齢者等)への配慮として、特に音の大きい作業日は事前告知し理解を得るよう努めます。騒音計を用いて近隣への影響をチェックするなど、業者と協力して苦情防止策を講じます。
塵埃対策と養生
配管交換では天井裏や壁内の作業に伴い、ホコリや粉塵が発生します。共有廊下やエントランスには養生シートを敷設し、作業後は毎回清掃するよう徹底します。各住戸内での作業時も、作業箇所周囲の家具家財をビニールシートで覆うなど丁寧な養生を行い、住民の大切な財産を汚損しないよう注意します。養生や清掃が不十分だと住民トラブルにつながりやすいため、理事会から業者へ厳守を求めましょう。
安全管理
工事関係者の出入りも多くなるため、防犯・安全面の配慮も必要です。資材置き場や作業エリアには関係者以外立入禁止表示をし、誤って子供が近づかないよう注意します。また工事用仮設材(脚立や工具)が倒れてケガをしないよう適切に管理します。万一に備え、工事関係者には労災保険加入や第三者賠償保険への加入を確認しておくと安心です。
コミュニケーション
工事中は何かと住民からの問い合わせ・苦情が発生しがちです。例えば「○号室で水漏れが起きている」「工事の音がうるさい」「作業員のマナーが悪い」等です。これらに迅速に対応するため、現場責任者と管理組合の連絡体制を明確にし、トラブル発生時はすぐ協議して解決策を取ります。定期的に工事ニュースなどを発行し、「今週はここまで進みました。ご協力ありがとうございます。来週は○○作業を予定しています」といった情報発信をするのも有効です。住民の不安や不満をこまめに吸い上げ、真摯に対応することで、工事を円滑に進めることができます。
〈工事完了後の注意点〉
試運転と検査
新しい配管へ切替が完了したら、給水・排水設備の試運転を行い正常に機能するか確認します。全ての蛇口から水を出してみて、水圧や水量に問題がないか、濁り水が出ないかをチェックします。施工箇所から漏水がないか再度目視点検し、排水テスト(水を大量に流して詰まりや漏れがないかの確認)も行います。これらは業者任せにせず、理事や専門委員も立ち会って確認しましょう。場合によっては第三者検査を依頼することも検討します。
水質の確認
新設した配管から最初に水を通すと、わずかな油分や不純物が混じる可能性があります。工事完了直後は各戸でしばらく水を流し続けて(フラッシング)、配管内を十分洗浄します。その後、水の色や臭いに異常がないか、必要に応じて水質検査を行うと安心です。給湯配管の場合も同様にお湯を出して内部をすすぎ、適正温度で供給できるか確認します。
工事記録の受領
工事完了後には、業者から工事記録書類一式を受け取ります。新しい配管の図面(竣工図)や仕様書、使用した機材・材料のメーカー保証書、工事写真、検査成績書、そして保証期間や連絡先を記載した書面などです。これらは今後の維持管理に重要な資料となりますので、きちんとファイリングして管理しておきます。特に配管の配置図は、将来修理やリフォームの際に役立ちます。
保証とアフターケア
通常、給排水管更新工事には何年間かの保証期間が付きます。例えば「引き渡し後2年間は施工不良箇所の無償補修保証」など契約書に定めがあるはずです。保証期間中に万一トラブル(漏水や配管の不具合)が発生した場合は、速やかに施工業者に連絡し無償対応してもらいます。また保証期間後であっても、明らかな施工ミスが原因の不具合であれば業者と交渉して対応を求めることも可能です。いずれにせよ、工事後もしばらくは注意深く様子を見ることが大切です。定期的にポンプ室やパイプスペースを点検し、水滴や異臭がないか確認すると良いでしょう。
住民への周知
工事が無事完了したこと、協力への感謝、そして新しい配管になったことによるメリット(水圧向上や水質改善等)を組合だより等で住民に報告しましょう。あわせて、しばらくは「水の使い始めに一時的に白濁する場合がありますが問題ありません」など注意事項があれば伝えます。住民にとっても工事の成果を実感し、安心して生活を続けられるよう情報共有することが望ましいです。
まとめ:業者選びを相談できる専門家が必要
マンションの給排水管交換工事は決して安い買い物ではなく、将来のマンションの安心安全に直結する重要な工事です。だからこそ経験豊富な専門家の知恵を借りることは、長い目で見て大きなメリットになります。適切なサポートを受けながら進めることで、管理組合の皆様にとって納得と満足のいく水道管交換工事を実現できるでしょう。
以上、マンションの水道管交換工事について導入からまとめまで詳細に説明しました。計画的な交換工事の実施と的確な業者選定により、マンションの給排水設備は蘇り、今後長期間にわたり安心して生活できる基盤が整います。
管理組合の適切なリーダーシップと専門家の協力のもと、ぜひ貴マンションの水道管更新プロジェクトを成功させてください。
給排水設備等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- 給排水工事では、専有部含め多数、約600戸 多棟型マンションでの実績もあります。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。更新工事/更生工事(含むFRP)それぞれに強みを持つ紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料