マンション給湯器交換時の管理組合対応ガイド
更新日:2025年09月17日(水)
マンションで給湯器の交換を検討する際には、「専有部分か共用部分か?」といった管理規約上の位置づけや、管理組合への届け出の要否など、事前に確認すべきポイントが多くあります。特に管理組合の役員や区分所有者にとって、適切な対応を取ることは住民トラブルの防止や円滑な工事実施に不可欠です。 本記事では「マンション 給湯器交換 管理組合」に関して、トラブル事例と回避策、理想的な管理組合の対応策、費用負担の考え方や近年注目される一括交換の検討まで解説します。
- 本記事のポイント
- 給湯器が専有部分か共用部分かの判断基準と、管理規約に基づく位置づけの重要性を理解できる。
- 給湯器の設置場所や仕様変更、号数アップ、高効率機種への変更など、管理組合の承認が必要な具体的なケースを学べる。
- 無断工事や工事中の事故、美観の問題など、よくあるトラブルとその回避策、管理組合としての理想的な対応方法を把握できる。
給湯器交換は専有部分?共用部分? – 規約上の位置づけと判断基準
まず給湯器(給湯設備)はマンションの専有部分か共用部分かを確認しましょう。一般的に給湯器は、区分所有者の財産であるため居住者自身が費用負担し、交換作業も自身で手配するのが基本です。交換前にマンション管理規約で機種や工事内容、工事業者が指定されていないか管理会社に確認を取り、必要な申請手続きを取ることが重要です。
たとえ給湯器が共用廊下の壁やバルコニーなど共用部分内に設置されていても、その機器自体は当該住戸専用であれば専有部分とみなされるのが標準的な考え方です。国土交通省のマンション標準管理規約コメントにおいても「給湯器が廊下やベランダに設置されている場合は、共用部分内であるが専用的に使用できるので専有部分と考えられる」と明記されています。
ただし給湯器に付随する一部の配管や構造によっては判断が分かれる場合があります。例えば、各戸の給湯管やガス管のうち、本管と一体となって建物構造内を通る部分は「共用部分」として扱われるケースもあります。管理規約には「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理は共用部分の管理と一体として行う必要があるときは管理組合がこれを行うことができる」との条項があり(標準管理規約第21条2項)、給湯器交換時にもその趣旨を念頭に置く必要があります。とはいえ給湯器本体そのものは基本的に各所有者の財産であり、その維持修繕は所有者の責任で行うのが原則です。
ポイント
自分のマンションの管理規約や付属細則を確認し、「給湯器(ボイラー)」が専有部分として明記されているかをチェックしましょう。多くのマンションでは標準管理規約に準拠し給湯器を専有設備扱いとしていますが、念のため規約の該当箇所を把握しておくことが大切です。
専有部分と位置づけられる以上、給湯器交換にかかる費用は基本的に区分所有者(居住者)の負担となります。共用部分の維持管理費として積み立てた管理費・修繕積立金を専有部分である給湯器の交換に充当することはできません。仮に経年劣化でマンション内の多数の給湯器が一斉に故障した場合でも、各戸それぞれ自己負担で交換するのが原則です。
管理組合としては「なぜ共用の修繕積立金でまとめて交換できないのか?」という疑問の声に備え、専有部分と共用部分の区分と費用負担の原則(区分所有法や管理規約に基づくルール)を住民に丁寧に説明できるようにしておく必要があります。
管理組合の承認が必要となるケース
給湯器交換を行う際に管理組合の事前承認や届出が必要になる場合について整理します。
給湯器は専有部分とはいえ、工事内容や設置状況によっては共用部分に影響を与えることがあるため、多くのマンションで何らかの届け出や許可取得が求められています。
以下に代表的なケースを挙げます。
給湯器が共用部分に設置されている場合
給湯器本体は専有設備ですが、共用廊下の壁面やバルコニーなど共用部分上に取り付けられている場合、その場所は居住者個人の所有物ではありません。したがって交換工事の際に壁面のビス穴をいじる、共用部分で作業を行う、といった「共用部分に変更を加える行為」が伴うため、管理組合(理事会)への届出が必要とされるのです。
実際、分譲マンションでは給湯器交換時に管理組合へ事前申請するケースが多いと指摘されています。賃貸マンションなら大家負担で交換しますが、分譲では自己負担であっても共用部分に手を加える以上、管理組合に知らせ許可を得る必要があるのです。
給湯器の外観や仕様が既存と異なる場合
新しい給湯器のサイズ・形状・色がこれまでのものと大きく変わる場合、マンションの美観や統一性に影響するため注意が必要です。管理規約で色・デザインの指定があるマンションもあります。例えば「外壁が茶系なので給湯器も茶色系で統一」等のルールです。もし色指定があるのに違う色の給湯器を設置すると景観を損ねてしまうため、事前に規約や管理会社へ確認し、必要に応じて管理組合の承認を得るべきです。色指定がある場合はメーカーに特注塗装を依頼する必要があり、その場合納期が1ヶ月程度かかることもあります。したがってデザイン面の条件は早めに確認し遵守することが大切です(管理組合への届出時に機種の色・サイズを報告し承認を受ける形になります)。
給湯能力(号数)を上げる場合
古い給湯器から新しいものへ交換する際に、「せっかくなら能力を高い機種にしたい」と号数アップを検討するケースがあります。しかしマンションでは給湯器の号数アップを禁止または制限している場合が多く、特に能力変更時には届出と承認が求められるのが一般的です。
理由は、給湯能力を上げるとガス消費量や給水量も増え、マンション全体の既存インフラに負荷をかける恐れがあるためです。各戸が勝手に大型化してしまうと、共用のガス配管や給水管で供給不足が生じるリスクがあり、管理組合としても号数アップは禁止もしくは一定容量までに制限するケースが多いのです。
国土交通省のガイドラインでも、共用設備の能力に影響を及ぼす専有部分工事(一定以上の大容量給湯器設置等)は理事会承認を要する工事と位置付けられています。したがって現在と同じ号数以外への変更を希望する場合は、事前に管理組合へ相談・許可取得が必須と言えるでしょう。
高効率機種(エコジョーズ等)への変更
従来型のガス給湯器から、排熱を再利用するエコジョーズタイプに交換する場合も注意点があります。エコジョーズは燃焼効率向上のため燃焼時に水(ドレン水)が発生し排水が必要となります。しかしマンションで給湯器をパイプスペース(PS)内に設置する方式の場合、元々ドレン排水の設備がないことが多く、そのままではエコジョーズを設置できません。バルコニー設置タイプであれば側溝に排水できますが、共用廊下のPS内設置の場合は排水口の新設や排水配管の工夫が必要になります。
このように従来なかった排水経路を新設することは共用部分への工作を伴うため、管理組合への届け出と承認が求められるケースとなります。事前に管理会社や理事会に相談し、技術的に設置可能か含め確認しましょう。場合によってはエコジョーズ化を断念せざるを得ないケースもありますが、無断で特殊な機種に変えて問題が生じると後から撤去指示などトラブルになる可能性があります。
共用部分を加工する必要がある場合
これは当然ですが、交換工事の範囲で外壁や床スラブ等の共用構造部に穴を開けたり削ったりする工事は原則認められません。例えば「配管経路を変えるために外壁やPS扉に新たな穴を開ける」などは、管理規約上理事会の許可以前に禁止事項であることが一般的です。給湯器交換工事だけでこのような大掛かりな加工が発生するケースは稀ですが、もし何らかの事情で共用部改変が避けられない場合は事前に理事会と十分協議し、必要なら総会決議等も経て慎重に検討する必要があります。
給湯器交換時に起こりやすいトラブルとその回避策
給湯器の交換工事にまつわるトラブルは意外と起こりがちです。ここでは管理組合と居住者双方の視点から、起こりやすいトラブル事例とその回避策を紹介します。
無断工事・手続き漏れによるトラブル
管理組合への連絡や承認を怠って工事を進めてしまうケースです。工事音に対する近隣苦情や、事後発覚して理事会から是正要求を受けるなど揉め事に発展しかねません。回避策として、必ず事前に規約を確認し、必要な届出・許可取得を済ませてから工事を行いましょう。また工事日程が決まったら管理人や周囲の住戸へ事前周知する心配りも大切です。「○月○日○時~○時に給湯器交換工事を行います。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。」といった掲示を出すことで、近隣からの理解を得やすくなります。
工事中の事故や不具合
給湯器交換はガス・水道・電気を扱う専門工事です。不適切な施工はガス漏れ・水漏れ等の事故につながり、大惨事になりかねません。過去の震災時には固定不足の給湯器が多数転倒・破損した例もあり、設置工事の質は非常に重要です。回避策として、資格と実績のある専門業者に依頼するのはもちろん、管理組合側でも可能であれば信頼できる業者リストを用意し紹介すると安心です。施工前には業者と十分打ち合わせを行い、ガス栓の閉鎖・開放手順や試運転確認など安全対策を徹底しましょう。工事当日は管理人や理事が立ち会うとベターです。また万一工事に起因して共用部や他住戸に損傷・不具合が生じた場合は、その工事を発注した区分所有者が責任をもって対処するという原則も周知しておきます。事前に「もしもの時の連絡フロー」や業者の損害保険加入状況も確認しておくと良いでしょう。
美観(景観)の問題
交換後の給湯器が周囲と著しく不調和だと苦情の元になります。例えば一戸だけ奇抜な色の給湯器や大きさの異なる機種を取り付けた場合、外観上目立ってしまい「マンションの統一感が損なわれた」と指摘されるかもしれません。回避策として、基本的には既存の給湯器と同じ色・サイズの後継機種を選ぶのが無難です。管理規約で細かな指定がなくても、管理会社から「できるだけ同系色・類似デザインにしてください」とお願いされる場合があります。迷ったら管理組合に事前相談し、建築当初のカタログ色に近いものを選ぶようにしましょう。どうしても後継機がなくサイズ等が変わる場合は、見た目に配慮した設置(必要なら周囲にカバー設置など)を検討します。
騒音・振動の問題
新しい給湯器の仕様によっては運転音や振動が従来より大きくなる可能性があります。特に能力の高い機種ほど燃焼時のファン音が大きかったり、燃焼振動が壁を伝わりやすくなるケースも考えられます。夜間に作動音が響けば近隣トラブルになりかねません。回避策として、号数アップは避け、基本的に既存と同等能力の機種を選定するのが安全です。どうしても高能力機種が必要な場合は、その機種の騒音レベルや振動対策についてメーカーに確認し、防振ゴムをかます等の対策施工を業者に依頼しましょう。また長時間の試運転を要する場合は昼間に行う、給湯器周囲に遮音シートを一時的に貼るなど、近隣への音配慮も怠らないようにします。
排気・換気の問題
ガス給湯器には燃焼排気がありますが、機種変更によって排気方式が変わったり排気量が増えたりすると換気不良のリスクがあります。例えば従来の給湯器は自然排気だったのに、新しい機種は強制排気ファン付きで排気筒経路が変わる、といったケースでは要注意です。排気ダクト径や配置が適切でないと一酸化炭素中毒等の危険も孕みます。また前述したエコジョーズ導入時のドレン水処理も排気に関連する問題です(排気熱を利用する分、水が出るため)。
回避策として、基本的には現在設置中の給湯器と同じ排気方式・設置方式のものを選ぶことが鉄則です。マンションによって設置できる給湯器の種類(例えば「屋外壁掛型」「PS設置型」など)は限られており、それを逸脱した機種は設置できません。業者と現場調査時に適合する機種かどうか、追加の配管工事が必要ないか入念にチェックし、不明点は管理組合経由で建築図面を確認するなど安全第一で進めましょう。排気筒の劣化が見られる場合は併せて交換し、ガス燃焼排気の逆流防止機構が正常に機能するかも点検します。万一交換後に異臭や排気異常を感じたらただちに使用を中止し、専門業者と管理組合に報告してください。
工事による周辺への影響(騒音・振動・通行など)
給湯器交換自体の施工時間は半日程度と長くはありませんが、ドリルでの固定具取り付け音やハンマー作業音など、それなりの騒音・振動が発生します。また共用廊下に脚立を立てたり、一時的に通路を塞ぐ場面もあるでしょう。回避策として、管理組合として工事可能な時間帯や曜日をルール化しておき、例えば「工事作業は平日9~17時まで」「日曜・祝日の作業禁止」などと定めておくことが有効です。実際に多くのマンションでリフォーム細則により作業時間帯の制限が設けられています。居住者側もそのルールを順守し、近隣在宅者への配慮として可能な限り短時間で作業が終わるよう業者と調整しましょう。例えばエレベーター養生など共用部の使用についても事前に管理人と打ち合わせ、作業後は清掃を徹底するよう依頼します。こうした基本的マナーを守ることで、「交換工事のせいでうるさかった」「汚れが放置されていた」等の苦情を未然に防ぐことができます。
管理組合としての理想的な対応
給湯器の個別交換が発生する際、管理組合としてどのように対応するのが望ましいでしょうか。ここでは理事会・管理組合の立場で整えておきたい仕組みやルール作りについて提案します。
工事申請のルール整備と様式の用意
管理組合としては、専有部分の設備工事に関する届け出・承認の制度を明確にしておく必要があります。理事会の決議事項として事前承認が必要な工事範囲を規約や細則に定め、区分所有者に周知しましょう。「給湯器交換程度であれば届出のみで承認不要」など各マンションの実情に応じたルール策定が望ましいとされています。あわせて工事申請書のフォーマットを整備し、必要事項を記入してもらえるようにします。申請書には工事内容(給湯器の型式・号数・色など)や工事日程、施工業者名、連絡先、工事方法の概要などを記載させ、トラブル防止の観点から誓約事項(例:「万一工事により共用部分に不具合が生じた場合は責任を持って復旧します」等)も盛り込むと安心です。こうした様式をあらかじめ用意し、管理事務室や掲示板で「給湯器交換の際は所定の申請書提出を」と周知しておけば、居住者も手順が分かりやすくスムーズに申請できます。
工事ルール(時間帯・業者資格など)の明文化
前述のトラブル対策でも触れましたが、工事可能な時間帯や曜日、作業マナーについて明文化しておくことが重要です。具体的には細則等で「工事作業は平日○時~○時まで。日祝および夜間早朝の工事禁止」「騒音を伴う作業は事前に管理組合へ届け出」などと規定します。また業者選定に関するルールも検討してください。例えば「給湯器交換業者は所定のガス工事資格を有すること」「作業員は管理組合指定の腕章を着用すること」等、安全・安心に直結する事項です。資格については簡易内管施工士やガス消費機器設置工事監督者などが該当しますが、あまり厳格にしすぎると業者選びが大変になるため、現実的に運用できる範囲で定めることが大切です。
さらに「工事中の養生と後片付けを徹底すること」「エレベーター使用時は他の利用者優先とすること」などのマナーも盛り込みましょう。理事会がその気になれば細かいルールはいくらでも考えられますが、肝心なのは居住者全員に周知し徹底することです。総会決議で細則を制定・改正した際は回覧や掲示で告知し、「ルールがあるのに誰も知らなかった」という事態を避けましょう。
管理組合主導での情報提供と業者紹介
給湯器交換は各戸の任意工事とはいえ、管理組合が一定のガイド役割を果たすと理想的です。経年時には「給湯器の点検・交換時期です。希望者に業者紹介できます」と掲示することなどが考えられます。また理事会が主体となり推薦業者のリストを作って配布するのも有効でしょう。
昨今はインターネットで安価な業者を探すことも容易ですが、資格や保証の面で不安も残ります。管理組合があらかじめ数社の見積もりを比較し、適正な業者と提携しておけば、居住者も迷わず依頼でき、トラブルも減らせます。給湯器交換程度でどこまで行うかは判断が分かれますが、「理事会推奨業者制度」があると入居者には心強いものです。さらに工事後のメーカー保証書コピーを管理組合で保管しておくなど、交換履歴を共有する仕組みがあると将来の大規模改修時にも役立つでしょう。
住民への啓発と情報共有
理事会通信や掲示板を活用し、給湯設備の寿命や注意事項を周知することも理想的対応の一つです。例えば「給湯器の寿命は一般に10~15年程度と言われます。故障するとお湯が使えなくなり生活に支障が出ますので、15年以上使用の給湯器は早めの交換を推奨します。」などと呼びかけることで、計画的な交換を促せます。
また前述の工事申請手続きや工事ルールについても定期的に告知し、特に新しく入居した区分所有者には理事会から書面で案内すると良いでしょう。「知らなかった」「聞いていない」で済まされないように、透明性のある情報発信を心がけます。さらに給湯器に限らず専有部分リフォーム全般の相談窓口(管理会社フロント担当者やマンション管理士への連絡先など)を設けておくと、住民から気軽に相談・申請ができトラブルの芽を摘めます。
費用負担の考え方と住民説明の注意点
給湯器交換の費用負担について、管理組合と区分所有者双方で認識を共有しておくことが大切です。原則論は既に述べた通り、給湯器は専有部分の設備であり、その交換費用は当該区分所有者の負担となります。管理組合の修繕積立金や管理費は共用部分の維持管理のために集めたものであり、専有部分の修理に充当することはできません。この原則を踏まえ、費用負担に関して管理組合が留意すべき点と、住民への説明方法のポイントを整理します。
管理組合としての基本方針
管理組合は「給湯器交換費用は各自負担」という方針を明確にし、一貫性を保つ必要があります。仮に理事会内で「多数の住戸で一斉に壊れたのだから組合費用で助成できないか」という意見が出ても、安易に組合負担に踏み切るのは避けるべきです。あるマンションで地震により各戸の電気温水器(給湯器)が破損した際、理事会で「組合費用で修理しよう」との提案があったものの、結果的にそれは不公平であり妥当ではないとの判断に至っています。壊れなかった住戸もある中で一律組合負担とするのは、享受する利益に差が出て不公平ですし、全組合員に合理的な説明もできないからです。従って管理組合としては「専有設備は自己負担」という原則を崩さず、共用部分以外への費用支出は行わないスタンスを維持しましょう。
住民への説明のポイント
費用負担に関しては、なぜ各自負担なのかを住民が納得できるよう説明することが大切です。説明の際は管理規約や区分所有法上の考え方を引き合いに出すと説得力が増します。「マンションには専有部分と共用部分があり、給湯器は専有部分です。共用の修繕積立金は廊下や屋根など共用部分のための基金なので、各戸専有の給湯器には充当できません。このルールは区分所有法と管理規約で定められており、皆様公平にご負担いただくことになります。」といった具合です。特に高額な機器ゆえに不満が出そうな場合は、過去の総会決議事項や専門家の見解なども引用すると良いでしょう。「〇年〇月の総会でご承認いただいたとおり、エアコン・給湯器など専有設備は各戸の管理と費用負担に属します」と議事録を示せば、組合員も再認識できます。
一括交換や割引交渉による費用軽減
費用は各自負担でも、管理組合が音頭を取って一括交換の機会を設けることでコストダウンを図ることは可能です(詳細は次節で述べます)。例えば同じ業者にまとめて複数台発注する代わりにグループ割引を受ける、という手法です。住民への説明では「組合として業者と交渉し、通常より◯万円安い特別価格を引き出しました。任意参加ですが、この機会に交換すればお得です」とメリットを強調できます。管理組合が費用負担するわけではありませんが、交渉力を生かして組合員の経済的負担軽減に寄与する姿勢は喜ばれるでしょう。説明会等では具体的な見積金額や他社比較も示し、透明性を確保しながら住民の理解を得ます。
予算計上と長期修繕計画
前述の通り給湯器交換費用は組合予算からは出しませんので、長期修繕計画の中に給湯器更新工事を組み込むことは通常ありません。ただし将来の修繕計画検討時に、各戸給湯器の更新時期が概ね重なることを考慮し、修繕計画表の備考などに「築15年目頃に各戸給湯器交換時期」等と注記しておくと親切です。そうすることで新築当初から区分所有者自身が将来の出費を認識でき、計画的な資金準備につながります。組合員へのライフプラン支援という観点です。さらに、もし蓄熱式電気温水器など特殊な設備を全戸設置している場合には、共用設備同様に将来の大量故障リスクを見据えて技術的助言や行政支援制度の情報提供をするなど、管理組合としてできるサポートを検討しましょう。
築年数20年超なら要検討?一括交換のメリットと計画的対応
築20年前後のマンションでは、給湯器が一斉に寿命を迎え始める時期です。最近では管理組合が中心となって給湯器の一括交換(まとめて更新)を検討・実施するケースも増えてきました。
ここでは一括交換のメリットや留意点、将来の設備更新に備えた計画的対応について考えてみます。
一括交換のメリット
個別に故障・交換が発生するのを待つのではなく、計画的に一定時期にまとめて交換してしまうことで様々な利点が得られます。最大のメリットは緊急の給湯切れトラブルを未然に防げることです。特に冬場に突然故障すると生活への支障が大きく、修理依頼も集中して工事待ちが発生するケースがあります。一斉交換キャンペーンを温暖な時期(4~9月)に実施すれば、冬の需要ピーク前に交換を終えられ安心です。
また費用面のメリットも見逃せません。複数台をまとめて発注することでスケールメリットによる割引が期待できます。さらに工事日程の調整や業者選定も組合主導で行うため各戸個別の手間が省け、居住者の負担軽減・満足度向上につながります。一括交換は安全・経済両面で大きなメリットをもたらします。
一括交換の進め方
一括交換を検討する際は、まず対象戸数と時期の見極めが重要です。築年数や各戸の給湯器使用年数をアンケート等で把握し、「○年に全◯戸中◯割が給湯器更新時期を迎える」といったデータを集めます。次に信頼できる複数の業者から一括見積もりを取り、割引率やサービス内容を比較しましょう。業者選定や見積査定をコンサルタントが支援するサービスもあります。そうした第三者の力も借りつつ最適な業者を決め、理事会で交換プランを策定します。各戸の任意参加が基本となるため、住民説明会を開催して一括交換の趣旨とメリットを丁寧に説明しましょう。
「壊れていないのに交換するのはもったいない」と思う方もいるため、長い目で見た費用比較(今壊れてから個別に交換すると高くつく可能性)や保証内容の充実など納得材料を提示します。任意参加とはいえ一定数が集まらないと割引が効かない場合もあるため、「◯戸以上参加で工事実施」といった条件設定も検討してください。参加を強制はできませんが、最終的な判断は各所有者に委ねる形で進めましょう(キャンペーン参加はあくまで任意であり、参加しない場合は個別交換を続けても問題ない旨を伝えます)。
一括交換実施時の注意点
実施に当たっては工事日の調整や入居者不在時の対応など実務面の調整が発生します。スケジュールには余裕を持ち、事前に複数日の候補を用意して居住者と調整しましょう。留守世帯には鍵の預け方や管理人立ち会いなどの取り決めが必要です。また交換後の保証書管理やアフターサービス窓口も明確にしておきます。一括交換では「〇年間の延長保証」や「〇年後の無料点検」など特典が付くこともあるので、そうしたアフターケア情報を全員に周知してください。
さらに、参加しなかった世帯へのフォローも忘れずに。次にその世帯の給湯器が故障した場合でも、一度組合で交渉した業者価格を適用してもらえるよう取り計らうなど、公平感に配慮します。理想的には一括交換終了後、理事会が「〇年〇月に◯戸の給湯器一斉交換工事を無事完了しました。ご協力ありがとうございました。」と報告し、実績と効果を記録しておくと良いでしょう。
計画的対応と将来展望
給湯器に限らず、各住戸内の専有設備(ユニットバスや分電盤、インターホン等)もいずれ老朽化します。最近では国土交通省の管理計画認定制度において、専有部分の設備更新も含めた長期的な維持計画が重視される傾向があります。管理組合は大規模修繕計画と併せ、専有部分の主要設備の更新時期を把握し、必要に応じて助言・支援する体制を作ると良いでしょう。例えば築20年を超えたら「専有部設備の更新ガイド」を作成し、エレベーターや給排水管の更新時期と合わせて各戸設備(給湯器や浴室乾燥機など)の更新目安を提示する、といった取り組みです。将来的にはIoT技術等で各設備の寿命予測が容易になるかもしれませんが、現時点では組合と区分所有者のコミュニケーションによる計画的対応が鍵となります。マンション全体で設備更新の知見を共有し、「あそこの家は交換したらしい」「うちはまだ大丈夫かな?」という情報交換が活発になるようなコミュニティ形成も理想です。
まとめ
マンションにおける給湯器交換は専有部分の工事であり各所有者の責任で行うものですが、共用部分への影響や近隣トラブル防止の観点から管理組合との連携が欠かせません。管理規約上は専有部分と位置付けられる給湯器も、物理的に共用部に設置される以上、規約に則った手続きやマナー遵守が必要です。
専有部分工事に関する細則整備や事前申請ルールの徹底によって多くのトラブルは予防できますし、給湯器交換時特有の課題(美観・騒音・排気・安全対策など)も適切な対処でクリアできます。管理組合としては住民に寄り添った情報提供とルール整備を行い、必要に応じて第三者の力も借りながら円滑な対応を心がけましょう。
費用負担については公平性と法規に基づく原則をしっかり説明しつつ、組合主導の一括交換など工夫で経済的メリットを生み出すことも可能です。マンション全体で計画的に設備更新に取り組むことで、将来的な安心・快適さを確保するとともに資産価値の維持向上にもつながります。
給湯器交換やその他修繕対応に不安がある場合は、信頼できる専門家に相談し、プロの知見を取り入れてみましょう。専門家の伴走サポートにより、管理組合運営や工事管理の負担を減らし、理想的なマンションライフの実現に一歩近づけるはずです。
給排水設備等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- 給排水工事では、専有部含め多数、約600戸 多棟型マンションでの実績もあります。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。更新工事/更生工事(含むFRP)それぞれに強みを持つ紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料



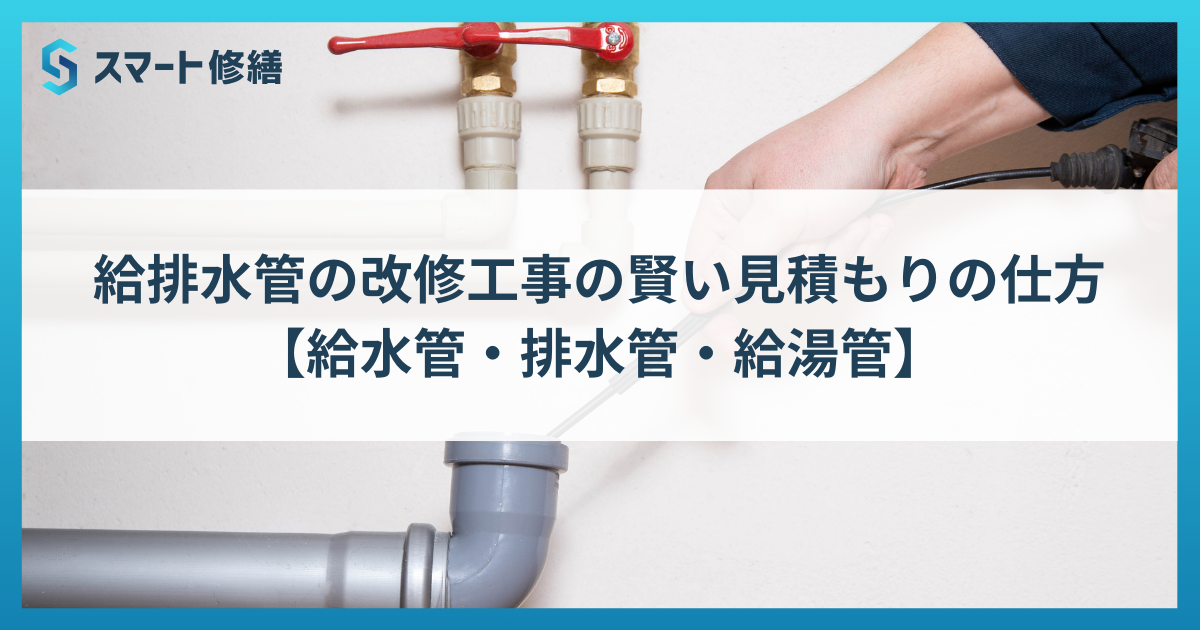
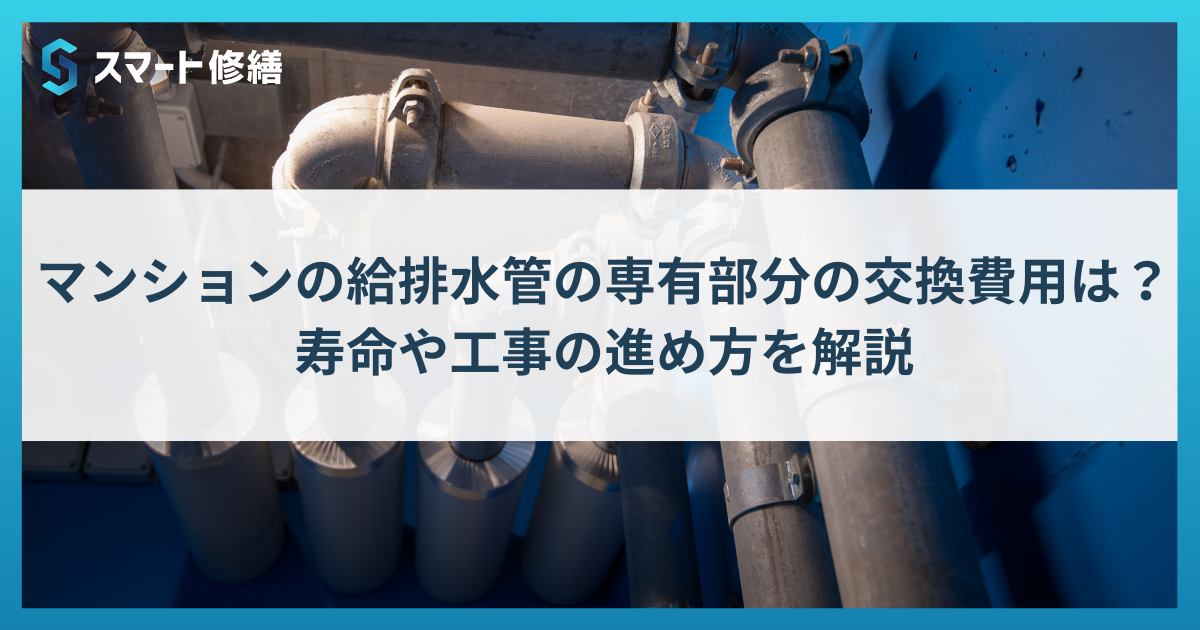
.png&w=3840&q=75)
