マンション給排水管リフォームの種類と費用相場をわかりやすく解説
更新日:2025年04月30日(水)
マンションの給水管・排水管(給排水管)リフォームは、建物の老朽化対策として管理組合が計画すべき重要な工事です。築年数の経過したマンションでは配管の劣化が深刻化し、漏水事故や水質悪化といった問題が発生しやすくなります。 実際、2021年時点で築30年以上経過したマンションは全国で230万戸を超えており、多くの建物が給排水管の更新時期を迎えている状況です。給排水管のリフォームには複数の工法があり、工事範囲や手法によって費用も大きく変わります。 本記事では、マンション管理組合の皆様に向けて給排水管リフォームの種類、費用相場、リフォームの工事方法ごとの特徴や判断ポイント、依頼時の注意点についてわかりやすく解説します。
- 本記事のポイント
- マンションの給排水管リフォームの種類ごとの特徴と費用相場を学べる。
- 給排水管リフォームを判断する築年数の目安や、劣化の兆候・トラブルのサインがわかる。
- リフォーム工事を依頼する際の業者選びのポイントや注意点、住民との合意形成の方法を把握できる。
マンション給排水管リフォームとは?
マンション給排水管リフォームとは、建物内の水道配管や排水配管を修繕・交換して劣化による問題を解消し、安心して生活できる環境を維持するための工事です。 給排水管は普段目に見えない場所にありますが、長年の使用で錆びや腐食が進み、放置すると漏水や詰まりなど深刻な被害を引き起こします。
国土交通省のガイドラインによればマンションの給排水管の寿命はおおむね30~40年程度とされ、これを超えると水漏れトラブルが増加すると指摘されています。実際に古い金属配管では錆による赤水・黄ばみが発生し飲料水の安全性に影響を与えたり、配管内部の腐食で水圧低下や漏水事故が起こり得ます。また、階下への漏水は住民間トラブルや高額な修繕費用につながりかねません。
給排水管リフォームを適切な時期に実施することは、建物全体の寿命を延ばし資産価値を維持・向上させる効果も期待できます。外壁塗装や防水工事など表面的な大規模修繕だけでは、内部の配管が老朽化している場合に快適な住環境を保つことは困難です。
マンション給排水管リフォームの種類
マンションの給排水管リフォームには、大きく分けて以下の3種類の工法があります。それぞれ工事内容や効果、費用が異なるため、メリット・デメリットを理解して選択する必要があります。
更新工事(全面交換)
更新工事とは老朽化した給水管・排水管をすべて新しい配管に取り替える工法で、根本的な解決策となります。 古い配管を撤去し、耐久性の高い新しい管(例:ステンレス管やポリエチレン管)に交換することで、その後30~50年程度は漏水や詰まりなどのリスクを大幅に低減できます。実際、最近では錆びに強い最新素材への交換により更新後の配管寿命は約30~50年とされ、建物が寿命を迎えるまで再度の配管工事が不要になるケースも期待できます。
根拠として、全面交換では配管自体を新品に置き換えるため、錆や腐食といった経年劣化の影響を根本から取り除くことができます。更新工事後は赤水・漏水などの懸念が解消され、水圧低下や悪臭のリスクも減少します。その結果、居住者は長期間にわたり安心して水まわり設備を利用できるようになります。
更新工事の内容は、共用部・専有部問わず老朽化した給排水管を一斉に取り外し、新しい配管に置き換える作業です。各住戸のキッチン・浴室・トイレ内の給水管や排水管も交換する場合、室内の壁や床を一部解体して配管を敷設し直し、最後に原状回復の内装工事を行います。
そのため、工事規模は大きく、期間も長期化します。また騒音・振動や粉塵の発生、各戸への立ち入り作業など居住者への影響も避けられません。最大のデメリットは費用の高さで、後述するように共用部だけでも戸あたり数十万円、専有部を含めると戸あたり100万円を超える負担となるケースもあります。
更生工事(ライニング工事)
更生工事(ライニング工事)とは、既存の給排水管内部を清掃・洗浄した上で特殊樹脂を内側に塗布することで配管を補強・防錆し、配管の寿命を延ばす工法です。 配管を新設せず内側を補修するため、更新工事に比べて工期が短く費用も安価で、居住者への影響(騒音・振動・粉塵)も小さい点がメリットです。劣化が比較的軽微な段階で実施すれば10~15年程度の延命効果が期待でき、近年は技術進歩により従来より長持ちするライニング材も登場しています。
国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでは更生工事(ライニング)の実施目安を19~23年程度と示しており、一度更生して延命した後、築30~40年で更新工事を行うという維持管理モデルが提唱されています。つまり築20年前後でライニング工事により配管を延命し、その後10~20年経過した時点で全面交換することで、トータルの配管寿命を伸ばす考え方です。
更生工事の手順は、まず配管内部に付着した錆や汚れを専用機材で洗浄・研磨し除去します。次に配管内部全体にエポキシ樹脂などの防食コーティング剤を塗布し、管内に新たな樹脂の膜を形成します。これにより、古い配管の内壁をライナーで覆って錆の再発を防ぎ、水漏れリスクを低減させます。工事は各戸の水道メーターや排水口などから作業できるため、大がかりな壁の解体を伴わない場合が多く、工期も数日から数週間程度で済みます。
一方で更生工事はあくまで既存配管の延命措置であり、老朽配管そのものを新品にするわけではありません。そのため、延命後もいずれは更新工事(全面交換)が必要になります。特に配管の劣化状態によってはライニング工法を採用できないケースもあります。
部分交換工事
部分交換工事とは、建物全体の配管を一度に更新・更生するのではなく、劣化や不具合の生じた一部の配管だけを選択的に取り替える工事です。 例えば特定の階の縦管(立管)や、一部の住戸の横引き管で漏水事故が起きた場合に、その部分だけ新しい配管に交換するといった対応が該当します。
マンションの配管は共用部と専有部が複雑に繋がり一体となっているため、本来区分して管理するのが難しいものです。しかし、現実にはすべての配管を一度に更新するには多大な費用と準備が必要なため、当面の処置として不具合箇所のみを修理・交換する部分的な工事が行われる場合があります。例えば「今回は共用部の主要な縦管のみ交換し、各戸内の配管は見送る」といった具合に工事範囲を限定するケースもあります。
部分交換は限定的な工事で済むぶん短期的な費用負担は抑えられます。小規模な漏水修繕であれば数万円程度で収まることもありますし、共用部の主要管1本だけの交換であれば戸あたり負担も更新工事全体に比べて軽微です。しかし、一部の住戸だけ配管を直しても根本的な解決にはならないため、結局マンション全体で計画的な更新工事が必要になります。部分的な対応を繰り返すうちに修繕費用が積み重なり、結果的に当初から計画的に全面更新した場合と同等かそれ以上の費用がかかってしまう恐れもあります。
マンション給排水管リフォームの費用相場
給排水管リフォームにかかる費用は、工事の範囲(共用部分のみか専有部分まで含むか)と採用する工法(更新か更生か)によって大きく異なります。またマンションの規模(戸数や階数)や配管系統の数によっても総額は増減します。ここでは一般的な費用相場の目安を紹介しますが、実際の見積もりでは各マンションの条件に応じて変動する点にご留意ください。
まず費用の考え方として、マンション全体の総工事費は各戸の負担額の合計となります。大規模な配管更新では工事費が億単位に達することもあり、管理組合の財政に大きな影響を及ぼします。費用負担の算定方法は管理規約で定められた持分割合等に基づきますが、便宜上「1戸あたり○○万円」といった形で示されることが多いため、本記事でも戸あたり費用で相場を説明します。
共用部のみの場合の費用相場
共用部分(パイプスペース内の縦管や横主管など)だけを更新・更生する場合、費用は比較的抑えられます。全面交換(更新工事)で共用部のみを施工するケースでは、戸あたり約20~50万円程度が一般的な相場です。例えば給水管の共用縦管だけ交換するなら一戸あたり20万~30万円、排水管の縦管交換で同程度、といった具体例が報告されています。
工法を更生工事とした場合はさらに費用が低くなり、共用部の排水管ライニングでは戸あたり10万円程度から施工可能との事例もあります。給水管のライニングも同様に1戸あたり十数万円程度が目安でしょう。共用部のみの場合、各住戸内の内装復旧費用が発生しないため、このように比較的低コストで済みます。ただし、共用部だけでは根本解決とならず専有部内の老朽管リスクは残るため、共用部工事を先行する場合でも将来的な専有部工事の計画を立てておく必要があります。
共用部のみの工事費は管理組合が全額を修繕積立金等から負担するのが通常です(詳細は後述の費用負担ルール参照)。1戸あたり数十万円とはいえ戸数が多ければ巨額となるため、組合の資金計画(長期修繕計画)で事前に積み立てておくことが重要です。
専有部を含む場合の費用相場
各住戸内の専有部分の配管も含めて建物全体の配管を更新する場合、費用は大きく増加します。専有部内の工事では壁や床の解体・復旧といった内装工事が伴うため、その分の費用が加算されます。全面交換(更新工事)で専有部まで含める場合、戸あたり約100万~150万円以上の負担となるケースも少なくありません。
専有部を含む場合の費用内訳は、共用部配管工事費+各戸内工事費となります。例えばとある試算では「共用部の給水管交換:戸あたり20~50万円」「専有部(各戸)の給水・給湯管交換:戸あたり20~100万円」「専有部の排水管交換:戸あたり20~100万円」といったレンジが示されています。最大値側で見れば各戸内全ての管を更新すると合計で戸あたり数百万円規模になり得ることがわかります。
このように費用負担は大きいものの、専有部内まで含めて一度に工事を行うことで各戸がバラバラに工事するよりもコストを抑えられる場合があります。全戸一斉に施工することでスケールメリットが働き、人件費や仮設費用を削減できるためです。管理組合としても、専有部を含む配管更新工事を長期修繕計画に組み込んで計画的に資金準備することで、一度の大規模工事で建物全体の配管問題を解決できる利点があります。
工法別の費用比較
上記で示した共用部/専有部別の相場を踏まえ、主な工法ごとの費用と効果を比較してみましょう。以下の表に、更新工事・更生工事・部分交換工事それぞれの目安費用(1戸あたり)と耐用年数、特徴をまとめます。
工法・範囲 | 配管の状態 | 耐用年数の目安 | 1戸あたり費用相場(目安) | 特徴(メリット・デメリット) |
|---|---|---|---|---|
更新工事(全面交換) | 古い配管を全て新品に交換(共用部のみ) | 約30~40年ごとに実施 | 約20~50万円 | 根本解決策。劣化問題を一掃し長期間安心。費用は比較的抑えられるが、未交換の専有部老朽管リスクは残る。 |
更新工事(全面交換) | 古い配管を全て新品に交換(共用+専有) | 約30~40年ごとに実施 | 約100~300万円 | 最も確実な根本解決策。今後数十年はメンテ費用低減。工期長・費用大きい。居住者への影響(立ち入り・騒音)大。 |
更生工事(ライニング) | 既存配管内部を洗浄・防錆コート | 約15~20年の延命 | 約10~30万円 | 配管を延命し更新時期を先送り。費用・工期を大幅削減。騒音や工事の負担小。劣化状況次第では施工不可も。将来的に再度更新工事が必要。 |
部分交換工事 | 不具合のある部分のみ交換 | 状況による(他の老朽管は残存) | 数万円~数十万円 | 応急措置的に問題箇所を解消。短期間・低コストで対応可。根本的解決にならず、他箇所で再度トラブル発生の恐れ。最終的には全体更新が必要。 |
※上記費用は一般的な目安であり、実際の工事費用はマンションの規模・構造、採用材料、施工業者等によって変動します。また専有部を含む更新工事費用の負担方法(各戸負担か修繕積立金からの支出か)によって各戸の実質負担額も異なります。
マンション給排水管リフォームを判断するポイント
配管リフォームの要否や工法を判断する際、管理組合が検討すべきポイントを整理します。以下のチェック項目を参考に、タイミングと方針を見極めましょう。
築年数と配管素材の確認
まず建物の築年数と使用している配管の材質を把握します。築後30年以上経過している場合、たとえ目立った不具合がなくても配管更新を視野に入れる時期です。特に1970~80年代頃までのマンションで使われた亜鉛メッキ鋼管(鉄管)は錆びやすく寿命が30年前後と短いため、更新の必要性が高いです。
劣化の兆候・トラブル発生状況
次に現在の配管の状態を評価します。錆混じりの赤水や濁り水が出ていないか、排水の流れが悪く頻繁に詰まりが起きていないか、過去に漏水事故が発生していないかなどの兆候をチェックしましょう。配管劣化の典型的な症状である赤水は、内部の亜鉛メッキが溶出したり鉄錆が発生しているサインです。悪臭を伴う排水詰まりも内部に汚れや油脂が堆積し管径が狭まっている証拠です。こうした兆候が見られる場合、その配管系統では既に劣化が進行しており、放置すれば漏水事故に発展するリスクが高まります。
長期修繕計画上の時期
自主管理・委託管理を問わず、マンションには長期修繕計画があります。そこに給排水管の改修時期がいつ頃に設定されているかを確認しましょう。国土交通省のガイドライン改訂により、配管更生は19~23年目、配管更新は30~40年目を目安にするよう示されています。長期修繕計画もこれに沿って策定されているケースが多く、2回目の大規模修繕(築25~30年)や3回目(築37~40年)で給排水管工事が計画項目に含まれていないか確認します。
工事範囲(共用部のみか専有部も含めるか)の決定
配管リフォームの方針として、「共用部分の配管だけを先行して改修するか」「専有部分の配管も含め一体的に改修するか」を検討します。根拠: 前述の通り専有部まで含めた更新は費用負担が大きく、合意形成も難易度が上がります。
一方、共用部だけでは専有部老朽管の問題を先送りにするだけで根本解決になりません。国土交通省策定のマンション標準管理規約のコメントでは、「共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことで各戸個別に行うより費用が軽減される場合、一体的に工事を行うことも考えられる」と記載されています。つまり全戸まとめて実施したほうがコストメリットがあるなら、専有部配管も含めて工事する価値があるということです。
費用負担のルールと合意形成
配管リフォームの費用を誰がどのように負担するかを明確にし、組合内で合意形成を図る必要があります。管理組合は事前に①費用負担方法(専有部分を各戸負担にするのか修繕積立金から出すのか)、②それに伴う規約変更や総会決議の必要性、③過去に自主的に専有部配管交換を行った区分所有者への補償の有無、などを総合的に検討します。特に修繕積立金から専有部工事費用を支出する場合、管理規約の改定と総会特別決議(議決権数および区分所有者数の各4分の3以上の賛成)が必要となり、ハードルは高めです。
合意形成の過程では「自分の部屋の配管工事費まで組合で出すのはおかしい」という反対意見や、「将来売却予定なので費用負担したくない」という消極的意見も出がちです。しかしマンション全体で計画的に実施しないと根本的な解決にならないことを丁寧に説明し、長期的なメリットを共有することが大切です。必要に応じてマンション管理士やコンサルタントなど第三者専門家の助言を仰ぎ、住民理解を深める説明会を重ねるなどして、合意形成に努めましょう。
耐震・防災面のリスク
給排水管リフォームの判断には、災害時のリスク対応も考慮します。根拠: 老朽化した配管は平常時の漏水だけでなく、大地震時に破損してしまうリスクが高くなります。配管が破断すると地震後に水道やトイレが使えなくなり生活に重大な支障をきたします。証拠: 東京都は老朽マンション対策の一環で「東京とどまるマンション給排水管点検調査」という制度を設け、専門家を無料派遣して古い配管の調査・改修方法の提案を行っています。これは大規模地震後に老朽配管が損傷し生活インフラが断たれる事態を防ぐ目的であり、行政も配管更新の重要性を防災面から支援している証左と言えます。
給排水管リフォームを依頼する際の注意点
配管リフォームの方針が決まり具体的に業者選定・発注段階に移る際には、管理組合として以下の点に注意してください。
施工業者の選定
マンションの配管工事実績が豊富な専門業者を選ぶようにしましょう。戸建てや小規模修繕とは異なり、マンションの給排水管工事は「居住者が生活しながらの工事」であり、「共用部分と専有部分の権利関係への理解」が必要など特殊な側面があります。このため、業者選定にあたってはマンション設備工事の経験・ノウハウが豊かな会社を重視してください。具体的には、過去に似た規模のマンション配管更新工事を手掛けた実績や、マンション管理会社からの推薦状などがある業者が望ましいです。自治体やマンション管理組合連合会等が紹介する適切な業者リストがあれば参考にすると良いでしょう。
相見積もりの取得
業者は必ず複数社から見積もりを取って比較検討することが大切です。管理会社から1社だけ紹介される場合もありますが、その1社に即決するのではなく、他の専門業者からも提案をもらいましょう。複数の工事会社から相見積もりを取ることで、工法や工事範囲の提案内容・見積金額を比較でき、過不足のない適切な工事計画を立てる助けになります。一社だけでは見抜けなかったコストダウンの工夫(例:一部更生工法を組み合わせる、仮設水道の効率的な設置方法など)が提示されることもあります。また相見積もりを取ること自体が業者間の適正価格競争につながり、不当に高額な見積となるリスクを減らす効果もあります。各社の見積内容は管理組合内でしっかり精査し、不明点は質問してクリアにしましょう。
工事契約と範囲の明確化
業者が決まったら契約を結びますが、その際に工事範囲・内容・費用負担区分を明確に文書で取り決めることが重要です。共用部と専有部のどこからどこまでを工事対象に含めるのか、専有部内の原状回復(内装復旧)は工事費用に含まれているか、仮設水道の設置や工事中の清掃など付帯サービスはどうか、といった点を契約書や仕様書で具体的に定めます。特に専有部分工事費用の扱いはデリケートなので、例えば「専有部内工事費○○万円は各区分所有者の負担とし、工事会社へ直接支払う」「全体工事費に含め管理組合から一括支出する」等、あらかじめ総会決議内容と整合する形で契約に反映させます。契約書の条項は専門用語も多いため、必要に応じて管理会社や弁護士等に内容を確認してもらいましょう。
居住者への周知と協力依頼
工事を円滑に進めるには、居住者全員の理解と協力が不可欠です。工事日程や各戸への立ち入り日時、断水する時間帯などを事前に丁寧に周知してください。特に専有部内の工事がある場合、在宅日時の調整や家具移動のお願い、貴重品管理の注意喚起など細かな配慮が必要です。高齢世帯や日中不在世帯には個別にフォローし、支障なく工事に入れるよう調整します。ポスト投函や掲示板告知だけでなく、説明会の開催や回覧での詳細説明など、複数の手段で周知徹底すると安心です。また工事期間中は管理組合として問い合わせ窓口を設け、住民からの苦情や要望を速やかに施工側へ伝えられるよう体制を整えましょう。
施工後の検査と保証
工事完了後は必ず竣工検査を実施し、契約内容どおりに工事が完了したか確認します。給水管であれば通水テストや水圧試験、排水管であれば排水テストや目視確認などを行い、漏れや詰まりがないことをチェックします。併せて各戸内の復旧箇所(壁紙や床材)は丁寧に仕上がっているか、汚損や傷はないかを住戸ごとに確認し、問題があれば迅速に補修させます。また工事保証の内容も確認しましょう。通常、給排水管更新工事には何年間かの保証期間が付きますので、保証書を受け取り大切に保管します。
万一、工事後しばらくしてから不具合(例えばごく小さな漏れや、閉め忘れたバルブ等によるトラブル)が見つかった場合でも、保証期間内であれば無償で対応してもらえます。保証期間終了後も定期点検などフォローアップ契約を結べる場合もありますので、必要に応じ検討してください。
工事記録の保存
工事完了後、施工図面や写真、工事報告書などの記録資料を管理組合で保管しておきましょう。新しく交換した配管の配置図やバルブ位置図、使用材料のメーカー保証書などは、今後のメンテナンス時に役立ちます。次回の長期修繕計画の見直しにも活用できますし、万が一将来売却する区分所有者が出た場合にも「配管更新済み」であることを示すエビデンスとなり、物件価値アピールにつながります。
特に業者選びと住民周知はトラブル防止の肝です。信頼性・専門性の高い業者による丁寧な工事と、管理組合・居住者の協力体制が揃えば、大掛かりな配管工事も安心して乗り切ることができます。
まとめ:最適なリフォームで快適な暮らしを実現しよう!
マンションの給排水管リフォームについて、種類ごとの特徴と費用相場、判断ポイントや注意点を詳しく解説してきました。公的ガイドラインや標準管理規約を活用しつつ、組合員全員が納得できる形で計画立案・合意形成を行いましょう。その上で経験豊富な施工業者を選定し、適正価格で高品質な工事を実現するよう努めます。
工事中のコミュニケーションやアフターケアまで含め、一連のプロセスを丁寧に管理することで、将来にわたって「このマンションに住んでいて良かった」と思える結果につながるはずです。
最後になりますが、マンション管理組合の役割は年々重要性を増しています。給排水管リフォームのような専門性の高いテーマでも、本記事のような信頼できる情報源を活用すれば適切な判断が可能です。ぜひ本稿の内容を組合運営や理事会協議の資料としてお役立てください。適切なリフォームによって安全・安心な住環境を維持し、住民全員が快適な暮らしを実現できるよう、管理組合一丸となって取り組んでいきましょう。
給排水設備等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- 給排水工事では、専有部含め多数、約600戸 多棟型マンションでの実績もあります。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。更新工事/更生工事(含むFRP)それぞれに強みを持つ紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料



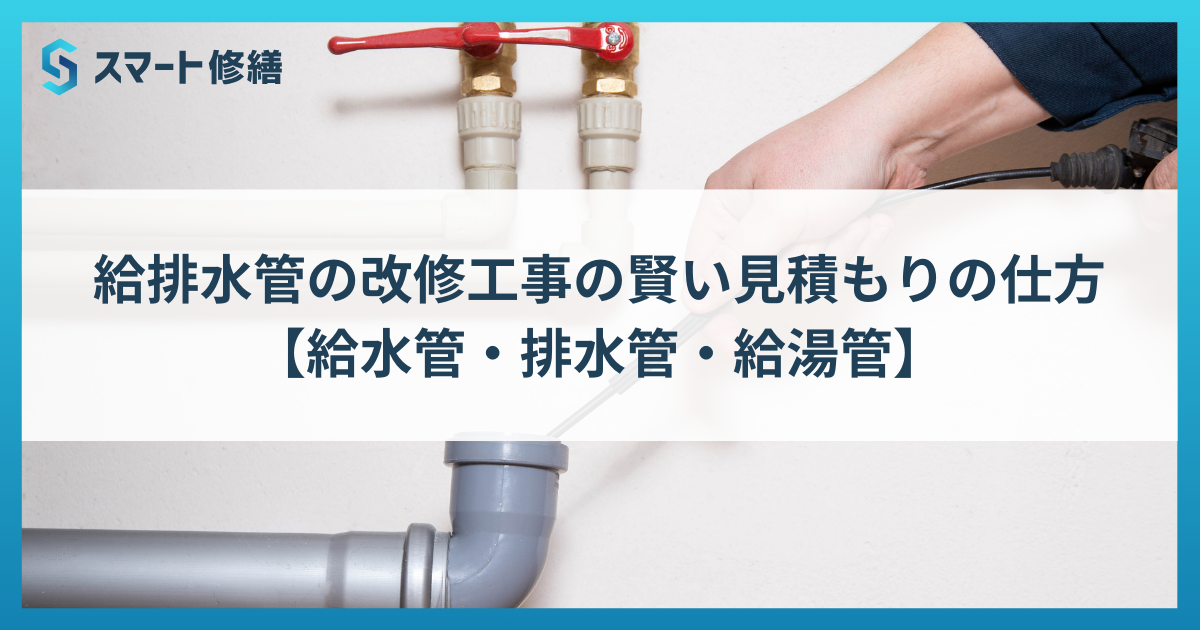
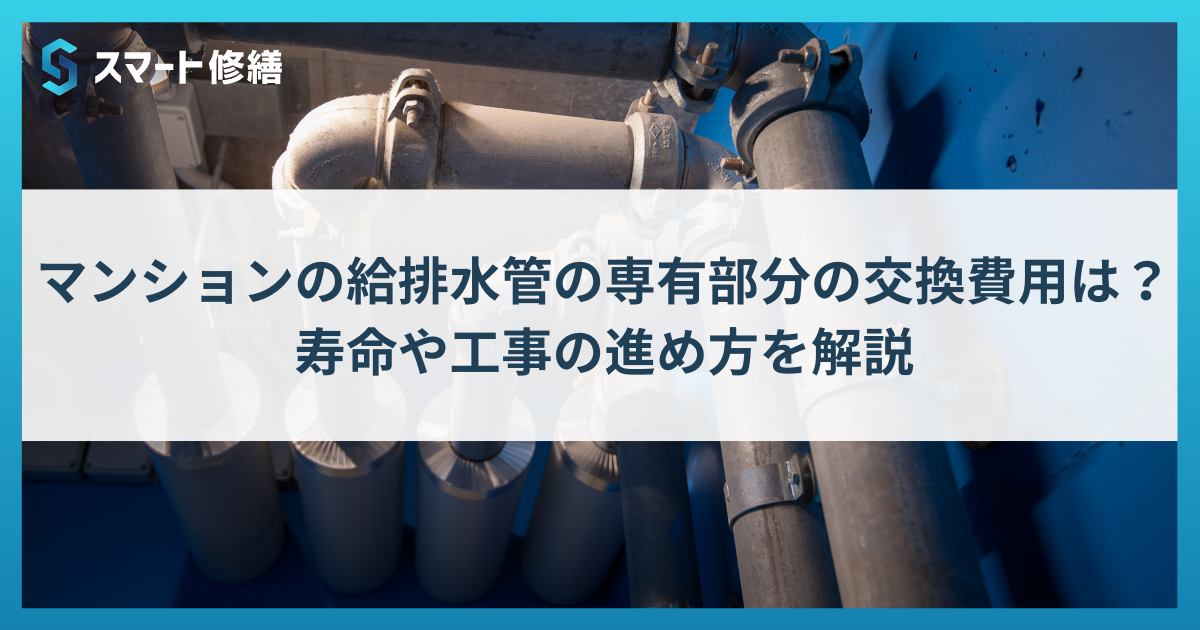
.png&w=3840&q=75)
