マンション排水管改修工事のポイントと注意点
更新日:2025年04月30日(水)
マンションの排水管は年月とともに劣化し、放置すると漏水や詰まりなど深刻なトラブルに発展します。特に老朽化した排水管からの漏水は階下の住戸にも甚大な被害を及ぼし、住民間のトラブルや高額な修繕費につながりかねません。 マンション管理組合にとって、排水管の適切な改修工事を計画・実施することは建物の長寿命化と安心安全な暮らしのために非常に重要です。 本記事では、マンションの排水管改修工事に関する基礎知識から工事のタイミング、工法の種類、費用相場、工事中の注意点、信頼できる業者選びまで、改修工事を検討するのに有用なポイントと注意点を解説します。
- 本記事のポイント
- 排水管の材質ごとの耐用年数と劣化サインを学べる。
- 排水管改修工事を検討すべき具体的なタイミングがわかる。
- 改修工事の種類別メリットや費用相場を把握できる。
マンション排水管改修工事の基礎知識
排水管改修工事について理解を深めるために、まず2つの基礎知識を押さえましょう。ひとつは排水管に使われる材質と耐用年数の目安、もうひとつはマンションにおける排水方式の種類です。それぞれ順に説明します。
排水管の種類と耐用年数
排水管の材質によって耐用年数(寿命)が異なり、金属製配管はおよそ20~30年、塩ビ管など樹脂製配管は50年前後が目安です。 これは一般的な寿命の目安であり、実際の寿命は使用環境やメンテナンス状況によって前後します。金属製の排水管(例えば鋳鉄管や銅管)は腐食により内部が錆びやすく、長期間使用すると肉厚が薄くなって穴が開き漏水の原因となります。一方、塩化ビニル管(塩ビ管)やポリエチレン管などのプラスチック製排水管はサビや腐食の心配がなく耐久性が高いため、40~50年以上もつケースもあります。ただしこれらはあくまで目安であり、定期的な点検や清掃を怠ると想定より早く劣化する可能性があります。
昭和期に建てられた古いマンションでは、排水の縦管などに鋳鉄製の排水管が使われている場合があります。このような金属製排水管は約20~30年で赤錆による閉塞や腐食穴による漏水が発生しやすくなります。実際、1960年代まで一般に使われていた亜鉛メッキ鋼管(給水管ですが類似の金属管)は15~20年程度しか寿命が持たず、現在では水道用途で使用禁止となっているほどです。
一方で、1970年代以降の建物では塩ビ管の使用が主流となり、サビない素材のため比較的長期間トラブルなく使用できています。樹脂製配管でも、例えば浴室やキッチンで大量の熱湯を流した場合に変形するなど、極端な使用条件では劣化が早まることもあるため油断は禁物です。耐用年数を過ぎた排水管は漏水や破損のリスクが高まるため、定期点検を実施し劣化状況を把握したうえで、寿命を迎える前に更新や更生による改修を検討することが大切です。
排水方式の種類
マンションの排水方式には、大きく分けて「合流式」と「分流式」の2種類があります。 これらは汚水と雑排水を一本の排水管にまとめるかどうかの違いです。マンションの排水経路には、トイレの排水である「汚水」と、キッチン・浴室・洗面所・洗濯機などからの「雑排水」、そして雨どいなどからの「雨水」の3系統があります。雨水は自然由来のもので生活排水ではないため、通常は汚水・雑排水とは別系統で排水されます。
マンションによって配管構成は異なりますが、一般的に合流式ではトイレの汚水とその他の雑排水を同じ排水立て管(縦管)にまとめて流し、分流式では汚水と雑排水を別々の縦管で流す方式を指します。例えば、合流式では各階のトイレも浴室も台所も全て一つの縦配管に接続され、分流式ではトイレ排水用の縦管と雑排水用の縦管が分かれている、といった具合です。
合流式は配管を一本にまとめられるため設置コストを低減できるメリットがありますが、その分一つの管に汚物も油脂分も集まるため詰まりのリスクが高くなり得ます。また管内の悪臭対策や通気の設計も重要です。一方、分流式は排水を系統ごとに分けることで油脂などによる閉塞を防ぎやすい利点があります。さらにマンションによっては、キッチンの雑排水(油分が多く詰まりやすい)だけ独立の縦管にする「部分分流」のような方式も採用されています。
いずれの場合も、各住戸からの排水は最終的に建物敷地内の排水管(横引き管)で合流し、公共下水道へと流されます(下水道未整備地域では浄化槽を経由)。東京23区では地域により細かな排除方式の指定があり、新設時にはその方式に適合するよう排水設備を設計施工する必要があります。マンション居住者にとって配管の方式は普段意識することは少ないですが、排水方式の違いを知っておくとトラブル発生時にどの系統で問題が起きているか把握しやすくなるため、有事の対処に役立ちます。
マンション排水管の改修工事を行うタイミング
排水管の改修(更新や更生)は、築後20~30年を過ぎた頃から検討を始め、遅くとも築40年程度までに実施するのが望ましいタイミングです。 また、明らかな劣化兆候(漏水や度重なる詰まり等)がある場合は築年数に関わらず早急に対策すべきです。
国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」では、給排水管の取替え(更新)時期の目安を築30~40年目と示しており、30年目あたりで更新するのが望ましく、40年程度までに更新しないと漏水事故が多発する傾向があると指摘されています。これは「水漏れや詰まり等の被害が発生しないよう、できるだけ早めに改修するのがよい」という趣旨であり、特に築30年を超えるマンションでは排水管の更新を積極的に検討することが推奨されています。
国交省が令和3年に改定した長期修繕計画ガイドラインによれば、従来30年とされていた給排水管更新の目安が30~40年に幅を持たせて設定されています。さらに平成30年度のマンション総合調査では、築40年以上でも給排水管の改修工事を実施したマンションは3割以下と非常に少ない実態が報告されており、この結果を踏まえてガイドライン改定では「30年程度で更新、遅くとも40年までに更新する」ことを促す内容となっています。
実際には資金不足等で排水管まで手が回らず40年以上未改修のマンションも珍しくありませんが、老朽化が進んだ配管は地震時にも損傷しやすく大地震後にトイレや水道が使えなくなるリスクも高まります。こうしたリスクを考えると、築年数とともに定期的な調査診断を行い、計画的に改修時期を見極めることが重要です。
具体的なタイミング判断のポイント
ここでは、排水管改修を検討すべき具体的なタイミングを4つの兆候としてまとめます。
築年数が経過している
前述の通り築20~30年を過ぎたら予防的な観点で改修計画の検討を開始しましょう。特に一度も配管更新や更生を行っていない築30年以上の建物は要注意です。長期修繕計画に基づき、大規模修繕(外壁や防水工事等)に合わせて配管工事を計画すると効率的です。なお築15年程度でも、給排水管の法定耐用年数(減価償却上の年数)は15年と定められているため、耐用年数を過ぎた段階で将来の更新計画を議論し始める管理組合も多く見られます。
漏水(水漏れ)の発生
天井や壁に水シミが現れたり、階下の住戸で天井から水が滴るなどの漏水事故が発生した場合、早急な対応が必要です。パッキン等の部品劣化による場合もありますが、配管そのものに腐食による穴あきやひび割れが生じているケースでは全面的な配管交換が必要になることがあります。特に汚水管(トイレの配管)からの漏水は悪臭や衛生被害が甚大です。被害拡大や住民間トラブルを避けるためにも、漏水が起きたら応急処置だけでなく抜本的な改修のタイミングと捉えましょう。
排水の詰まりや悪臭が頻発
台所や浴室の排水が度々詰まる、流れが悪くなる、または排水口付近から下水臭が上がってくるといった症状は、配管内部に相当量の汚れが蓄積しているサインです。キッチンの雑排水管では油脂がこびり付き固まりやすく、浴室や洗面の排水管では石鹸カスに毛髪や垢が絡んで詰まりの原因となります。これらが進行すると油塊の腐敗による悪臭や、排水逆流といった深刻な事態に発展します。定期的な高圧洗浄など清掃を行っても再び短期間で詰まるようなら、管内劣化が進んでいる可能性が高いため改修の検討時期と言えます。
水質の異常やサビ汚れ
蛇口から赤茶色のサビ混じりの水が出る(赤水)などは給水管の劣化兆候ですが、排水についても配管内の腐食が進むと流れたサビや腐食片が排水口に溜まって周囲に茶色い汚れとして現れることがあります。また排水管の継手部分からジワジワ漏れて床下が濡れるケースでは、床や壁にカビ臭や腐敗臭が漂うこともあります。こうした異常に気付いた場合も早めに専門業者に調査を依頼し、必要なら改修に踏み切るのが安全です。
改修工事の方法
排水管の改修工事には大きく分けて2種類の方法があります。それが「更新工事」と「更生工事」です。以下ではそれぞれの工法の特徴やメリット・デメリットを結論→根拠→具体例の順で解説します(※マンションによっては部分的な補修など他の対処法を組み合わせる場合もありますが、ここでは代表的な2工法を取り上げます)。
更新工事
更新工事とは、老朽化した排水管そのものを撤去し、新しい配管に全面的に取り替える工事です。 劣化した管を新品に交換することでサビや腐食といった悪影響を根本から解消でき、工事後は数十年規模(概ね30~50年程度)にわたり漏水や詰まりのリスクを大幅に低減できます。マンション全戸の排水管を一斉に更新すれば、場合によってはその後建物の寿命が尽きるまで再度の更新工事が不要になるケースもあります。
更新工事では既存の古い排水管をすべて取り外し、新規配管を設置します。新しい管材には耐久性の高いステンレスや合成樹脂管などが使用されるため、交換後は長期間にわたり安定した排水性能が期待できます。近年は管材技術の進歩もあり、従来よりも寿命の長い配管への更新が主流となっています。例えば鋼管から腐食しにくいステンレス管やポリエチレン管へ更新すれば、将来的なサビ発生を抑制できメンテナンス負荷も軽減できます。
更生工事
更生工事(ライニング工事)とは、既存の排水管内部を洗浄し特殊な樹脂等で内壁をコーティングすることで、配管を交換せずに寿命を延命させる工法です。 古い管をそのまま活かすため工期が短く費用も抑えられるのがメリットで、騒音・振動も比較的少ない方法です。適切な更生工事を施せば、当面のサビや漏水リスクを低減しつつ配管の使用を継続できます。
更生工事ではまず配管内部に付着したサビ・汚れ・油分などを研磨や薬品洗浄で徹底的に除去し、その後エポキシ樹脂などのライニング材を管内に塗布します。これにより管内面に新たな樹脂被膜(内張り)を形成し、内側から配管を補強・防錆します。工事の手順は配管内部のみで完結するため壁や床を壊す必要がなく、更新工事に比べ居住者への負担が小さいのが特徴です。例えば更新では各戸に数日ずつ立ち入り工事が必要だったのに対し、更生ではパイプスペース等から管内部作業を行うため各戸への入室時間が短くて済んだケースもあります。費用面でも、更新より1戸あたり数十万円規模安価になる傾向があります。
マンションの排水管改修工事にかかる費用
排水管改修工事の費用は、建物の規模や工事範囲、採用する工法によって大きく異なります。マンション全体で数百万円から数千万円と幅がありますが、一般的に更新工事(配管取替)は更生工事(ライニング)に比べて1.5~2.5倍程度高額になるとされています。管理組合としては事前に相場観を把握し、長期修繕計画に沿って計画的に資金を準備することが重要です。
共用部のみ排水管を更新する場合の費用は1戸あたり30~70万円、共用部のみ更生工事なら1戸あたり20~40万円が一つの目安とされています。
50戸規模のマンションで全戸の排水管更新を行えば、単純計算で数千万円規模になる計算です。一方、更生工事で対応できれば場合によっては半額程度に圧縮できる可能性があります。実際、あるマンション(7階建て50戸・築37年)で他社が出した排水管更新工事の見積り約1億3,000万円が、ライニング更生工事なら約5,400万円で施工可能と試算された例もあります。
このように工法選択によって費用に大きな差が出るため、複数の選択肢を比較検討することが大切です。
費用に影響する主な要因
排水管改修工事の費用は以下のような要素によって決まります。
工事範囲・規模
共用部分(立て管や横引き管)のみ行うのか、各住戸内の専有部分の配管まで含めて行うのかで費用は大きく変わります。また建物の総戸数や階数、配管延長や径の長短によって必要材料や作業量も異なるため、同じ工法でも規模が大きいほど総費用は高額になります。
工法と使用材料
更新工事か更生工事か、また更生工事の場合でも塗布ライニングなのかFRPライニングなのか等、選択する工法や使用する樹脂・管材の種類によって費用単価が変動します。例えば更生工事でも、耐久性に優れる樹脂ライニング(FRPライニング)は材料費・施工コストが高めですが寿命が長く、樹脂塗布のみの簡易ライニングは安価な反面耐久年数が短い(約10年程度)とされます。最適な工法を選ぶには初期費用と効果持続年数のバランスを考慮する必要があります。
施工期間と人件費
工事に要する期間が長くなるほど人件費や仮設経費が増加します。特に居住者の生活への影響を減らすため工事可能時間を制限したり、夜間作業を行う場合は追加費用が発生します。例えば日中しか作業できない場合、全体工期が延びその分人件費が嵩むことになります。
付帯工事費用
排水管工事に付随して必要となる周辺設備の補修や仮設設備の設置にも費用がかかります。たとえば、工事期間中に一時的な仮設排水ラインや仮設トイレを設置する場合や、撤去した配管周りのコンクリート補修・内装復旧工事などです。こうした付帯工事も含めて総額となるため、見積もり時にはどこまで含まれるか確認が必要です。
以上のように、費用は建物ごとに個別性が高いものです。そのため実際に改修計画を立てる際は、信頼できる複数の業者から詳細な見積もりと工事計画の提案を受け、内容と金額を比較検討することをおすすめします。その際、工事範囲や使用材料、工期、保証内容など細部まで確認し、総合的に判断することが重要です。
工事中の注意点とトラブル回避策
排水管改修工事を円滑に進め、トラブルを避けるために、管理組合として押さえておくべき注意点を6つ挙げます。事前準備から工事完了まで、以下のポイントに留意しましょう。
事前計画と住民合意
工事開始前の入念な準備が何より重要です。準備不足のまま着工すると、想定外の問題で工事が遅延したり入居者とのトラブルに発展する恐れがあります。特に排水管工事では各住戸の専有部分へ立ち入って作業する必要があるため、全住戸の協力を得ることが肝心です。もし一部の住戸が工事に非協力的だと、その配管だけ老朽化が放置され将来漏水事故につながる危険性が高まります。数百戸規模の大規模マンションでは合意形成に時間がかかり、プロジェクト完了までに数年を要するケースもあります。理事会・管理会社主体で早めに計画を立ち上げ、住民説明会等を通じて十分な理解を得ておきましょう。
専門調査の実施
工事に先立ち、専門業者による現況調査・診断を必ず実施しましょう。配管の劣化状態を正確に把握することで、更新工事か更生工事か適切な工法の選定が可能になります。事前調査では配管内カメラ調査や水圧テストなどを行い、目に見えない問題箇所を洗い出します。その結果に基づき工事範囲や工法を最終決定することで、施工中の追加工事や変更を減らし予算超過や工期遅延のリスクを抑えられます。例えば更生工事を予定していたが調査で一部管に穴が開いていることが判明し、その部分のみ更新工事に切り替えたケースもあります。プロの診断に基づき最適な計画を立案することが成功の鍵です。
周知と代替策の準備
工事中は一時的に水の供給や排水が停止する可能性があります。そのため、該当時間帯の代替手段を事前に考慮し入居者に周知しておく必要があります。具体的には、「○月○日の午前10~12時は○号棟の水道・トイレ使用禁止」といったスケジュールを早めに通知し、各自に事前に水を汲み置きしてもらう、仮設トイレを設置する、他棟のトイレを共用開放する等の対応策を検討します。断水や排水停止に関わる作業は可能な限り短時間で済むよう工程を工夫し、工事日時の選定も平日日中に限定するなど配慮しましょう。長期間にわたる大規模工事では、週末や夜間の作業を避けることで入居者の生活リズムを守ることも大切です。
騒音・振動への配慮
配管工事ではハツリ(コンクリート削り)作業や機械操作に伴う騒音・振動が避けられません。近隣や同じマンション内への影響を最小限にするため、工事可能時間帯を管理規約に従い昼間の一定時間内に限定します。騒音が大きい作業(コア抜き等)は時間帯を定め、一斉放送や掲示で「○時から○時に大きな音が出ます」と事前周知するなど、心構えしてもらう工夫をしましょう。振動で家具や棚上の物が落下しないよう各戸に呼びかけることも有効です。また、防音シートの設置や低騒音型機器の使用など業者側で取れる対策は講じてもらいます。管理組合として事前に業者と打ち合わせ、騒音振動対策計画を確認すると安心です。
安全管理の徹底
工事期間中の安全対策も重要な注意点です。共用部での作業では、資材や工具の落下防止策、立ち入り禁止措置、消火設備の確保など、安全管理を徹底してもらいましょう。特に高所作業や溶接作業がある場合、施工業者にリスクアセスメントと対応策を事前提出させると安心です。居住者にも工事箇所に近づかないよう通知し、お年寄りや子供への注意喚起も行います。また、万一事故や損害が発生した際の責任範囲や保険について契約段階で確認しておくこともトラブル回避につながります。信頼できる業者であればこの点もしっかり説明してくれるでしょう。
進捗共有と監督体制
工事期間中、管理組合が主体的に工事状況を把握し、入居者に適宜進捗を共有することも大切です。施工管理は基本的に業者に任せますが、丸投げにせず定例会議などで進行状況や問題点の報告を受けましょう。特に長期に及ぶ工事では、「全体の○割が完了した」などの情報を定期的に掲示・配布していくことで入居者の安心感につながります。住民からの苦情や要望が出た場合も迅速に施工側と調整し、可能な範囲で対応策を講じるよう努めます。工事完了後には組合として立ち会い検査を行い、施工不良や見落としがないか確認しましょう。以上のように終始コミュニケーションを密に取り、管理組合・施工業者・居住者が一体となって工事を成功させる姿勢がトラブル防止の最大のポイントです。
業者選びのポイント
排水管改修工事の成否は、施工を任せる業者の技術力や信頼性に大きく左右されます。ここでは、管理組合が業者選定する際にチェックすべきポイントを挙げます。
実績と専門性
マンションの排水管改修工事の豊富な実績を持つ業者を選ぶことが望ましいです。過去に類似規模・構造のマンション工事を手掛けた経験があれば、工事計画や住民対応も慣れており安心です。業者のウェブサイトや会社案内で施工実績例を確認したり、必要に応じて他の管理組合から評判を聞くのも有効でしょう。
また、更生工事を検討している場合はライニング工法の専門業者かどうかもポイントです(更新工事が得意な業者、ライニングを専門とする業者、それぞれあります)。工法ごとに高度な技術とノウハウが求められるため、自社で対応できない工法を無理に勧めてくる業者には注意が必要です。信頼性の高い業者は自社の得意不得意を正直に説明し、必要に応じて協力会社を紹介するなど誠実に対応してくれるでしょう。
複数社からの見積取得と比較
いきなり一社に決めてしまわず、必ず複数の工事会社から見積もり提案を取得して比較検討しましょう。排水管改修工事は高額なため、一社だけでは適正価格か判断がつきにくいからです。3社程度からプランを提示してもらい、総額だけでなく工事範囲や使用材料、工期、保証内容の違いをしっかり確認します。例えば「A社は更生工事で○年保証、B社は更新工事で保証なしだが価格は安い」など、それぞれメリット・デメリットがあります。サービス内容や提案の妥当性、見積り明細の透明性なども注目し、価格だけに惑わされず総合的に評価しましょう。なお見積もり依頼時には各社に同じ条件で依頼する(現地調査に立ち会う、図面や過去の修繕履歴を共有する等)ことで、公平な比較が可能になります。
契約条件と保証
最終的に契約する際は、契約書に工事内容の詳細や責任範囲、保証条件を明記してもらいます。工事後何年間は不具合があれば無償補修するのか、保証範囲(漏水事故への補償など)はどこまでか、といった点を確認しましょう。大規模な工事では念のため履行保証保険への加入も検討します。また、万が一工期が延びた場合の取り決め(違約金や追加費用の扱い)も契約で取り交わしておけばトラブル時に安心です。信頼できる業者であれば契約内容も明確で、こちらの疑問にも丁寧に答えてくれるはずです。
まとめ:マンションの大規模修繕は専門家に相談しよう
マンションの排水管改修工事は、建物の寿命や居住者の安心に直結する重要なイベントです。本記事で解説したように、排水管の種類や劣化サインを理解し、適切なタイミングで適切な工法を選ぶことが肝要となります。特に築年数の経過したマンションでは、早め早めの対策が将来の大きなトラブル防止につながるでしょう。
しかし、実際の工事計画を立てるには専門知識が不可欠です。管理組合だけで判断するのが難しい場合は、遠慮なく専門家に相談することをおすすめします。例えば、国土交通省や東京都など行政でも老朽配管に関する無料相談や現地調査支援を行っています。東京都では、古くなった給排水管の改修方法や大地震後の点検方法を提案してくれる専門家派遣制度を実施しており、管理組合が利用できる支援策があります。
また、マンション管理適正化法に基づくマンション管理士や建築士事務所のコンサルタントに依頼し、第三者の立場から改修計画を策定してもらうのも有効です。公的機関が公表しているガイドラインや統計データも積極的に活用し、エビデンスに基づいた計画づくりを心がけましょう。
排水管改修工事は決して安価ではありませんが、放置すればマンション全体の資産価値や安全性を損ねるリスクがあります。管理組合として十分な知識と準備を持って臨めば、きっとスムーズに工事を成功させることができるはずです。迷ったときは経験豊富な専門家の意見を仰ぎ、適切な判断を下すことが何より重要です。建物の将来と居住者の安心のため、計画的な排水管改修工事を進めていきましょう。
給排水設備等修繕の支援サービス「スマート修繕」
- 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
- 給排水工事では、専有部含め多数、約600戸 多棟型マンションでの実績もあります。社内にはゼネコン、デベロッパー、修繕コンサルティング会社、修繕会社、管理会社出身の建築士、施工管理技士等の有資格者が多数いますので、お気軽にご相談ください。
- 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。更新工事/更生工事(含むFRP)それぞれに強みを持つ紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料



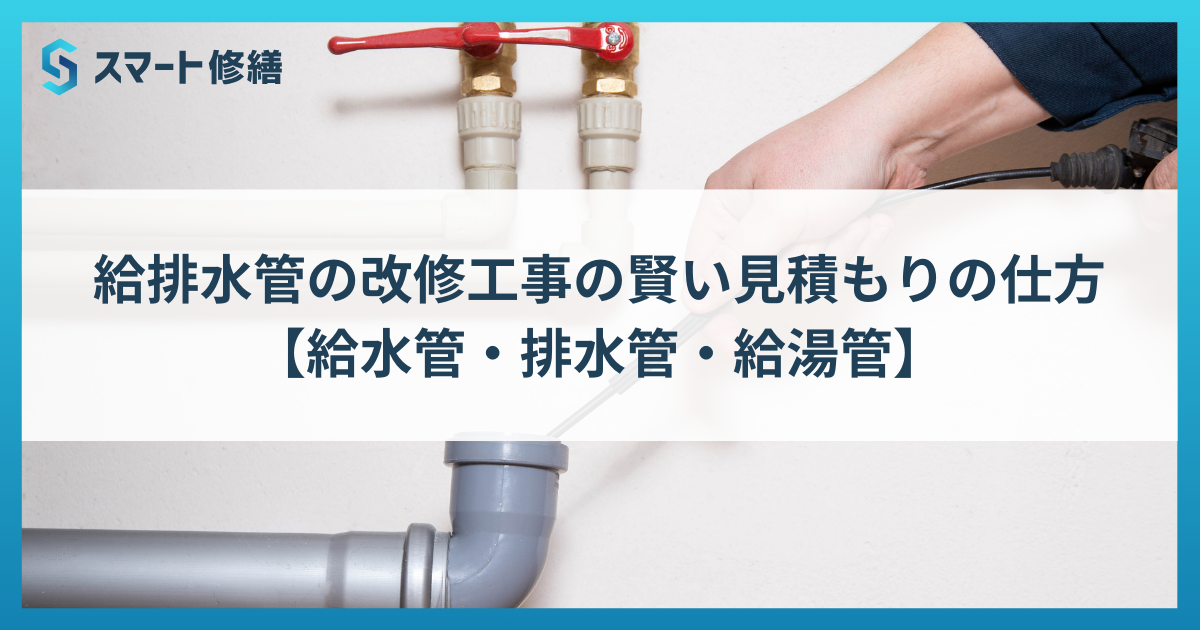
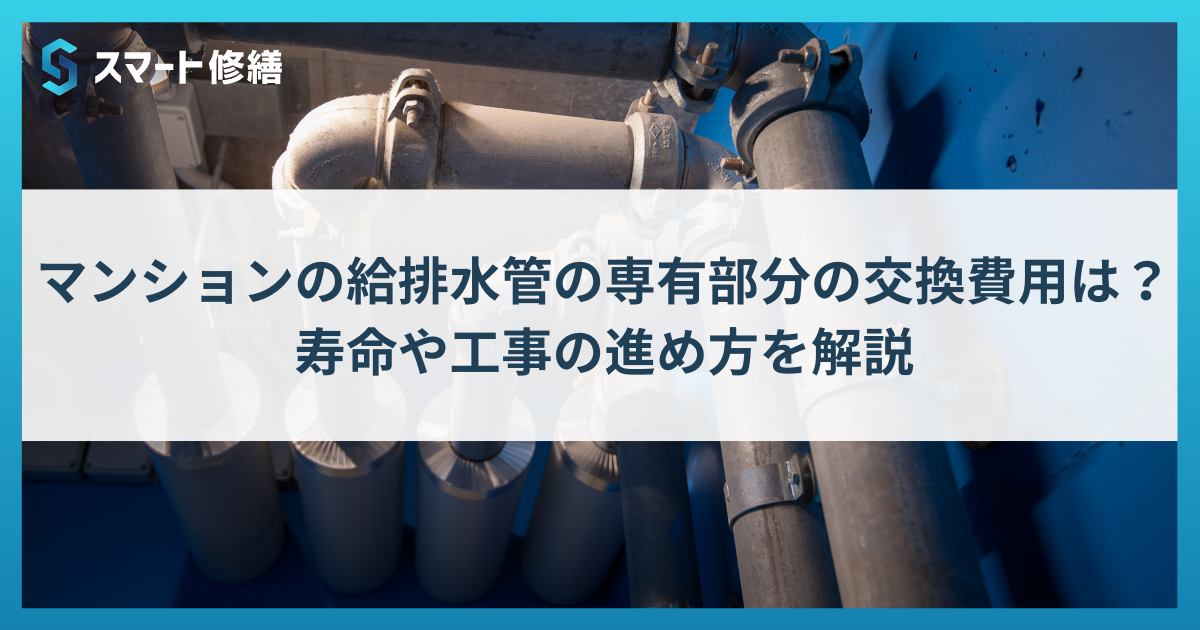
.png&w=3840&q=75)
