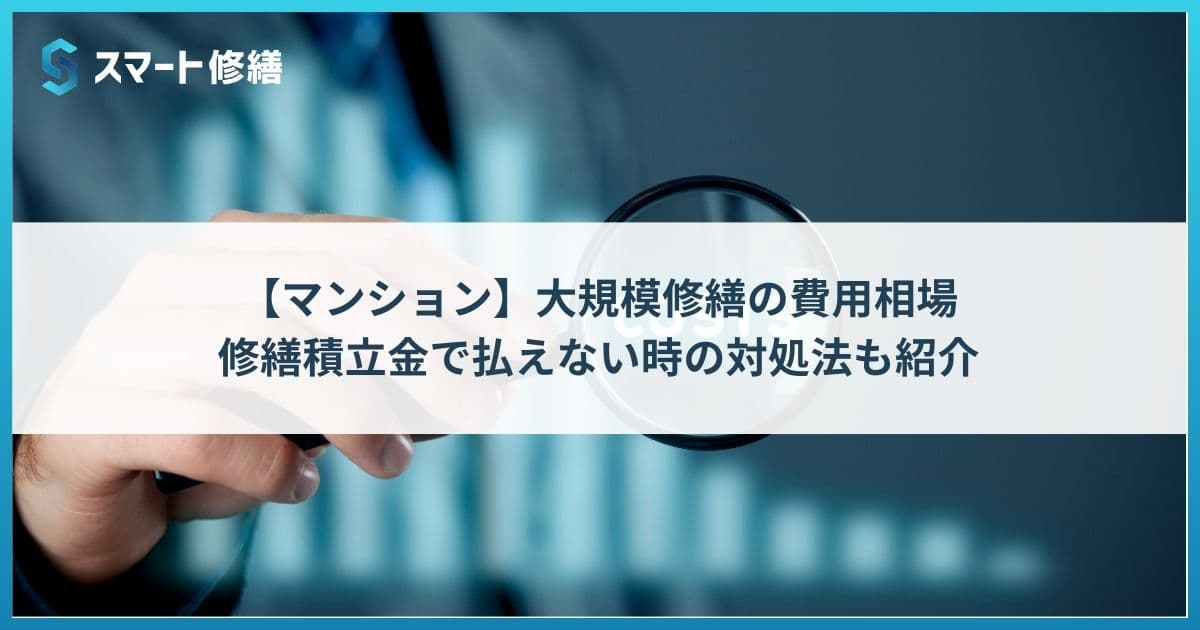マンションの新耐震基準はいつから?旧耐震基準と新耐震基準の違いも解説
更新日:2025年09月17日(水)
マンションの購入や管理を考える上で、「旧耐震」「新耐震」という言葉は避けて通れません。特に「マンション 新耐震基準 いつから」といった疑問を持つ方も多いでしょう。1981年を境に建築基準法の耐震基準が大幅に強化されており、この違いは建物の安全性や資産価値に直結します。 本記事では、新耐震基準がいつから施行されたのか、その背景や旧耐震基準との具体的な違いを解説します。また、旧耐震マンションにおける耐震診断・補強の必要性、補助金制度、専門家による支援サービスの活用方法について、マンション所有者・購入検討者・管理組合の方々に役立つ情報を提供します。
- 本記事のポイント
- 旧耐震基準と新耐震基準の違い(想定される地震規模・構造設計の手法など)が理解できる。
- 自分のマンションが新耐震かどうかを「建築確認日」で判断する方法や、耐震診断・補強の流れがわかる。
- 国や自治体の補助金制度、税制優遇等を活用して、コスト負担を抑えながら安全性と資産価値を保つ手段が把握できる。
新耐震基準はいつから施行?
新耐震基準は1981年(昭和56年)6月1日の建築基準法改正によって導入されました。それ以前(~1981年5月)に適用されていた基準は「旧耐震基準」と呼ばれます。
新耐震基準制定の直接のきっかけは1978年6月12日に発生した宮城県沖地震でした。この地震ではマグニチュード7.4、最大震度5の揺れで27名が死亡し、RC造ビルの倒壊を含む甚大な被害が発生しました。とりわけ近代的な都市で大地震に襲われた初の例として衝撃を与え、当時の耐震基準の不備が浮き彫りになったのです。
宮城県沖地震の教訓を受け、建築基準法は1981年に改正され耐震基準が大幅に強化されました。新耐震基準では「震度6強~7程度の大規模地震でも建物が倒壊・崩壊しないこと」が法的に求められるようになり、ブロック塀の規制強化など安全対策も強められました。
この新基準の施行以降に建てられた建物は、旧基準に比べ地震に対する安全性が飛躍的に向上しています。実際、1995年の阪神・淡路大震災でも、被害の多くは旧耐震基準の建物に集中し、新耐震基準の建物は倒壊が少なかったことが報告されています。新耐震基準のマンションが大地震でその安全性を実証した一方、旧耐震の建物は依然リスクを抱えていることが明らかになりました。
旧耐震基準と新耐震基準の違い
旧耐震基準は1950年制定の建築基準法施行時から1981年5月まで適用されていた耐震基準で、新耐震基準は1981年6月以降に適用された基準を指します。両者では想定する地震の規模や構造設計上の要求事項が大きく異なります。
主な相違点は以下のとおりです。
想定される地震規模の違い
旧耐震基準では中規模地震(震度5強程度)で倒壊しないことが目標で、大地震(震度6以上)は想定されていませんでした。一方、新耐震基準では震度6強~7程度の大地震でも「倒壊・崩壊しない」ことが明確に求められています。新耐震の建物は震度6~7クラスの直下型地震に対しても人命を守る性能を持つとされています。
構造計算方法の違い
旧耐震基準下では構造設計時に一次設計(許容応力度計算)のみ行われ、各部材が中程度の地震荷重に耐えられるか確認していました。新耐震基準ではこれに加えて二次設計として「保有水平耐力計算」が導入され、建物が大地震時に最大級の力を受けても倒壊しないことを計算で検証するようになりました。
簡単に言えば、新基準では構造物の粘り強さ(靭性)と余裕度も考慮した設計が必要となり、建物全体の倒壊しにくさを数値的に確認するプロセスが追加されています。これにより、新耐震の建物は巨大地震に対しても粘り強く踏ん張る設計となっています。
構造規定・細部基準の違い
新耐震基準では、建物形状や構造上の弱点への対策も強化されました。
例えば耐力壁の配置バランスについて偏りがないか検証し、1階がピロティ(柱だけで壁が少ない開放階)になっている建物の弱点を補うよう求めています。また各階の層間変形(ねじれや揺れによる変形)が過大にならないよう、層間変形角1/200以下といった基準も設けられました。旧耐震時代には考慮されていなかった偏心率のチェック(建物の重心と剛心のずれ確認)やピロティ形式への補強なども新基準で追加された項目です。
要するに、新耐震基準では不規則な形状や下階の壁不足による弱点を構造計算で補強・是正することが義務化され、よりバランスの良い安全な構造が求められています。
以上のように新耐震基準は旧耐震基準に比べ、想定地震の規模も設計の厳密さも格段に向上しています。
特に「震度6~7でも倒壊しない」ことが公式に要求されている点は、新旧で最も大きな違いと言えます。その分、新耐震の建物では大地震でもひび割れ程度の被害に留め、人命を守ることが期待されています。一方、旧耐震の建物は震度6以上の直下型地震に対する安全性が証明されていない建物であり、大地震時には深刻な損傷や倒壊のリスクを抱える点に注意が必要です。
「新耐震」と「旧耐震」の見分け方:建築確認日と竣工日の関係
1981年6月1日を境に耐震基準が切り替わったことは前述のとおりですが、重要なのは「建物の完成日ではなく建築確認申請の受理日」で判断するという点です。
建築確認日とは、建物の設計が法令に適合しているか行政が確認し、確認済証が発行された日付のことです。新耐震基準は1981年(昭和56年)6月以降の確認申請に適用されたため、確認済証の発行日が1981年6月1日以降であれば新耐震基準、1981年5月31日以前なら旧耐震基準で設計されていると判断できます。
この区切りにより、例えば1982年や1983年竣工のマンションでも、設計自体が1981年5月以前に確認申請を通していれば旧耐震基準となります。実際に「1982年竣工だけど旧耐震だった」というマンションも存在するため注意が必要です。反対にごく一部ではありますが、旧耐震時代(1981年以前)に建設されたが新耐震相当の耐震性を持つマンションもあります。これは当時の設計者が自主的に耐震余裕を多めにとったケースなどですが、基本的には少数例です。
お持ちのマンションが新耐震か旧耐震か確認する方法としては、管理組合が保管している「建築確認済証(確認通知書)」の日付を確認するのが確実です。もし手元に書類が無い場合でも、市役所の建築課で「確認台帳記載事項証明書」を発行してもらえば建築確認日を調べられます。購入を検討している中古マンションの場合は、必ず建築確認日を不動産業者に確認し、その建物が旧耐震か新耐震か把握しておきましょう。新耐震基準に適合している物件かどうかは、安全面だけでなく後述する資産価値や融資の面でも重要なポイントとなります。
耐震診断の必要性と方法
旧耐震基準で建てられたマンションにお住まいの場合、まず検討すべきは耐震診断です。国土交通省も「1981年(昭和56年)以前に建築された建物は耐震性が不十分なものが多い」ため、まず耐震診断で自らの建物の耐震性を把握するよう呼びかけています。耐震診断を行えば、現状の建物が大地震に対してどの程度耐えうるかが数値(耐震指標Is値など)で評価され、補強の必要性を客観的に判断できます。
耐震診断は誰に依頼できる?費用は?
一般的に、一級建築士の資格を持つ耐震診断の専門家(構造設計事務所など)に依頼します。マンションの場合、管理組合が主体となって専門家へ診断を発注します。診断の費用は建物の規模や延床面積によりますが、数十万円から数百万円程度かかるケースが多く、詳細な構造計算を伴う場合は高額になります。
ただし多くの自治体で診断費用の補助制度があり、国と地方自治体で診断費用の2/3を補助してくれる制度も用意されています。補助金制度を活用すれば、費用負担を大きく減らすことが可能です。
診断の内容と流れ
耐震診断ではまず予備調査として建物の設計図書や増改築履歴、劣化状況などを確認し、適用する診断方法を決定します。次に専門家が現地調査を行い、コンクリート強度の推定や鉄筋探査、ひび割れ状況の記録など必要なデータを収集します。そして構造計算により建物の耐震性能(各階の耐震指標Is値など)を算出し、基準値と比較して安全性を評価します。
例えば住宅の耐震診断では、Is値が0.6未満で耐震性不足と判定されるケースが多く、その場合は補強工事や建て替えが推奨されます。診断結果について専門家から詳細な報告を受け、補強の必要性や緊急度を管理組合で検討することになります。
耐震診断の結果、「耐震性に問題なし」と判定されればひとまず安心ですが、仮に安全性に不安が指摘された場合は放置せず対策を検討することが肝要です。旧耐震マンションは「震度7の直下型地震で倒壊しない保証がない建物」でもあるため、専門家の診断で弱点が見つかった場合には早めに補強計画を立てることが居住者の生命・財産を守ることにつながります。
耐震診断には行政の義務付けも徐々に強まっています。大切なマンションを将来にわたり安全に使い続けるため、まずは耐震診断による現状把握を行いましょう。
耐震補強工事の流れと工法の例
耐震診断の結果、マンションの耐震性が基準を満たしていない場合は耐震補強工事(耐震改修工事)を検討する必要があります。補強工事には建物の構造や弱点に応じて様々な方法がありますが、いずれも「建物の弱点を補い、地震に耐える強さを高める」ことが目的です。ここではマンションにおける耐震補強の一般的な進め方(フロー)と代表的な工法を紹介します。
耐震補強計画・工事の進め方(フロー)
補強方針の検討
耐震診断結果を踏まえ、構造の専門家とともに補強の方針を決定します。建替えか補強かの比較検討や、補強しても目標の耐震性が確保できるか検討する段階です。管理組合で合意形成を図り、補強工事を行う方向で意見がまとまれば次へ進みます。
補強設計の実施
構造設計者が具体的な補強設計を行います。どの柱・壁を補強するか、どんな工法を使うか、補強後どの程度耐震性が向上するかを計算し図面化します。補強案と概算費用が示されるので、管理組合で承認を得ます。必要に応じて補強設計は評価機関の評定を受け、補助金申請に備えます。
施工業者の選定
補強設計に基づき施工業者から見積もりを取得します。複数社から提案を募り、工法・価格・実績を比較検討するとよいでしょう。専門家の助言を受けながら適切な業者を選定し、工事契約を締結します。
耐震補強工事の施工
工事計画に従い、現場で補強工事を実施します。基本的に居住者が住んだまま工事を行うため、工事中の騒音・振動や粉じん対策、資材置き場の確保などに配慮しながら進めます。工事期間中は共用部の立入制限や仮設物の設置など、不便も生じますが、安全第一で施工が進められます。補強内容によって数か月〜1年以上の工期になる場合もあります。
完了・効果の確認
工事完了後、補強によって耐震性が所定の水準に向上したことを確認します。設計者や第三者機関による検査を経て、目標の耐震性能が確保されたことを住民にも報告します。その後、補強された建物として耐震基準適合証明書を取得することも可能です(後述の税制優遇等に活用)。
代表的な耐震補強工法(マンションの場合)
耐震補強の方法は建物ごとに異なりますが、マンションでよく採用される主な工法は次のとおりです。
耐震壁の増設・補強
壁量(耐力壁の量)が不足している建物には、コンクリート壁を新設したり既存壁を厚くする方法で建物全体の強度を高める補強を行います。壁のない開口部を塞いで新たに壁を増やす、あるいは壁内に鉄筋を追加埋設する工法などがあります。特に1階ピロティ部分など壁が少ない階に壁を追加設置するのは基本的な強度向上策です。
鉄骨ブレース(筋かい)の設置
建物の枠組みに斜め材(ブレース)を入れて補強する方法です。RC造マンションの場合、柱と梁で構成されるラーメン架構の開口部に鉄骨の筋かい(ブレース)を取り付けることで水平力に対する抵抗力を高めます。ブレース設置は壁を増やすのと同様に強度向上効果が大きく、かつ開口部の一部を残せる利点もあります(駐車場スペースの確保等)。
柱・梁の巻き立て補強
建物を支える柱や梁そのものを強くするため、部材の周囲を別の材料で巻いて補強する工法です。具体的には、既存の柱の周囲に鉄筋コンクリートを増し打ちする「RC巻き立て工法」、柱を厚い鉄板で巻いてモルタル充填する「鉄板巻き立て補強」、そして炭素繊維シートを柱に巻き付ける「炭素繊維巻き補強」などがあります。
これらはいずれも柱・梁の粘り強さ(靭性)や耐力を向上させる目的で、地震時に部材が脆性的に壊れないようにする効果があります。特に炭素繊維シート補強は近年注目される工法で、炭素繊維は引張強度が鉄の約10倍、重量は4分の1と非常に高性能な素材です。エポキシ樹脂などで既存構造にシートを直接貼り付ける外付け補強工法であるため、構造を大きく壊さず短工期で施工でき、居住者に与える負担も小さい点がメリットです。薄いシート状のため施工後に内装・外観へ与える圧迫感も少なく、美観を損ねにくい利点もあります。炭素繊維補強を施すことで、古いマンションでも現行耐震基準を満たすレベルまで耐震性能を向上させた事例も増えています。
建物形状の弱点改善
建物の形状由来の弱点(不整形さや偏心など)がある場合は、その部分を補強してリスクを低減します。例えばピロティ形式で柱だけの階が弱点なら、先述の壁追加や柱補強で1階部分の耐力を底上げします。耐力壁の配置偏りが問題なら、不足部分に新設壁を設けるなどして構造バランスを是正します。これらは個々の建物固有の弱点に合わせたオーダーメイドの補強策です。
免震レトロフィット(Base Isolation Retrofit)
既存建物に後付けで免震装置を設置する高度な工法です。建物の基礎下や中間階にゴム支承や滑り支承といった装置を挿入し、地震エネルギーをそこで吸収・遮断してしまうことで上部構造を大きく揺らさないようにします。免震レトロフィットは工期・費用とも大規模になりますが、揺れそのものを低減できる最先端の対策で、文化財建築物などで採用例があります。マンションでは事例が限られますが、選択肢の一つとして知っておくと良いでしょう。
以上のように耐震補強には様々な手法があります。
補強工事を行う際の注意点として、基本的に住みながらの工事となるため騒音・振動やスペース確保など居住者の負担軽減策が課題になります。また補強後は室内に補強壁や柱型が出て生活動線に影響が出たり、窓の一部が塞がれることで採光や眺望に制約が出るケースもあります。外観デザインが変わってしまうこともあります。こうした実用上・景観上の影響も総合的に検討し、最適な工法を選択することが重要です。信頼できる専門家と十分に協議し、自分のマンションに合った補強方法を計画しましょう。
耐震性不足のマンションが抱えるリスク(安全性・資産価値)
耐震補強を行っていない旧耐震マンションには、大きく分けて「地震安全性のリスク」と「資産価値・取引面のリスク」が存在します。
安全性のリスク
旧耐震基準の建物は前述のとおり震度6強~7の地震に対する安全策が不十分であり、巨大地震では倒壊や大破する危険性があります。阪神・淡路大震災では建物倒壊により多数の犠牲者が出ましたが、その多くが旧耐震物件だったことが報告されています。新耐震基準の建物であれば大地震でも倒壊しない可能性が高く、人命が守られやすいのに対し、旧耐震では命に関わるリスクがどうしても高くなってしまうのです。
「今まで大きな地震が来ていないから大丈夫だろう」と思われがちですが、日本は南海トラフ巨大地震や首都直下地震など近い将来に発生が予想される大地震が指摘されています。いざという時に取り返しのつかない被害を出さないためにも、旧耐震マンションの所有者・居住者は早めに耐震性の確認と必要な対策を講じておくことが肝要です。
資産価値・市場取引上のリスク
旧耐震マンションは、不動産市場で敬遠されがちであることも知っておく必要があります。購入を検討する買い手は耐震性能に不安を感じやすく、同じ立地・規模でも新耐震の物件に比べ売却価格が低めに評価される傾向があります。
また金融機関の住宅ローン審査においても、耐震基準は大きく影響します。新耐震のマンションなら35年ローンが組める場合でも、旧耐震だと融資期間が10~20年程度と短くなり、評価額(担保評価)も低く抑えられてしまうことが一般的です。金融機関から見れば、旧耐震物件は「大地震で建物が無くなるリスク」があるため担保価値を低く見積もらざるを得ないのです。結果として買い手は希望額のローンを組めなかったり、月々の返済負担が増えるため購入自体を諦めるケースも出てきます。
具体例を挙げると、住宅金融支援機構の長期固定ローンフラット35では築年数が古い住宅でも利用可能ですが、旧耐震物件の場合は事前に耐震評価を受けて基準適合証明を取得することが条件となります。耐震チェックには時間と費用がかかり、場合によっては「基準不適合」と判定されるリスクもあるため、買い手にとって大きなハードルです。
このように耐震性が劣る物件はローンの制約や手続き負担が増えるため、敬遠され売れにくい傾向があります。資産価値の維持という観点からも、旧耐震マンションをこのまま放置することにはデメリットが大きいと言えるでしょう。
以上を踏まえると、旧耐震マンションの所有者にとって耐震性の改善は喫緊の課題です。安全面の不安を取り除くことはもちろん、適切な耐震補強や建替えによって耐震適合物件となれば、資産価値や流動性の向上、ローン利用制限の解消、地震保険料の軽減(※耐震等級に応じた割引制度あり)といったメリットも得られます。逆に何も対策せず時間が経てば、建物は老朽化が進み修繕コストが増大するうえ、市場評価も下がり続ける恐れがあります。
「いつか大規模地震が来るかもしれない」というリスクに備え、早めに耐震診断・補強で建物の安全性を確保することが、結果的に資産価値を守ることにもつながるのです。
耐震診断・耐震改修に利用できる補助金・支援制度
マンションの耐震化を進めるため、国や地方自治体は様々な支援制度(補助金・融資・税制優遇)を用意しています。費用が高額になりがちな耐震診断や耐震改修ですが、これらの制度を上手に活用することで経済的負担を大幅に軽減することができます。
ここでは代表的な支援策を紹介します。
国による耐震改修支援策
国土交通省は「住宅・建築物の耐震化の現状と目標」を定め、令和12(2030)年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消する目標を掲げています。この達成に向け、毎年各種補助制度が予算化されています。例えば「住宅・建築物安全ストック形成事業」では、耐震診断や耐震改修、建替え等に要する費用の一部を補助しています。具体的には、耐震診断や補強設計にかかる費用の2/3を国と自治体が補助(民間所有の住宅の場合)する枠組みや、耐震改修工事費用自体にも一定額の補助金を出す仕組みがあります。
また耐震改修促進税制として、耐震改修工事を行い所定の耐震基準を満たした場合に所得税控除(工事費用の一定割合、上限額あり)や固定資産税の減額(一定期間1/2減税等)を受けられる制度も整備されています。
さらに住宅金融支援機構では、マンションの管理組合向けに耐震改修工事費用の長期ローンを低利で融資する制度や、高齢者向けのリバースモーゲージ型融資(リ・バース60)なども提供しています。
このように国の支援策を組み合わせれば、診断・改修にかかる自己負担をかなり抑えることも可能です。
自治体(都道府県・市区町村)の補助制度
各自治体でも地域の実情に応じた補助金を設け、耐震化を促進しています。
例えば東京都では、昭和56年以前築の分譲マンションを対象に耐震診断・補強設計・耐震改修工事それぞれの費用の一部を助成する制度があります。東京都の最新施策の一例として、「命を守るためのピロティ階等緊急対策事業」があります。これは旧耐震マンションでピロティ形式など倒壊リスクが高い構造を有するものについて、耐震補強設計および工事費用の2分の1(50%)を助成する制度です。補助金の上限額は設計・工事合わせて1,750万円と高額で、2025年度から助成限度額と対象範囲を拡充し、延べ面積1,000㎡未満の小規模マンションにも対象を広げています。具体的には、耐震診断の結果1階ピロティの耐震指標Is値が0.4未満と判定されたマンションが対象となり、まずピロティ部分の補強費用を補助するものです(将来的には建物全体の耐震化も促す位置づけ)。
このほか東京都では、大地震発生後も居住を継続しやすいマンションを増やす「東京とどまるマンション」促進事業や、段階的な耐震改修を支援する制度などもあります。自治体によって名称や内容は様々ですが、多くの市区町村で耐震診断の無料化または大部分補助、耐震改修工事費の一部助成を行っています。
詳しい内容は各自治体の建築防災担当部署やマンション耐震化支援窓口にお問い合わせください。
専門家派遣・相談制度
自治体によっては、マンションの耐震化について専門家(建築士)を無料派遣して初期相談に乗ってくれたり、耐震診断結果の見方や改修方針についてアドバイスしてくれる制度もあります。耐震改修には技術的・資金的な検討事項が多いため、こうした制度も積極的に活用するとスムーズです。
支援制度は毎年度更新される場合もあるため、最新の情報を自治体の公式サイトや国土交通省の案内ページでチェックしてください。適用条件(例えば戸数や延べ面積の制限、管理組合総会の決議要件など)が定められている場合もありますが、要件を満たせば公的資金で工事費の半額以上が補填されるケースも珍しくありません。高額な耐震改修も補助金を上手に使えば実現可能ですので、「費用が心配で踏み出せない」というマンションも一度調べてみる価値があります。
スマート修繕で実現する、安心・適正な耐震化
マンションの耐震性は、安全面だけでなく資産価値や将来の売却・融資にも直結する重要なテーマです。旧耐震の建物にお住まいの方や購入を検討している方は、まずは耐震診断や補強の必要性を確認することが安心につながります。
本記事でご紹介したように、補助金制度や専門家のサポートを活用すれば、費用や手間を軽減しながら耐震化を進めることも可能です。大切なマンションを守るためにも、早めの行動が肝心です。
「スマート修繕」は、耐震診断から工事会社の選定、住民合意形成まで、専門家が一貫して伴走するコンサルティングサービスです。管理組合だけでは難しい課題も、中立的な立場から適正な内容・費用で進められるため、安心してマンションの耐震化に取り組めます。
耐震性に不安をお持ちの管理組合様は、ぜひご相談ください。
マンションの「建替バリュー」 を見える化する「スマート建替」
- 「スマート建替」は、マンションの「建替バリュー」がマップ上で分かる、ディー・エヌ・エー(DeNA)グループの無料のサービスです(特許出願中)。※建物を建て替える価値を自動で計算しマップ上で表示するWEBサービスは、日本初となります。(2024年6月・当社調べ)
- 「建て替えるべきか」、「耐震補強工事をするべきか」、「修繕工事をするべきか」、「それぞれの経済性の評価、検討プロセスはどうしたらいいのか」、といったお悩みを、スマート建替の専門的なアドバイスとサポートで解決します。
- 「耐震補強工事」「修繕工事」については、「スマート修繕」で各種支援をさせていただきます。「スマート修繕」では、担当コンサルタントが、建物調査診断から、工事会社のご紹介、見積取得、工事内容のチェック、契約、工事完了までをワンストップでサポートいたします。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)