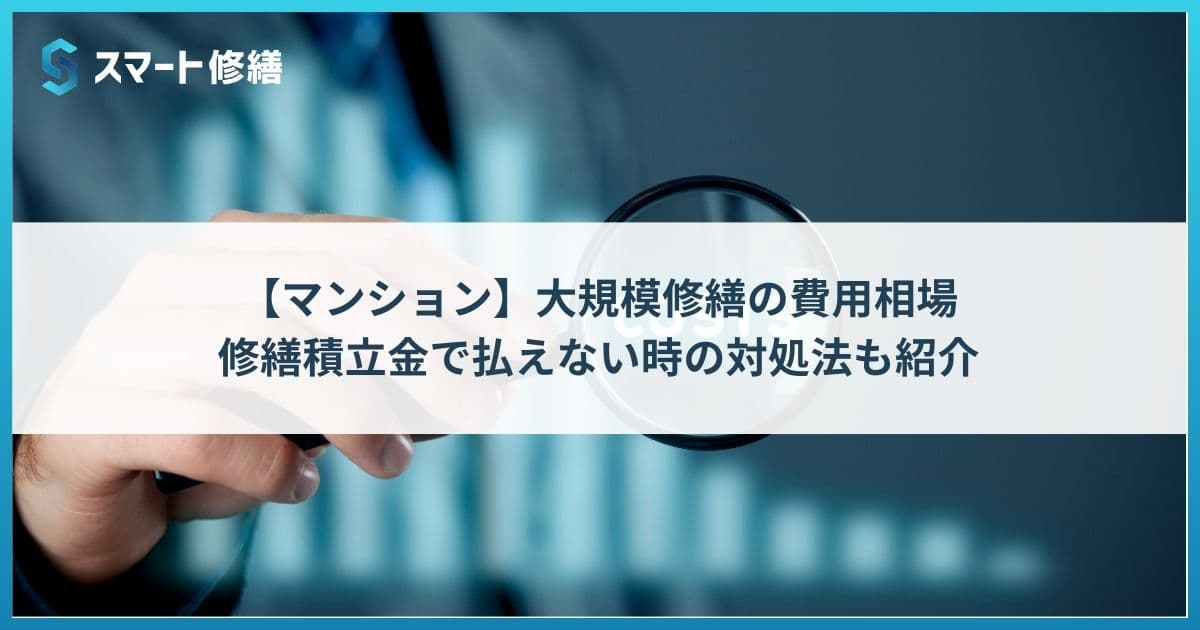炭素繊維シートの施工単価はいくら?耐用年数やデメリットもわかりやすく解説
更新日:2025年08月29日(金)
マンションなどコンクリート建物の耐震補強手法として注目される「炭素繊維シート工法」。その施工単価(費用)はどのくらいなのか、耐用年数(寿命)はどれほど持つのか、そしてメリット・デメリットは何か――マンションオーナーや管理組合の皆様が気になるポイントをわかりやすく解説します。
- 本記事のポイント
- 施工単価と耐久性の目安がわかる。
- 軽量で短工期、高耐久な工法のメリットを理解できる。
- 注意すべきデメリットとコスト削減手段を学べる。
炭素繊維シートとは?高強度で軽量なコンクリート補強材
炭素繊維シートとは、炭素繊維で作られたシート状の補強材で、既存の鉄筋コンクリート構造物に貼り付けて耐震補強などを行うものです。極めて軽量かつ高強度であることが特徴で、例えば比重は鉄の約1/4しかなく、引張強度(張力に耐える強さ)は鉄の約10倍にも達します。エポキシ系の含浸接着樹脂(専用の接着剤)を用いてコンクリート表面に貼り付け、繊維シートをコンクリートと一体化させて補強効果を発揮します。
炭素繊維シートは1995年の阪神・淡路大震災後に耐震補強工法として本格的に導入され、多くの実績を積んできました。その用途は幅広く、建築物の柱や梁、壁板の補強はもちろん、橋梁の桁(ガーダー)や橋脚、トンネル、煙突など土木構造物にも適用されています。
鉄板を巻く工法やコンクリート増し打ちによる補強に比べて、炭素繊維シートは重量が増えないため建物への負担が少なく、耐食性にも優れる(錆びない)点で有利です。
炭素繊維シートの耐用年数:少なくとも50年は効果が持続
炭素繊維シートの耐用年数は非常に長く、少なくとも約50年は耐久性があるとされています。
これは、実験室での促進劣化試験(厳しい環境を人工的に再現する耐久試験)の結果から得られた知見です。その試験によれば、炭素繊維シートで曲げ補強した部材は50年間は性能を維持でき、その間に再補強の必要はないと考えられることが報告されています。つまり、一度適切に施工すれば、通常の使用環境下で半世紀程度は補強効果が持続する見込みです。
さらに炭素繊維シートは材料自体が炭素繊維(CFRP)とエポキシ樹脂の複合体でできており、鋼材のように腐食(サビ)しないため耐久性に優れています。ただし、長期間にわたり補強効果を保つには、施工後の適切な保護処理も重要です。例えば、シート表面に仕上げ材(表面保護材)を塗布しておくことで、紫外線や外的な衝撃から炭素繊維シートと接着樹脂を守り、補強効果を長続きさせることができます。
このように適切な施工と保護を行えば、炭素繊維シートは建物の残り寿命に匹敵する長期間にわたって耐震補強効果を発揮し続けると期待されています。
炭素繊維シートの施工方法:下地処理と貼り付けの手順を解説
炭素繊維シート工法による耐震補強は、比較的簡易な施工手順で行えるのも特徴です。以下に、一般的な施工の流れをステップごとに説明します。
事前調査と下地処理
補強対象となるコンクリート部材の劣化状況を調査し、浮きやひび割れがあれば下地補修を行います。具体的には、浮いているモルタルや劣化したコンクリート片をはつり取る(ケレン作業)など、表面を健全な状態に整える作業です。
また、大きなひび割れはエポキシ樹脂の注入やポリマーセメントモルタルでの埋め戻し等で補修します。必要に応じて段差や凹凸を樹脂系パテで平滑にならし、不陸調整を行います。
プライマー(下塗り剤)の塗布
下地処理後、コンクリート表面にエポキシ樹脂系プライマーをハケやローラーで塗布します。プライマーは接着剤の密着性を高める下塗り材で、これを塗ることで後工程の炭素繊維シート接着剤(エポキシ樹脂)の性能が十分に発揮されます。プライマー塗布後は所定の時間乾燥させます。
炭素繊維シートの貼り付け
設計に従い必要なサイズにカットした炭素繊維シートを、補強箇所に貼り付けます。通常、シートを貼り付ける際にはエポキシ樹脂系の含浸接着剤を用います。施工者がシートに樹脂を含浸させながら圧着し、コンクリート表面に密着させていきます。柱の場合はシートをぐるりと巻き付け、継ぎ目で適切に重ね代(ラップ長)を確保します。梁や壁の場合も、必要であれば複数面にわたってシートを貼り付けます。設計で指示された層数だけ、1層ごとに同様の手順で貼り重ねることもあります。
仕上げ処理
シート貼り付け後、表面にトップコート(仕上げ塗装)を施します。前述のような保護塗料(仕上げ材)を塗布することで、シートや接着樹脂を紫外線や湿気から守り、耐久性を向上させます。外観上も周囲のコンクリート面と馴染むように仕上げることで、美観に配慮します。
以上が基本的な施工方法です。
炭素繊維シート工法は騒音や粉塵も少なく(コンクリートを大きく壊す作業がないため)、比較的短工期で済むことが利点です。ただし施工にあたっては、接着不良やシートの浮きが生じないよう、コンクリート表面の清掃・乾燥や樹脂の調合などを専門業者が慎重に管理する必要があります。また、柱に壁が接している場合などシートを途切れなく巻けない箇所では、あと施工アンカーを併用してシート端部を定着させる工夫(CFアンカー工法など)も行われています。
炭素繊維シートの施工単価はいくら?相場は1平米あたり約3万円~
肝心の費用について、炭素繊維シート工法の施工単価(㎡あたりの工事単価)はおおよそ3万円台からとされています。ただし、使用するシートの種類や貼り付ける層数、工法の仕様によって変動します。参考までに、建設資材の公表価格データ(2025年版)によれば、例えば東レ社の「トレカクロス工法」という炭素繊維シート補強工法では1層貼りの場合で1㎡あたり29,040円、2層貼りで44,940円、3層貼りで61,550円という価格が示されています。別の製品例でも概ね1㎡あたり3~4万円前後が単層の目安となっており、シートを重ねる層数を増やすと比例して高くなり、3層では約8~10万円/㎡程度になるケースもあります。
以上はあくまで工法ごとに設定された標準的な公表単価であり、実際の見積もりでは下地補修の範囲や施工箇所の高さ・数、作業の難易度(狭所作業の有無など)によって増減します。また、小規模な工事では単価が割高になる傾向があり、大面積を一括施工する方が単価は割安になる場合もあります。
いずれにせよ、炭素繊維シート工法は従来の鉄骨ブレース増設やRC増し打ち工法などと比較して仮設や廃材処理コストが低減できる面もあるため、トータルでは経済的メリットを期待できる補強方法と言えるでしょう。
炭素繊維シートによる耐震補強のメリット
炭素繊維シート工法には数多くのメリットがあります。ここでは主なメリットを3つ、その根拠とともに説明します。
メリット1:軽量なのに高強度で、建物への負荷が小さい
炭素繊維シート最大の利点は「軽くて強い」ことです。シート自体は薄く重量もわずかで、構造体に貼り付けても建物全体の重さへほとんど影響を与えません。実際、炭素繊維シートの比重は鉄の4分の1程度と非常に軽量である一方、引張強度は鉄の約10倍にも達する高強度材料です。このため、補強材として必要な強度を発揮しつつ建物自重を増加させない理想的な改修が可能です。
また、軽量であることは施工時の扱いやすさにもつながります。重機で重量物を運搬する必要がなく、人力でシートを持ち運びできるため狭い場所でも施工可能です(※鉄板補強では鋼板の搬入・溶接に重機や大掛かりな作業が必要でした)。結果として、居住中の建物でも比較的容易に施工でき、住民への負担が少なくて済みます。
メリット2:騒音・粉塵が少なく工期が短い
炭素繊維シート工法は、耐震壁の増設や鉄骨ブレース設置などに比べて施工時の騒音や粉塵が格段に少ないことがメリットです。コンクリートを大規模に解体・削孔する工程がないため、ドリル騒音や粉塵発生が抑えられ、工事中の周辺環境への影響も軽減されます。マンションであれば居住者が生活しながら施工する場合でも、騒音・振動によるストレスが比較的小さくて済みます。
さらに、工期が短い点も見逃せません。シート貼付は硬化待ちの時間を除けば迅速に進めることができ、増設壁工法のようにコンクリ打設後の養生日数を長く取る必要もありません。工期短縮は人件費や仮設足場の使用期間短縮にもつながるためコスト面でも有利ですし、入居者にとっても日常生活への制約期間が短くて済む利点となります。
メリット3:錆びないため高耐久でメンテナンス性が良い
炭素繊維シートは非金属材料であり、水分や塩分によって錆びることがありません。この点は鋼材を用いた補強(例えば鋼板接着や鉄骨ブレース)と大きく異なるメリットです。炭素繊維シートとエポキシ樹脂からなるFRP補強材は腐食の心配がなく、耐久性に優れます。そのため、将来的な補強材自体の劣化が少なく、長期にわたって補強効果を維持できます。
また、錆びないことで維持管理の負担も軽減します。従来の鉄骨ブレースだと定期的な防錆塗装の塗り替えなど維持管理が必要でしたが、炭素繊維シートにはそうしたメンテが不要です。さらに、シート厚みはわずか数mm程度で仕上がりがコンパクトなため、室内側に補強を行っても居住空間をあまり狭めずに済みます。外観についても、コンクリート壁面と同色の仕上げ塗装を施せば補強跡がほとんど目立たず、美観を損ねにくい利点があります。
以上のように、炭素繊維シート工法は軽量高強度・施工性・耐久性の面で優れ、多くの建築・土木構造物の補強に有効な手法です。
炭素繊維シートによる耐震補強のデメリット
優れた炭素繊維シート工法にも留意すべきデメリットや限界があります。ここでは考慮すべき主なデメリットを4点挙げ、その内容を説明します。
デメリット1:下地コンクリートの強度・状態に依存する
炭素繊維シートの効果を十分発揮するには、貼り付け対象となる既存コンクリートがある程度健全で十分な強度を有していることが前提となります。極端に劣化が進んでいるコンクリートや、強度が低すぎる場合には、シートを貼ってもコンクリート側が先に壊れてしまい補強効果が得られません。そのため、国土交通省の指針では、連続繊維シート補強を適用するためには既存コンクリートの圧縮強度が少なくとも18N/mm²以上あること等が条件とされています。劣化が激しい場合は、先に断面修復(欠損部の補修)や増し打ちなどで下地を補強してからシートを貼る必要があります。
また、施工段階でも下地処理の良否が品質を大きく左右します。表面に浮きや脆弱部が残ったままだと局部的に剥離しやすくなり、想定通りの補強効果が出ない恐れがあります。そのためデメリットと言うより注意点ですが、信頼できる専門業者による丁寧な下地処理と品質管理が不可欠です。コンクリート面の乾燥状態や清掃状態にも敏感で、雨天時や低温時の施工は接着不良のリスクがあるため避けるなど、施工環境の管理も重要になります。
デメリット2:火災時の耐火性に課題がある
炭素繊維そのものは難燃性ですが、シートを貼り付けるためのエポキシ樹脂接着剤は高温下で軟化・劣化してしまいます。このため、シート補強を施した構造物が火災に遭遇すると、比較的低い温度域(一般にガラス転移点付近の数百℃程度)で接着層が性能を失い、補強効果が損なわれる可能性があります。実際、連続繊維補強工法に関して「耐火被覆なしでは火災時に連続繊維補強材はその強度を保てない」旨が指摘されています。この問題への対策として、必要に応じて難燃性の被覆材でシートを覆う、もしくは耐火塗料を塗るなどの処置を行うことが推奨されています。
建築基準法上も、耐火建築物の耐火区画等にFRP補強を施す場合には所定の防火措置が求められるケースがあります。従って、炭素繊維シート工法を採用する際は火災時の構造耐力低下について設計者が考慮し、必要に応じて防火対策を講じることが重要な課題となります。
デメリット3:十分な補強効果を得るには巻き付け条件に制約がある
炭素繊維シートは柱や梁にぐるりと巻き付けることで最大の補強効果(特にせん断補強や軸方向の拘束効果)を発揮します。しかし、建物の構造部材には壁付き柱やスラブ付き梁など、四方を開放できずシートを閉じた輪に巻けないケースも多く存在します。例えば柱の一面が壁に接している場合、その面でシートが途切れてしまい「閉合型」に巻けないため、シートの拘束効果が減少してしまいます。このように取り付く部材形状によって補強効果が左右される点はデメリットと言えます。
その対策として、先述したCFアンカー(炭素繊維ロープ状の定着材)を用いて、巻き付けられない部分でもシート端をコンクリート内部に固定する技術が開発されています。この工法によって壁付き柱や片面だけの補強でも大きな補強効果を得ることが可能となっていますが、アンカー施工には追加の穴あけ作業が必要であり施工がやや煩雑になる側面もあります。また、アンカーの品質は作業員の技量に依存しやすく、熟練者による施工管理が求められます。
デメリット4:材料費が割高で初期コストは高めになりがち
炭素繊維シート自体や専用エポキシ樹脂は高性能な反面、材料単価が高価です。そのため、同じ補強効果を得る場合でも、材料費ベースでは従来工法より初期費用が高くつくケースがあります。もっとも、FRP補強材は将来的なメンテナンス費を含めたライフサイクルコストで見ればメリットがあります。ただし当面の工事費用の捻出という面では、自治体の補助金等を活用しない限り一時的な負担が大きい点はデメリットと言えます。
また、炭素繊維シート工法は専門技術者による施工が必要で、現場条件によっては手間がかかる場合もあります。例えば、広範囲にひび割れ補修を伴う場合や、曲面・凹凸面への貼り付けには熟練した施工技術が必要です。そうした技術料や手間賃も含めると、単純な材料費以上に初期工事費が膨らむこともあります。しかし、この点も長い目で見れば、補強後の維持費が抑えられる利点とトレードオフであることを踏まえて判断すべきでしょう。
以上のように、炭素繊維シート補強には適用上の制約や注意点がありますが、これらは事前に把握した上で適切に対策・設計することで多くは解決可能です。総合的に見れば、デメリットを上回るメリットがある工法と言えるため、専門家と相談しながら最適な活用を図ることが大切です。
耐震工事のコストダウンの手法
耐震補強工事は決して安い買い物ではありません。しかし、工夫次第でコストダウンを図る手法がいくつか存在します。ここでは、マンションの耐震改修費用負担を軽減する主なポイントを紹介します。
自治体の補助金を活用する
国や地方自治体には、住宅や分譲マンションの耐震化を促進するための補助制度が用意されています。例えば自治体によっては、耐震診断・耐震設計・耐震改修工事それぞれに費用補助が出る場合があります。多くの自治体で耐震改修工事費の一部(例えば工事費の1/2や2/3)を補助しており、その結果実際の所有者負担額は工事総額の3分の1程度に抑えられているケースも少なくありません。補助金の上限額や条件は自治体ごとに異なるため、所在地の行政窓口に問い合わせ、利用可能な補助制度を漏れなくチェックしましょう。
足場費用を削減する
建物の外部で行う工事では、仮設足場の設置・解体に大きな費用がかかります。これを削減するため、最近注目されているのが無足場工法(ロープアクセス工法など)です。足場を組まずに高所作業車やブランコ作業で補強工事を行う手法で、足場設置費や組立解体の手間を省けるため、コストと工期の大幅な削減が期待できます。無足場工法は建物形状や立地条件によって適用可否がありますが、都心部の隣接距離が狭いマンションなどでは有効な場合があります。ただし高所作業の安全管理が重要となるため、実績のある専門業者に依頼する必要があります。
低コスト工法を選定する
耐震補強の方法は一つではありません。建物の状況によっては、工事内容を見直すことで費用を大きく圧縮できる場合があります。例えば、室内側から壁を補強する場合、在来工法では内装を一度解体して耐震壁を設置し、その後仕上げを復旧する必要がありました。しかし外壁を撤去せず外部から補強できる工法を採用すれば、内装や仕上げの復旧工事が不要となり工事費や工期を短縮できます。炭素繊維シート工法はまさに既存仕上げを大きく壊さずに済む工法の一つであり、このような低侵襲で効率的な工法を選ぶことがコストダウンに直結します。
改修工事を一体的に計画する
耐震改修だけを単独で行うより、他の改修・修繕と同時並行で実施するとコストを抑えられる場合があります。例えば、大規模修繕(外壁塗装や設備更新)と耐震補強を同じタイミングで行えば、足場を共用できたり、工事管理費用をまとめられたりします。その結果、個別に工事を行うよりも費用・工期ともに削減できることがあります。マンションの場合、長期修繕計画の見直し時に耐震補強も組み込んで、一体的な改修計画を立てると良いでしょう。
火災保険等の活用を検討する
補強工事そのものは保険適用外ですが、例えば地震による被害箇所を補修する際に耐震補強を兼ねる場合など、条件次第では保険金や減税措置が利用できることもあります。耐震改修後は地震保険料の割引が受けられる制度(耐震等級に応じた地震保険割引)もあるため、長期的な金銭メリットも考慮しましょう。
以上のように、費用負担を軽減する方法は複数存在します。特に補助金については情報収集が鍵となりますので、国土交通省や自治体の耐震化支援策を積極的に調べてみてください。工事内容についても複数の施工業者からプラン提案や見積もりを取り、費用対効果の高い手法を選ぶことが重要です。
まとめ:手法それ自体の見直しで安くなる!最適な耐震補強を選ぼう
耐震補強工事は、「手法それ自体の見直し」によって大きくコストを削減できる可能性があります。炭素繊維シート工法のように軽量・高効率な補強手法を採用すれば、補強効果を確保しつつ工事期間短縮や付帯費用削減によるコストダウンが期待できます。実際、従来工法では必要だった内装解体や長期の養生期間を省けるため、品質と安全性を維持しながら費用を抑えることが可能です。
さらに、公的補助の活用や施工計画の工夫によって、マンションオーナー・管理組合の負担は大幅に軽減できます。多くの自治体が耐震改修工事費の補助制度を設けており、上手に活用すれば実質的な自己負担を工事費総額の3分の1程度まで低減できるケースもあります。また、一度にすべてを改修するのではなく、優先順位をつけ段階的に補強することで予算内に収める戦略も有効です。
最後に大切なのは、建物の状況に適した最適な補強方法を選ぶことです。炭素繊維シート工法は多くのメリットがありますが、全ての場合に万能とは限りません。他の工法との比較検討や、構造専門家からのアドバイスも踏まえつつ、安全性・経済性・将来の維持管理まで見据えた賢い選択をしましょう。適切な手法を選び工夫を凝らすことで、耐震補強は決して過度な財政的負担とならず、安心・安全な住まいを実現することができるのです。ぜひ本記事の情報を参考に、満足のいく耐震補強計画を立ててください。安心な暮らしへの一歩を、コスト面でも納得のいく形で踏み出しましょう。
マンションの「建替バリュー」 を見える化する「スマート建替」
- 「スマート建替」は、マンションの「建替バリュー」がマップ上で分かる、ディー・エヌ・エー(DeNA)グループの無料のサービスです(特許出願中)。※建物を建て替える価値を自動で計算しマップ上で表示するWEBサービスは、日本初となります。(2024年6月・当社調べ)
- 「建て替えるべきか」、「耐震補強工事をするべきか」、「修繕工事をするべきか」、「それぞれの経済性の評価、検討プロセスはどうしたらいいのか」、といったお悩みを、スマート建替の専門的なアドバイスとサポートで解決します。
- 「耐震補強工事」「修繕工事」については、「スマート修繕」で各種支援をさせていただきます。「スマート修繕」では、担当コンサルタントが、建物調査診断から、工事会社のご紹介、見積取得、工事内容のチェック、契約、工事完了までをワンストップでサポートいたします。
電話で無料相談
24時間対応通話料・相談料 無料
Webから無料相談
専門家に相談する
本記事の著者

鵜沢 辰史
信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。
本記事の監修者
.png&w=640&q=75)
遠藤 七保
大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。
二級建築士,管理業務主任者
24時間対応通話料・相談料 無料

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)